■活字読了日記
2001
スティーブン・キング小説作法 スティーブン・キング:アーティストハウス:1600
 アメリカ人の実直なところは、このように自分のテクニックを多くの人にわかりやすく述べて行こうとする姿勢にある。決して秘伝としないところだ。キングは、小説作法といっても、決して一筋縄ではいかないテクニックで読むものを引きつける。
アメリカ人の実直なところは、このように自分のテクニックを多くの人にわかりやすく述べて行こうとする姿勢にある。決して秘伝としないところだ。キングは、小説作法といっても、決して一筋縄ではいかないテクニックで読むものを引きつける。
キングの特徴である部分は、かれの文体のリズムにある。このことをかれは認識しており、文体について延々と書かれているところが、他の小説作法とは違う。それがどれくらい見事なものであるかは、文末に挿入された短編の出だしを、第一校と二校と続けて書かれたものを読むと一目瞭然だ。翻訳文にも関わらず、明かにリズムが違うのだ。
他にも他の作者なら声高に自身の優れた点を自慢げに振り返るのだが、キングは淡々とその自出を述べる。母親に育てられ、貧乏の中大学へ行き、教職を続けながら書きつづけたこと。
自分が労働階級の出ということも自覚している。それが彼の作品を解くのもうひとつの鍵だと思う。
わたしは、本書とディーン・クーンツの「ベストセラー小説の書き方」(朝日文庫)を併読することをお薦めする。
テレビゲーム文化論 桝山寛:講談社現代新書:660
 長らく待たれた作者のテレビゲームに対する著作が遂に出た。予想以上の濃い充実した内容なので、コンピュータ文化関係の概論について学ぶには最適な書ではないだろうか。
長らく待たれた作者のテレビゲームに対する著作が遂に出た。予想以上の濃い充実した内容なので、コンピュータ文化関係の概論について学ぶには最適な書ではないだろうか。
作者はテレビゲームをエンターテインメントや技術などの狭い枠に留めようとせず、かといって大雑把なゲームの世界は日本が席巻しているという日経エンターテインメントのような煽りもしない。ゲームはどこから来てどこに行こうとしているのか。それを
文化状況、テクノロジーの進化から読み解く。
テレビゲームもカイヨワの遊びについての分析から外れていないこと。それでいて、「どこでもいっしょ」や「ポケモン」などの的確な分析。特にポケモンが欧米に受け入れられたのは、ゲームの出来もあるが、かわいいキャラクターを受け入れるようになった感性の変化もあったことを指摘する。
かれの読みとしては、いまのゲームは行きつくところに来てしまったという。これからは、肉体を持ったゲームが必要という。どう言う形かははっきりしないけれど。
著者がベルリンで行ったインタレスションが面白い。「トーキョー・テクノ・ツーリズム」 と題して、ゲーム空間のなかにあるトーキョーを見せることで、架空の東京を観光してもらおうと言う思考だ。もうひとつの東京体験だ。そこでは電車でGo!だったり、バーチャ・ファイターが秋葉原で行われたりする世界だ。
http://www.hotwired.co.jp/news/news/culture/story/1773.html
カリフォルニアオデッセイ5 ビーチと肉体 浜辺の文化史
海野弘:グリーンアロー出版社:2381
 このシリーズの第5弾はカリフォルニアを北から車で海岸沿いに下りて来る。そこにあるひとつひとつのビーチが、どのような背景から生まれてきたのかを示している。特にカリフォルニアの
ベニス・ビーチの変遷はカルフォルニア伝説のひとつだろう。
このシリーズの第5弾はカリフォルニアを北から車で海岸沿いに下りて来る。そこにあるひとつひとつのビーチが、どのような背景から生まれてきたのかを示している。特にカリフォルニアの
ベニス・ビーチの変遷はカルフォルニア伝説のひとつだろう。
香港の食の物語 辻村哲郎:主婦の友社:1800
 ジャッキーチェンの個人通訳として、また料理の鉄人をはじめさまざまなテレビ雑誌の取材コーディネーターを勤める作者が薦める、「香港には二度以上来ている人のため」の旅行ガイド
である。なかなか一筋縄に行かない香港の裏まで知り尽くしたひとだけが知る香港の姿が見えます。
ジャッキーチェンの個人通訳として、また料理の鉄人をはじめさまざまなテレビ雑誌の取材コーディネーターを勤める作者が薦める、「香港には二度以上来ている人のため」の旅行ガイド
である。なかなか一筋縄に行かない香港の裏まで知り尽くしたひとだけが知る香港の姿が見えます。
SAS特殊任務 ギャズ・ハンター:並木書房:2200
 作者は、輝かしいSASでの経歴の途中で、突如除隊してしまう。そして、そこにあるモノを、ソビエトが侵攻していたアフガニスタン
に運んで欲しいというアメリカ人が現われる。作者はパキスタンから国境を越えて山岳地帯を休まずに三日歩きつづけて、ゲリラ部隊に合流する。そこでソビエトを相手に戦うゲリラの姿。捕虜を虐殺する様子を目撃する。そしてようやくゲリラに持ってきた対空ミサイル砲の使い方を教える。
作者は、輝かしいSASでの経歴の途中で、突如除隊してしまう。そして、そこにあるモノを、ソビエトが侵攻していたアフガニスタン
に運んで欲しいというアメリカ人が現われる。作者はパキスタンから国境を越えて山岳地帯を休まずに三日歩きつづけて、ゲリラ部隊に合流する。そこでソビエトを相手に戦うゲリラの姿。捕虜を虐殺する様子を目撃する。そしてようやくゲリラに持ってきた対空ミサイル砲の使い方を教える。
ランボーでお馴染みのこの兵器をはじめて西側から運んだのが、かれで依頼したのがCIAということになる。本書の冒頭では、空飛ぶ戦車といわれているソビエト製のヘリ、ハインドに襲われるシーンが出てくるがこれが恐ろしい。
かれは途中で帰ってくるのだが、かれの報告で対空ミサイル砲が有効だとわかり、その後続々とゲリラに流れた。と作者は書いている。その後、再入隊するのだが、訳者は、これはSASの現役が参戦するのはまずいという政治的な策略があったのではと推測している。
ほかにも、コロンビアでの対麻薬カルテル、FBIとのテキサスのデビアン・ブランチの篭城へのアドバイサーとしての役割。そのおかげで湾岸戦争には参加できず、指揮官のいないかれのブラボー小隊は、壊滅的な打撃を受ける。その作戦失敗の様子は、「ブラボー・ゼロ」などにくわしい。
全面自供! 赤瀬川原平:晶文社:2840
 断片的にしか見えてこなかった赤瀬川が、カタログになって現われるお得な一冊である。「トマソン」から入った者としては、前衛作家としての赤瀬川のクレバーさに驚かされる。その大胆な思考が、本人のキャラクターとは異なり、帝都を揺るがす大犯罪者の末裔となって行く様がオカシイ。
断片的にしか見えてこなかった赤瀬川が、カタログになって現われるお得な一冊である。「トマソン」から入った者としては、前衛作家としての赤瀬川のクレバーさに驚かされる。その大胆な思考が、本人のキャラクターとは異なり、帝都を揺るがす大犯罪者の末裔となって行く様がオカシイ。
千円札裁判にしても、本物と偽者の違いはどこにあるんだろうという単純な発想が、偽札という国家の存在自体を揺るがせることになってしまう戯画化。これがハプニングだ!と言ったかはわからないけど。作者は密かに含み笑いをしていただろう。それは決して冷笑のたぐいではなく、ユーモアに近いものだと思う。そのセンスが文章として、不思議な手触りと味わいを感じさせる、「肌ざわり」、「父が消えた」などの尾辻克彦の作品に集結するのだろう。
赤瀬川原平を一言で言うなら、実験室で博士の横にいる、夢見がちな助手。だれも注目しないが、彼が試薬の計量を違えたために、実験は滅茶苦茶になり大混乱が起きる。でも彼は大真面目でこのコメディーの状況を笑えない。
控え目なマッドサイエンティストなのかもしれない。
転がる香港に苔は生さない 星野博美:情報出版センター:1900
 この街を生きる誰もが、驚くようなドラマチックな過去を持っている。著者はカメラマンであるが、中国本土返還またぐ時期に、香港に住みながら、大学の語学教室に通う。街に出て様々な人と語り合って行くうちに出てきた言葉が、冒頭のものだ。
この街を生きる誰もが、驚くようなドラマチックな過去を持っている。著者はカメラマンであるが、中国本土返還またぐ時期に、香港に住みながら、大学の語学教室に通う。街に出て様々な人と語り合って行くうちに出てきた言葉が、冒頭のものだ。
よく聞く本土から決死の思いをしてきて、下積みを重ねて店を持ち、カナダの市民権を得て移住する。という話は珍しいものではなく、ごく日常的であるのだ。そこにあるアグレッシブな現実性は、日本人には決して理解できないだろう。はじめて会ったオーストラリア市民権を持った華僑の独身男性に、結婚を迫る女性「だって、このチャンスを逃したらもう二度とないかもしれないじゃないの。とにかく結婚してよ」。
作者が再会するかつての大学時代のクラスメートの姿も様々だ。30歳に近い彼らも、大学のエリートとして社会に出たが、カナダに行って挫折して大学のプールでひたすら泳ぐ者、したたかに香港で金を貯める者。何かを吹っ切るように仕事に入れこむ者。だれもが物凄いスピードで動く現実のなかでもがいている。
そんな彼らは返還したらどうなるかの質問を笑い飛ばす。なにも変わらないよ。という彼らは、海外の市民権を持っていたりする。そんなかれらを見る著者の視線はやさしい。よそ者であるかもしれないが、まともな答えが返ってこないかもしれないけれど何故何故と尋ね苦笑される。国籍はどこなのだろうかと聞かれ、かれらはこう答える。わたしたちは香港人だと。おもわずこの本に出てくる人が今どうしているのだろうかと、ふと思う、そんな本だ。
シリコンバレー・スピリッツ 起業ゲームの勝利者たち デイビッド・A・カプラン:ソフトバンクパブリッシング:2200
 そこにカネがある。これは、シリコンバレーの成立から、ネットスケープが、ナビゲーターのシェアがマイクロソフトのエクスプローラーに食われ、没落する頃までを描いている。
そこにカネがある。これは、シリコンバレーの成立から、ネットスケープが、ナビゲーターのシェアがマイクロソフトのエクスプローラーに食われ、没落する頃までを描いている。
どこという特徴のない、サンフランシスコ郊外の土地に、人が集まり企業を興し、ある者は成功し、ある者は消え去る。そんな興亡の様子が淡々と描かれる。ここでは強烈な個性を持ったものがのし上がる。わずか数十年のあいだにかれらは生きた伝説となった。インテル、ヒューレット・パッカード、ネットスケープ、サン。ただコンピュータのOSの話ではなく、もっと
シリコンバレー自身の成り立ちと大立者の姿が余すところなく描かれる。かれらの思ったことのひとつひとつが今も世界の流れを決めていると言っても良いだろう。どう考えても日本人には真似できないシリコンバレー人種の生き方とマネーゲームが虚飾を剥ぎとられて見ることができる。非常にまっとうなノンフィクションである。ビジネス書ではない。
カポーティー ジェラルド・クラーク:文藝春秋:6000
トルーマン・カポーティー ジョージ・プリンプトン:新潮社:3500

 ひとりの作家の生涯を描くのに、二冊の本は相互に補完し合っている。それぞれの描く作家像は、同じ人物かどうか疑うくらいに違う。いや、それぞれが描こうとする人物像はそれほど違っていない。猥雑で有名人が好きで、俗物でありながら繊細な部分もある。そんなポートレイトではある。
ひとりの作家の生涯を描くのに、二冊の本は相互に補完し合っている。それぞれの描く作家像は、同じ人物かどうか疑うくらいに違う。いや、それぞれが描こうとする人物像はそれほど違っていない。猥雑で有名人が好きで、俗物でありながら繊細な部分もある。そんなポートレイトではある。
しかし二冊の本から浮かび上がろうとする作家の姿は、そこに収まりきらない魅力を持っている。どうしようもない通俗さを持ちながら、あれだけの言葉を探し出してくる作家。自らの美しさを武器にして現われ、その神話に押しつぶされる晩年。道化を演じてまで、もぐりこんだ上流社会。でも彼らのスキャンダルをどうしても書きたくなった作家としての性。喩え、それがかれを社会的に抹殺することもあるとしても。端から見れば明白な自殺行為なのに、実は作家自身はそのことに気づいていなかった。ちょっといたいたずらと思っていた。やがて、作家は彼の頭の中にしかない次作のアメリカ文学の傑作を、何度も人に聞かせる。もしかしたら自分でももう書いてしまったと思っていたのかもしれない。
「冷血」を書いただけで、アメリカ文学史に残る仕事をしているのだが、ちびででぶなホモのおしゃべりが許せない人々はいた。彼自身、まったく政治や社会には無頓着だったけれど、社会は彼を放っておいてはくれなかった。まあ彼自身名声やスポットライトを求めつづけていたということもあるけれど。
複雑な人物像を描くのに、従来の伝記の方式と、関係者へのインタビューという、異なった手法が取られている。記憶違いもあり、カポーティ像はますます不明瞭になっていく。読み終わった後には、かれのことがわかるのではなく、新たなカポーティー神話に荷担している自分に気づく。
孫正義は倒れない 吉田司+アエラ取材班:朝日新聞社:1500
 ビジネス礼賛本か、週刊誌暴露本か、という二者択一しかなかった、現在進行形の人物評伝の世界にようやっと、すこしはまともな本が出たことは非常に喜ばしい。これが
この手の本のスタンダードとなることを期待する。というか少なくともこの本のレベルを指針としてほしい。
ビジネス礼賛本か、週刊誌暴露本か、という二者択一しかなかった、現在進行形の人物評伝の世界にようやっと、すこしはまともな本が出たことは非常に喜ばしい。これが
この手の本のスタンダードとなることを期待する。というか少なくともこの本のレベルを指針としてほしい。
本書は、吉田司による、縦横な推論を含めた、孫正義のルーツからの展開を踏まえながら、孫個人の考えを探り、アエラ編集部による、客観的な部分(評論家インタビューなど)を固め、さらに東海大学教授による、資料からみるソフトバンクの仕組みを解説している。それぞれに読み応えがあり、
読者がさらに推論するのに、的確な資料を与えてくれる柔軟性を与えてくれている。
内容は、本書を読んでいただくとして、今後ソフトバンクがどうなるにせよ、現在形の分析としてはバランスの取れたものとなっていると言える。ソフトバンク商法の中味とか、孫のインターネット財閥を、新興財閥のかたちとして、昭和初期の類似する事例を引き出すなど、非常にオーソドックスな方法を取っている。
また結論として、日本での彼の異端さ、アメリカのインターネット企業では普通のやり方であり、Yahoo!の株価がソフトバンクが支えていると喝破する。多くの会社に投資してもどれかが当たれば良いと考えているだけだとも。また株価の儲けだけで会社を維持している企業というのも他に見当たらないことも疑念を示している。
ただ巻末の石川好との対談がいるかは、どうだろうかね?あと索引が欲しいところですね。
幻滅への戦略 グローバル情報支配と警察化する戦争
ポール・ヴィリリオ:青土社:1600
 ジャン=ボールド・リヤールは中東の戦争中に「湾岸戦争はなかった」と書いて、非難を受けまくって、その学者生命を危機に晒した。その後の状況をみていると、かれの発言はあながち間違いではなかったと思う。しかし現実の戦争(たとえテレビでしか見ていないにしろ)、に対して、不可視の戦争を提言しては分が悪すぎた。消え行くメディアの上では、感情にかなうものはないからだ。
ジャン=ボールド・リヤールは中東の戦争中に「湾岸戦争はなかった」と書いて、非難を受けまくって、その学者生命を危機に晒した。その後の状況をみていると、かれの発言はあながち間違いではなかったと思う。しかし現実の戦争(たとえテレビでしか見ていないにしろ)、に対して、不可視の戦争を提言しては分が悪すぎた。消え行くメディアの上では、感情にかなうものはないからだ。
本書は、コソヴォに対する、国連無視のNATO軍の空爆に対する答えとして書かれた。ボールルド・リヤールを意識しないことはなかったろうことは想像できる。
現実に対するリアルタイムの事象では、簡単に割り切ることができないし、ここでは彼独特の言葉は禁じ手にしている。
非常に丁寧な手法でひとつひとつ、状況を解読して行く。そこに現われたものは、「戦争は政治の延長である」とした地政学の始祖クラウゼヴィッツの言葉はすでに消え去り、戦争のための戦争、宣戦布告なしの戦争である「純粋戦争」が台頭している
ことを示している。
空爆という領土無しの戦争は、イラクに続いて適応され、なんのための戦争なのだかわからない兵器の見本市に終わった。現在のNATOとアメリカの対立の遠因にはこの空爆があるといってもよいだろう。
クリントンは最後まで「紛争」と言い続けた、しかし欧州の認識ではあくまでも「戦争」だったという。ここには倫理観に対する危機が、内在していることを意味しているのではないか。
アメリカ合衆国の国内的な正義感が世界のスタンダードになるという、均質性(グローバリゼーション)の柔軟性のない世界が待っているのではないだろうか。
なぜこの店で買ってしまうのか ショッピングの科学 パコ・アンダーヒル:早川書房:1800円
 本書はものを売るための指南書ではない。もうひとつ余分に買わせるための指南書である。もっとも、どのような方法を取るにせよ、売上が上がることには変わりはないのだが。それを著者は「衝動買いの重要さ」として上げている。もはや情報やものが行き渡った社会では、消費者が商品についての知識は持っており、商品は、在庫がちゃんとあれば、勝手に客が選んで買われる。問題はその客にもう一度財布を開かせることだ。そのためにはレジの近くに安いこまごまとした商品を置いたり、通路を迂回させて、他の商品に目がいったりするようにする。などのヒントが多く書かれている。
本書はものを売るための指南書ではない。もうひとつ余分に買わせるための指南書である。もっとも、どのような方法を取るにせよ、売上が上がることには変わりはないのだが。それを著者は「衝動買いの重要さ」として上げている。もはや情報やものが行き渡った社会では、消費者が商品についての知識は持っており、商品は、在庫がちゃんとあれば、勝手に客が選んで買われる。問題はその客にもう一度財布を開かせることだ。そのためにはレジの近くに安いこまごまとした商品を置いたり、通路を迂回させて、他の商品に目がいったりするようにする。などのヒントが多く書かれている。
著者は、社会学者ウイリアム・H・ホワイトのもとで公共空間について学んだあと、徹底的なフィールドワークで、店内の客の行動、流れ、消費傾向を観察する。その徹底さは、以前8mmカメラのフィルム消費量が全米のトップテンに入ったという事からも窺える。
いんちきコンサルタントのビジネス書、御託を聞くよりは、非常に効果的、実践的な書だと思う。いま店をやっている人には非常にお薦めです。
ただネット関係については考察がいまひとつです。
子どもを殺す子どもたち デービッド・ジェームズ・スミス:翔泳社:1800円
 神戸の事件が起きた時に世界の事例として取り上げられたのが、リバプール郊外に住む、8才の少年2人が、2才のこどもを殺害したこの
ジェームズ・バルガー殺人事件だ。すでにふたりは8年の刑期を終え保護観察処分で出所して、名前を変えて生活しているという。
神戸の事件が起きた時に世界の事例として取り上げられたのが、リバプール郊外に住む、8才の少年2人が、2才のこどもを殺害したこの
ジェームズ・バルガー殺人事件だ。すでにふたりは8年の刑期を終え保護観察処分で出所して、名前を変えて生活しているという。
このときのマスヒステリーもものすごい取材合戦だったらしい。メディア王マードックが所有する「サン」が一番すごく、実名写真入りをやったらしいけど。まあネットをさがせば、本名は出てくるだろうけど。
なにが問題になったかというと、子どもを裁判にかけるときに、「はたしてかれらは裁判の意味を理解できるのか」
という点だった。意味を理解できないものに判決を言い渡せるのか。これについては意見が別れたようだ。日本でも少年を成人と同じに裁く際に、今後出てくる問題であることは確かだ。この点については結論は出ていないことも確かだ。
独立書評愚連隊 天の巻 大月隆寛:国書刊行会:2000円
独立書評愚連隊 地の巻 大月隆寛:国書刊行会:2000円

 「言うだけ番長」これが、作者には一番似合う渾名ではないだろうか。天の巻では、作者の属するフィールドワーク、民俗学、文化人類学の書評。地の巻では、マンガ、一般の本、特に90年代の同時代の作者に対する書評。そこに底通する罵倒は、芸としても未熟であり、読んでいて鼻白む。はたして、
大月はかれの仕事に対して他者が同じような罵声を浴びせた時に耐えられるような仕事をしているのだろうか。これが第一の疑問。
「言うだけ番長」これが、作者には一番似合う渾名ではないだろうか。天の巻では、作者の属するフィールドワーク、民俗学、文化人類学の書評。地の巻では、マンガ、一般の本、特に90年代の同時代の作者に対する書評。そこに底通する罵倒は、芸としても未熟であり、読んでいて鼻白む。はたして、
大月はかれの仕事に対して他者が同じような罵声を浴びせた時に耐えられるような仕事をしているのだろうか。これが第一の疑問。
また、付記のカタチで書かれている。業界の暴露裏話的なコメントは、けっきょく彼の言説はせまいマスコミ業界のなかでしか流通しない
ことをあらわしているのではないだろうか。いわばお座敷芸じゃなかろうか。他人の暴露話をするのであれば、問題となった2チャンネルのネタを鵜呑みした自身の事件について検証すべきではないだろうか。どっかに書いてあるかと期待したが書いていなかった。そこらへんをネグって田口ランディとか、攻撃しても仕方ないと思うんだけど。これが第二の疑問。
そこから敷衍した問題で、作者は<いま・ここ>という問題に、多くのダメな本や学問が対応していないという。<いま・ここ>という問題はジャーナリスティックな問題提起の仕方であって、その問題はそのまま作者の仕事に対して跳ね返ってくるとおもうのだけど、その点について作者は無自覚ではないだろうか。けっきょく作者は、どのスタンスでどんな仕事をするのかが問われるとおもう。それにはまったく答えていない。在野、スタンドアロンの知性となるには、もっと黙って仕事をしてほしい。
やはり、「大月隆寛」の書評と、冠がつかないと商品として成立しないのが一番問題だとおもう。
レクサスとオリーブの木 グローバリゼーションの正体 トーマス・フリードマン:草思社:1800
 いわゆるグローバリゼーションについて、胡散臭さを感じているのはわたしだけだろうか。グローバリゼーションを考える時に、トヨタのレクサスのように、全世界規格を目指すのか、それとも裏庭にあるオリーブの木を大切にするのかを国際ジャーナリストの視点から見てみるという謳い文句なのだが、どうも乗りきれずに最後まで読んで行くと、あーら吃驚、「グローバリゼーションは必然で、アメリカは一番進んでいる。だから世界に対して指導的な地位を占めるべきだ」の一節で閉じられている。なんだ、
カタチを変えたグローバリゼーション礼賛書じゃねえか。
いわゆるグローバリゼーションについて、胡散臭さを感じているのはわたしだけだろうか。グローバリゼーションを考える時に、トヨタのレクサスのように、全世界規格を目指すのか、それとも裏庭にあるオリーブの木を大切にするのかを国際ジャーナリストの視点から見てみるという謳い文句なのだが、どうも乗りきれずに最後まで読んで行くと、あーら吃驚、「グローバリゼーションは必然で、アメリカは一番進んでいる。だから世界に対して指導的な地位を占めるべきだ」の一節で閉じられている。なんだ、
カタチを変えたグローバリゼーション礼賛書じゃねえか。
けれど他HPなどを読むと、課題図書かなんかになっているらしく、ここからグロバリゼーションの勉強をはじめましょう的なノリが多い。
ここからグローバリゼーションの議論をはじめることは間違いだと思う。この上下巻のなかには、明らかにミスリーディングを誘う要素が多すぎる。視点が近視眼的であり、誘導的である。あまりにも現象面から物事を見過ぎではないだろうか。これはあくまでも一ジャーナリストが見たある局面でしかないのに、あまりにも普遍的な事象に敷衍されすぎている。
たしかに「黄金の拘束衣」というキーワードのように、豊かになるためには、自由を拘束されるのは仕方がないし、そちらの方向にしか世界は動かないという説はおもしろいし刺激的だ。しかしそのアメリカ的な見方をアジア、中東に「そうしないと経済は破滅だ」という黙示録的な言いまわしで伝えることには疑問を感じる。
古い閉鎖的な市場でなく、開かれた市場にしないと、海外投機家が来なくなって、資金が国に入らなく、豊かにならないよと脅しながら、ロシアやマレーシア、タイ、韓国のように株価が暴落した場合は、開示が不徹底で魅力的ではなかったのだと斬る。どこか、アメリカのやり方だけが正しく、アメリカの投資家のために市場を開きなさい。そうすればオコボレがくるからという言い方にしか聞こえないのだ。
ジャーナリストの書く文章としては、レクサスが非常に魅力的で、オリーブの木は守りたいけど、世界の流れではねえと、投げやりな態度が気になるし、自身も儲けるために投機をしているとなると、システムは疑わないよな、ということだ。
アメリカの見方がどうなっているかを知るには良い本だと思うが、グローバリゼーションについては、何が問題だか、なにもわからない本だと思う。アメリカ=グローバリゼーションと思われても仕方がない部分が多すぎる。
東京アンダーワールド ロイ・ホワイディング:角川書店:1900
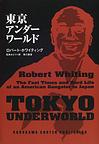 あっと驚くような人物が出てくるわけでもない。ものすごいドラマがあるわけでもない。ただ丹念にその人物を追いかける手法がロイ・ホワイディングの作品を支える。
あっと驚くような人物が出てくるわけでもない。ものすごいドラマがあるわけでもない。ただ丹念にその人物を追いかける手法がロイ・ホワイディングの作品を支える。
戦後のどさくさをチャンスと思ったニューヨーク育ちのイタリア系アメリカ人がたどった人生を縦軸に、そこに交錯する
在日外国人を横軸にして、六本木、赤坂という歓楽地が舞台で生臭いもうひとつの日本史がみえてくる。
作者の日本観に賛同するか否かで、楽しめるかどうかが分かれるだろう。極端な被差別感を軸に日本を書き続けている。日本人からみるとそこには、別のバイアスがかかっていると感じられる。この本がいま一つ読まれなかった理由ののひとつと言えるだろう。
かれらの眼からみると、いまでもフジヤマ・ゲイシャの国なんだろうな。そのハリウッド映画的な変わりない視線に戸惑いも覚える。(だからスコセッシが映画にするのかな)
花森安冶の編集室 唐澤平吉:晶文社:2100
 「暮らしの手帖」の名編集長のもとで、数年間働いた著者がから見た、花森像である。限定された編集の現場、名功成ったかれをみる作者の視線は、包括的ではなく断片的な記憶からなる。
「暮らしの手帖」の名編集長のもとで、数年間働いた著者がから見た、花森像である。限定された編集の現場、名功成ったかれをみる作者の視線は、包括的ではなく断片的な記憶からなる。
こういう本もよいとは思うけど、人物像が湧き上がるほど鮮烈なものではない。終始、平身低頭な作者の態度は、出し遅れた追悼文のようなもので読者にはなんの刺激も与えない。どうせなら、かれの仕事をCD-ROMのようなカタチで提供してもらえれば、その方が読者には自由度があるだろう。
いまこのような本はだれも必要としていないと思う。もっとちゃんとしたカタチでの花森安冶像を見てみたい。
グリーンスパン ボブ・ウッドワード:日本経済新聞社:2300
 世界で最も謎で、その発言に影響力のある人物、アメリカ連邦準備銀行(FRB)理事の、アラン・グリーンスパンの、理事になってからクリントン時代までのあいだに何が起こり、何を決断し、なにを決断しなかったのかを、本人以外の関係者へのインタビューや公開記録を基に構成した書である。作者ボブ・ウッドワードは、湾岸戦争への開戦プロセスを明らかにした「指導者たち」と同じ手法を駆使する。
世界で最も謎で、その発言に影響力のある人物、アメリカ連邦準備銀行(FRB)理事の、アラン・グリーンスパンの、理事になってからクリントン時代までのあいだに何が起こり、何を決断し、なにを決断しなかったのかを、本人以外の関係者へのインタビューや公開記録を基に構成した書である。作者ボブ・ウッドワードは、湾岸戦争への開戦プロセスを明らかにした「指導者たち」と同じ手法を駆使する。
その精密な取材から浮かび上がるグリーンスパン像は、ブラックマンデー、赤字削減、株式市場の拡大、ハイテク景気など、さまざまな変化にすべてついて来る実行力。ほとんど宗教的とまでいえる、数字への執着。銀行関係者から大統領までもねじ伏せる、そのマキャベリストの手腕。複雑怪奇な結論の無い経済動向に神のような宣託を述べるかれというスタイルがいまの世界経済を動かしているといっても過言ではない。
テレビニュースで現れるかれの言っていることや、公定歩合がといわれてもなにもわからないけれで、本書を読めば、そのプロセスを知ることができ、興味深く経済ニュースを見ることができる。「グリーンパン神話」、これもまた新しいアメリカの神話のひとつだろう。
麻薬脱出 250万人依存者の生と死の闘い 軍司貞則:小学館:1500
 かれのノンフィクションは伝えたい事象に対して通俗化することをおそれないし、対象を求め作者が希薄になっても構わない。昨今の作者が煩わしい似非ノンフィクション作家とは歴然と違う。題材にしてもすぐ「スーパーテレビ特捜最前線」にネタとしてパクラれそうであっても躊躇しない。そこには伝えることに対する潔さがあるので読みやすいし、押し付けでないので読者自ら考える余地がある。
かれのノンフィクションは伝えたい事象に対して通俗化することをおそれないし、対象を求め作者が希薄になっても構わない。昨今の作者が煩わしい似非ノンフィクション作家とは歴然と違う。題材にしてもすぐ「スーパーテレビ特捜最前線」にネタとしてパクラれそうであっても躊躇しない。そこには伝えることに対する潔さがあるので読みやすいし、押し付けでないので読者自ら考える余地がある。
本書は、麻薬に対して断罪はない。劇的な部分もない。ただ何人かの麻薬依存者、薬物依存者がどのように生まれ、家族やまわりの人間を巻き込みすべてを崩壊していくか。その様子を綴った部分とそこから脱出しようとする人間が同じ視点から描かれている。
また薬物依存の渦中にある人々への救いを差し伸べる手引きの書の役割も果たしている。
ダルクという施設をご存知だろうか。アルコール依存者ではなく、薬物中毒者だけの治療更正施設
だ。いまは全国にあるが、最初にはじめた人物も薬物依存者だ。けっして過去形にならないのは自らその誘惑への恐れを隠すことができないし、自分の弱さを認めないと施設の運営などできないという、慈悲とリアリズムを両天秤にかけなければならないことをよくわかっているのである。運営者の近藤は言う。「この施設に来て回復したのは三割、一割は死にました。あとの三割は行方不明。残りは刑務所か精神病院」「施設に来てからも、すぐに薬物を断てた人間はふたりだけ。あとは必ず一度は薬物依存する」。もちろん近藤も依存者。かれがダルクを作れた背景にある神父の存在があり、カトリックへの帰依もあるが、この本の中では、キリストも聖書もあえて省かれている。なぜなら
神へ依存することが解決ではないからだ。
また、近藤が薬物の世界に引き込んだ、全身刺青の元ヤクザがダルクの所長になる様子が語られていて感動的だ。
薬物依存は、その人間がだめだからではなく、精神も含めた病気なので必ず治る というひとことで立ち直ることができたという。
もう一例、長男がシンナー中毒になり、35歳まで復帰できず、両親の家庭も仕事も崩壊し、新しい人生を歩もうとする家族の様子が描かれ壮絶だ。成長期にシンナーを濫用するとほとんど脳みそが溶けて復帰するのはまず不可能という。
近藤は「ダルクに来るのは、ほとんど男性なので一概には言えないが、家庭環境が、ワーカホリックで家庭を顧みない父親と、息子をかばう母親、よくできるもうひとりの兄弟が父親と一緒になって攻め立てる場合が多い
」と言う。本当に立ち直らせたいのなら、親は仕事を畳み、親子の縁を切り息子を切り離せという。乱暴だが、(依存=金銭的最新的へ)それが真の解決だと言うことが読んでいるうちにわかる。
さいごに、「薬物を一度でもする可能性はあるし、してしまっても、問題は更正の施設、プログラム、対処窓口がわからないのが現状だ。薬物防止キャンペーンだけに多額の金額を使うのは片手落ちではないだろうか」と疑問を呈する。
伝えるべきことを伝えようとする軍司の次作は「中途失明」をテーマにするという。
機会不平等 斎藤貴男:文藝春秋:1619円
 バブルの終わりのころ、ある人と議論になり、このあとの日本はどんな社会になるかとの問いに、わたしが「これからは、特権意識と金銭意識がはっきりと分かれ、階級社会になる」と言ったのに対し、かれは「いや、階層社会になるだろう。それは日本にはヨーロッパのように階級がはっきりとないからだ」と反論した。なるほど確かに「一億総中流」になったバブル期、そのあとにはいままではっきりとして見えなかった社会格差が見えてくるだろうという部分では同じことを言っていたわけで、ようするに
「持つもの」と「持たざるもの」はとてつもなく大きな差になって社会的に認知されてくるだろうという結論だった。ただそれをどう呼ぶかでのヲタクと団塊での意識の差はあったと思うが。
バブルの終わりのころ、ある人と議論になり、このあとの日本はどんな社会になるかとの問いに、わたしが「これからは、特権意識と金銭意識がはっきりと分かれ、階級社会になる」と言ったのに対し、かれは「いや、階層社会になるだろう。それは日本にはヨーロッパのように階級がはっきりとないからだ」と反論した。なるほど確かに「一億総中流」になったバブル期、そのあとにはいままではっきりとして見えなかった社会格差が見えてくるだろうという部分では同じことを言っていたわけで、ようするに
「持つもの」と「持たざるもの」はとてつもなく大きな差になって社会的に認知されてくるだろうという結論だった。ただそれをどう呼ぶかでのヲタクと団塊での意識の差はあったと思うが。
本書は、これからの何十年かに向けての現在からみた鋭いレポートである。
6つの章からなり、それぞれ「ゆとり教育」と「階層化社会」、「派遣OLはなぜセクハラを我慢するか」、「労組はあなたを守ってくれない」、「市場化する老人と子供」、「不平等を正当化する人々」、「優生学の復権と機会不平等」と社会の各点からみている。
弱者ということを言うと、論旨がずれてくる可能性があるので、ここでは、既得の財産のない誰の身にも起こる
かも知れないこととしておく。
ゆとり教育という欺瞞については、読んでいてこわいほどのことが書いている。ゆとり教育によって、確実に全体の学習能力は低下する。でもこれでよいのだとゆとり教育を推進する委員会は別のところでは述べている。ようはいままでの戦後社会は、中途半端にデキル子供を作りすぎていた。だからキレて犯罪に走るような奴がでてくる。だからそんなこどもをつくるよりは、
勉強を教えないで奉仕活動を叩きこんで、ロボットのように権力に反抗せず働く人材をつくればいい。指導者はエリート教育を受け一般のこどもはそれを邪魔するな。ということだ。
これがうまくいかないことは、アメリカが70年代にゆとり教育をはじめてから、学習能力が落ち、近年共通試験などを導入したり、予算をかけて学習能力をあげようとしていることを見てもわかる。同じ道を30年遅れで選ぼうとしているのだ。ゆとり教育という口当たりの良い言葉にはこのような意味が隠されているのだ。同様なことが大人社会でも起こっている。
多くの政治家や財界人の描く社会は、一部のエリート層が社会的、会社での決定権を握り、かれらは一種のテクノクラートであるので当然高収入を得る。その下に流動的な人材が存在する。かれらは
エリートの決定に従い、産業構造の変化によって、雇用を調整される労働力となるのだ。
そのような、強者適合の社会的淘汰(ダーウィニズム)がグローバリゼーションの御旗のもとでおこなわれる。
その旗を振る学者たちにあるエリート意識を作者は問題にする。竹中平蔵、中谷巌、中条潮、かれら慶応閥欧米留学組に果たして社会全体のための経済政策を立てられるのか。その感覚はエリートのそれではないだろうか。現に竹中は大臣発言として、「不良債権処理で一時的に数十万人の失業者がでるが、痛みは我慢して欲しい」と公言しているが、その口調は楽観的であり、
社会的セーフティ・ネットの構築にはあまり熱心ではないようだ。社会のしわよせがどこにくるかについて、その痛みの程度について無頓着なきらいさえする。
どう転がっても、アメリカ型の貧富の差がものすごくあり、どうあがいてもそれは縮まらない世界はどんどん近づいている。そのための用意として本書を読んでいただきたい。特に教育を骨抜きにしようとするゆとり教育についてはお勧めである。
結局のところ限りなく「階級社会」に近い、「階層社会」が生まれることになるだろう。金銭財産や社会的地位の既得の者はもっと富み、そうでないものは努力とは別に機会さえも失われていく社会に近づくのだろう。
さいごにせっかくの良い本であるが、非常に読みづらい。雑誌に書いたものを再構成しながらまとめられたものであるので、文章の統一性や、地と会話の文体の違いなどがとてもわかりづらい。これは編集者の責任だと思う。読みやすく段落とか指摘するべきだろう。それによってもっと多くの人に簡単に読んでもらえると思う。
精神の瓦礫ニッポン・バブルの爪痕 斎藤貴男:岩波書店:1900円
 ノンフィクションライターの吉田司はバブルを「第二の敗戦」と定義した。本書もそれを様々な視点から
「なぜバブルがはじまり、人が踊り、はじけたか」を例証し、なにが起こりなにが失われたかを追っている。
ノンフィクションライターの吉田司はバブルを「第二の敗戦」と定義した。本書もそれを様々な視点から
「なぜバブルがはじまり、人が踊り、はじけたか」を例証し、なにが起こりなにが失われたかを追っている。
ここで見えてくるのは、地上げに踊った神田の街。
携帯電話の普及が産業界の押しにより、法整備を拒み、事故を誘発している構造。(カナダでの実験によると、 運転しながらの携帯電話での会話は注意力を散漫にして、それは交通違反摘発許容内ぎりぎりのアルコール摂取して運転している状態に匹敵する
と言う。)
長野オリンピックという分かりきった土建構造にあえぐ状況とそこから脱しようとする人の暗闘。
新潟県湯沢町のワンルームマンションで疲弊した、まちづくり。それを活性化しようとした学者と旧弊の町長のぶつかり合い。固定資産税を滞納した投資用ワンルームマンションの持ち主が、都営住宅に住む矛盾。
知らぬ間に公共事業の担保として使われた政府保有のNTT株。それが何度もまだ使える担保として国会論争を呼ぶ不思議さ、
NTT株神話ともいえよう。
小笠原空港計画の行方。
つぶれたのに社員を海外留学に出す懲りない長銀の体質。一流の腕を持っているがゆえに疎んじられるレストランシェフ、ファミリーレストランの進出に職人料理人は不要となる。独立開業するも、回転資金と客がついてこない現実。
同様にいいつのまにかしぼんだメセナ。
国民におこづかいを与えた地域新興券の愚挙。二世がどこにもはびこり、その特権を否定しない世界。
ここに描かれた世界はわたしたちにはあまりにも身近だ。よくもまあと思うくらい、じゃぶじゃぶのお金づけ状態。誰にも止められなかったのだろうか。端的にいえば、ここであきらかになったことは、1945年の敗戦からここまで、築き上げてきたものがチャラになったということ。戦後の神話がことごとく粉砕され、あれは間違っていたんだといわれるようになった。右上がりの成長と地価上昇神話。よって株もゼネコン、銀行も不滅ということ。
ふたを開けてみれば、この時代に実力が見合った指導者、政策者がいなかったこと。一億総バクチに走ったこと。
結局は戦前から資産を持っている二世層の勝ちという、身も蓋もないオチ。 もはや彼等にしか利さない世の中にしかならんことを事実として知っておく必要はあるだろう。
わたしたちはなぜ科学にだまされるのか ロバート・L・パーク:主婦の友社:1900円
 原題を「VOODOO SCIENCE」という。なんと魅力的なタイトルではないか。いわゆるインチキ科学を斬る書なのだが、単純に笑うあげつらうのではなく非常に啓蒙的である。
中学生や高校生にぜひ読んでほしい。
原題を「VOODOO SCIENCE」という。なんと魅力的なタイトルではないか。いわゆるインチキ科学を斬る書なのだが、単純に笑うあげつらうのではなく非常に啓蒙的である。
中学生や高校生にぜひ読んでほしい。
有人宇宙開発はやめるべきだという部分は刺激的だ。ガガーリン、アポロ、スペースシャトルと続く一連の開発は、政治的なデモンストレーション以外にはなんの価値もないと断言する。無人衛星の性能があがっているいま、火星や木星へ飛ばして成果をあげているのに、なにも危険とカネをかけて人間を乗せることはないという。あえて人間でないとできないことはなにもないというのだ!うーん単純明快すぎます。
よく信じられている「高圧電線の下に住む人には白血病が多い」というのも、偏見にみちたジャーナリストと統計の誤った使い方から出てきた結果だということを指摘する。これも追調査で真実が証明された。また
サプリメントや磁気治療についての気休めも科学的に解明してくれる。
いまや暴露された「スターウォーズ計画」のでたらめさと提唱した科学者のダメさや、常温核融合騒ぎの問題点(日本の通産省やトヨタはあとあとまでこの学会に資金を出していた)を科学者の視点、科学者の科学に対する誠実さから語っている。
そう、ここで語られているのは、科学とはなにかなのである。それは難しい方程式でもインチキなことでもない。それをもう一度知ることは重要なことだろう。信
じられないような発見は起こりようもないというのが結論である。でもひょっとしたら、ということはわたしたちは思ってしまう。作者は科学の考え方をこう述べている。
新しい科学上の発見だと思ったとき、1.それが実験により再現でき検証できるか 2.それによって万物の予測がたつようになるか このどちらかのこたえがノーであったらそれは科学ではないという。
それを厳密にするための科学者のルールとして、1.すべてを公開してほかの科学者に自由に実験を再現してもらう 2.自説より完璧、あるいは信頼できるものがあれば、それに自説を放棄しそれに従う
これらの点は非常にわかりやすく重要であるし、すぐに使える。たとえば、テレビでやっている心霊写真者や奇跡のなんたらとか、ニュースショーのアンケート調査やコメントなど、上記の考えに従っていないものは自然科学であれ、社会科学であれ、それは番組やニュースではなく、ただのエンターテインメントだということがわかるだろう。
そのことは第2章「信じたがる脳 科学こそ真実を選び出す戦略」にまとめられてある。学生に科学的な考えの必要性を知ってもらうには、この章を科学の授業の第1回に読むのが一番良いだろう。格好のテキストであることは保証する。
作者は物理学の教授でアメリカ物理学会のワシントン事務所長。いまも毎週
メールマガジン
を発行しているので一読あれ。
だれが本を殺すのか 佐野眞一:プレジデント社:1800円
 かれのノンフィクションは、人物インタビューにより切り取って行く手法と資料の読みこみが、事象の新しい側面を浮き上がらせて行く。
でもこの本はわたし的には?。映画興行についての本も?だったけどね。
かれのノンフィクションは、人物インタビューにより切り取って行く手法と資料の読みこみが、事象の新しい側面を浮き上がらせて行く。
でもこの本はわたし的には?。映画興行についての本も?だったけどね。
大前提としてのかれのスタンスに疑問を呈する。作家として拠って立つのか、読者として立つのか、はっきりしない。
たぶん業界的には、対外側に向かっては衝撃的なのだろうけど、内側にいる業界人同士ではたいした話ではないと思う。ようするに、官僚の世界と同じことなのね。
業界が古い商慣例でなりたっていることが問題なのだろう。まあ他の業界も多かれ少なかれ同じとは思うのだけど。版元と販売のあいだに、取次が存在する世界ではどこも変わらないとおもうのだけどね。いわゆる野口悠紀夫のいう「1940年体制」によって統制された経済構造が戦後の解体によっても残っている状態。この場合だと取次大手の日版とトーハンが独占状態として戦中戦後と君臨していること。そしてこの
取次の株を保有しているのが、大手出版社という状態が新陳代謝ができない一因になっている。またもうひとつの遠因「55年体制」による労使協調体制が拍車をかけている。これにより、出版の現場は
「文化」と「営業」に分かれ、それぞれに飼われながら互いに持たれる形となる。売れる本はワルイ本。売れない本はヨイ本というねじれたテーゼが行き交う。
ある種学問、文化と呼ばれる世界はこれによって成り立つようになる。これはサブカルチャーの現実に、簡単に押し流されちゃうんだけどね。
作者の佐野もこの流れの恩恵にいる人なんでそこら辺の自覚ツッコミがない。だからマンガの現状についてもなにも書かれていない
し、角川春樹がはじめたメディアミックスについての言及もない。だからこの本の正確なタイトルは「だれがヨイ本を殺すのか」である。おめえの本のとなりに、携帯着メロや、タレント本が並んでいてなにが問題なんだよ。
そこら辺は作者が前書きで、いみじくも大学出て最初に作った「原色怪獣怪人大百科」をいやいや酒飲みながら編集して、一緒に仕事をした怪獣博士くんに、「子どもたちはなけなしの小遣いを持って買いに来るのですよ」と怒られた挿話に象徴されるだろう。
総花的には、いろんな情報があっておもしろいのだが、委託販売制度や再販制度などに原因を求めている部分があるが、多少出版に携わっていたものとしては、肝心な点が抜けていると考える
。「なぜ返品可能な委託販売なのか?」という点だ。そこら辺は在庫をどう考えるともリンクしていると思う。実際在庫がどこにあるのかわからなく、返品率40%で裁断される書物に文句をいうことは一理はある。が、在庫は業界のアキレス腱でもある。トヨタがジャスト・イン・システムといういわゆるカンバン方式で業績をあげたことは承知のこととは思うけど、これはなにかというと、流通過程な複雑な業界で
会社が過剰在庫を抱えない姑息な手段といえる。アメリカのパソコン業界がこれをいまパクっているのはお分かりでしょう。同じく複雑な流通の本も、どの過程でも在庫を抱えず、まわしていることで、帳簿上の売上(利益じゃないよ)が出て、実際にお金が入ってくるまでは時間がかかるが、当座の運転資金は出る(銀行が貸してくれるということ、または手形が割れること)。だから印刷所が支払いを待ってくれなかったり、取次からの入金が送れると、小出版社は大変なことになる。このあたりは編集者、安原顕の雑誌、書評誌「リテール」が売れたのに廃刊したいきさつが参考になる。
また在庫を抱えないということは、実は売上ではなく、在庫の量に対して税金がかかるという現実が一因だろう。そこで出版数の調整を含む在庫処分のネックになる。売れようが売れまいが、在庫があると税金がかかるのだ。だからロングセラーより裁断したようが良いこともあるということ。逆にいえば、規模の小さい企業の集合体である出版業界の苦肉の互助システムなのかも知れない。
そのあたりの数字のマジックについて書いてないから人口に膾炙するのだろう。
カルトの子 心を盗まれた家族 米本和弘:文藝春秋:1571円
 カルトとは、組織や個人がある教えを絶対であると教え込み、それを実践される過程で、人権侵害あるいは破壊行為を引き起こす集団である。
カルトとは、組織や個人がある教えを絶対であると教え込み、それを実践される過程で、人権侵害あるいは破壊行為を引き起こす集団である。
これは作者が定義した「カルト」だ。統一教会、エホバの証人、オウム真理教、ヤマギシ、ライフ・スペースなど個人だけではなく一家総出で入信することを求められる集団では、
子供には選ぶ権利も無く、はじめから神の子どもとして生きることを命じられる。他の生きかたが分からない子どもは成長しても愛情の偏った大人になることが多く、そのキズは絶えないことが多い。
作者は取材の過程で、宗教から抜け出した親が、宗教が子どもに与えた影響を考えていないことに驚く。入信して親子が別れさせられて、親に捨てられたと感じる子どもが多いのに、その反対はないのだ。
子どもは親を連れ去った宗教を憎むが、親に捨てられないために宗教を肯定する素振りをみせる。このアンビバレンツな感情が人物形成に影響すると見られる。
そのような研究も日本では行われていないことを作者は嘆き、オウム事件のときの報告書が作られなかったことの手抜かりを指弾する。
巻末にヤマギシが学校法人を申請しようとしたとき、三重県がヤマギシの子どもにアンケート調査をした資料を独自に入手して公開している。
洗脳の楽園 ヤマギシ会という悲劇 米本和広:洋泉社:2200円
地位を捨て全財産を寄付して、家族で入村する。どこかで聞いた話じゃないですか。オウムが活動を中止したいまもこんなことをしている集団があるというのに驚く。その秘密が
「特講」と呼ばれる七泊八日のセミナーにあるという。これは門外不出の潜入記録であり、ヤマギシ会の全貌を捉えようとしたものである。
「特講」の様子を読むと、自己開発セミナーに酷似していることに気づく。自己開発セミナーについては、鶴見済の「人格改造マニュアル」に詳しいが、いわば
これは洗脳である。無防備な人に「なにかが変わるから」と言って受けさせるのはほとんど犯罪と言っても良いだろう。なんの基礎知識がなければ、どんな人間でもオチルと思う。
「特講」後の作者の状態を、精神家医の斎藤環は、「特講を受けた人は解離状態になっている」と分析する。解離状態とは、精神医学上「人間の精神の統合が失われる状態」と定義されている。さらにいうと「たとえていえば、
解離とは体験を構成している諸感覚の入力のスイッチが切り替わってしまうことである。その変化の仕方は多くの場合は非常に素早く、そのきっかけは本人も気がつかないことが多い。ともかくある時点から自分の感じ方、知覚、感情などの体験のされ方が変わってしまったりする」
「特講」では、「なぜあなたは腹が立つのか?」という答えのない質問に延々と「では、なぜあなたはそう思うのか?」と問い詰められ、
精神的に防御反応が働き、諸感覚の入力スイッチが切り替わって、感じ方が変わる状態になる。まったく洗脳じゃないか。
ところで、社会でも同じようなことってない?いつのまにか会社の人間がみんな同じような考え持っているなんて、それに近いよね。ひとりだけそれは違うと言っていても、どつかれているうちに苦しむよりは、同じようにすることで楽になるという逆転。体育会的でもあるわな。
ともあれ、この体験、ようするに相手の意見を無条件に受け入れやすくなっている状態に、新しい価値観を植え付けるのはたやすい。ここで地上の楽園のように喧伝されるヤマギシの考え方を刷り込めば、目的は達せられる。恐ろしいことに、その後も地方の研鑽会という会に出れば、継続してその効果はなくなることはない。
この「特講」は、すでに朝鮮戦争より先にあったらしい。考えてみれば禅問答なんてこれと同じだよな。答えの無い問いに答えること。わかったということは、自分が間違っていて、自分の考え方が変わったと言うところなど。
これは意思が強く疑っていたら大丈夫とかいう問題ではないから注意。自分でもわかっていない潜在意識や生理学の部分に直接射ち込まれる注射のようなものだから、人間であれば誰にでも効くはずだ
終末と救済の幻想 オウム真理教とはなにか ロバート・J・リフトン:岩波書店:3200円

Aum Shinrikyo,Apocalyptic Violence, and the gloval Terrorism
作者は朝鮮戦争で行なわれた洗脳のメカニズムを公表した心理学者であり、ホロコースト時のナチの心理状態などを調査している人物である。
基本的なスタンスは心理学のものであって、そこから逸脱しないでオウムとはなにかに迫っている。麻原の生い立ちから、ひとの上に立ち掌握したがる癖、などを指摘し、最初の殺人後、次第に精神的に病み、
サリン事件以降は、ほとんど妄想的心理状態に陥っただろうことを述べる。とともにオウムは麻原だけの妄想ではなく、グルに応えようとした弟子の存在
の大きさに注目する。かれらが相互依存により補完し合って宗教として成立し、やがてオウムが暴走していったことを、その心理状態から解いて行く。
日本で問題とされた、神秘体験やサブカルとの接点も、ニューエイジの変形と簡単に切り捨てる。オウムに高学歴という問題も、ほとんどが高学歴でないと指摘する。
こういったたいしてセンセーショナルでもないけど、日本人による、きちんと書かれている本が、なんで出ないのかというのが最大の謎なんですけどね。
国際誘拐ビジネス 語られなかった真実 アン・ヘッジドーン・オーバック:DHC:1900円
 いまも世界中で、誘拐されている人間は数万人いるというショッキングな情報からこの本ははじまる。
いまも世界中で、誘拐されている人間は数万人いるというショッキングな情報からこの本ははじまる。
1990年代に「誘拐」は、主義主張の大義からビジネスへと変容した。コロンビア等中南米では、
GDPの数%を占めるという。 たとえば、誘拐犯とよく交渉する日本は、メキシコでのサンヨー日本法人副社長誘拐の解放に使われた身代金が、翌年の武装蜂起に使われるという明確に武器調達資金に変わることが確認されている。世界的には麻薬と並ぶ手っ取り早いビジネスと化しているのが現状だ。
もはや、外務省等の公的機関のみでは、現地危険情報の提供はもとより、誘拐された時に現地国との板ばさみとなり、独自交渉もできないのだ。これはアメリカといっても同じだ。そこで、民間会社の登場となる。ディック・フランシスの「誘拐」のモデルとなった、CRG(リスク・コントロール・グループ)などいくつもの会社がそれぞれロイズなどの保険会社およびそのクライアントの会社の代表として独自に交渉をする。そこには、身代金支払いも含め、あらゆる手段を視野に入れている。
身代金を値切らないのは、誘拐犯に「この相手汲み易し」という信号を出しているのと同じことを表わし、第二の事件の誘因となるという。他国でのぎりぎりの交渉が誘拐交渉人の腕となる。値切らないのは、相場の高騰にもつながる。この情報は世界中に素早く広がる。
日本人がターゲットにされるのはすぐに支払うことに原因があるらしい。
誘拐交渉人に話を戻すと、ペルー日本大使館占拠事件で、早々と欧米の人間が解放された背景には、民間会社の誘拐交渉人による独自の交渉があったという。その点では日本政府の橋本ポマード総理の「あんぱん配達」が、いかにノー天気かがわかるだろう。
作者は他国を旅行する者へ、旅行会社のいい加減なあおり広告に注意することを呼びかかる。カンボジアのアンコールワットは確かに観光できるようになったけど、ポルポト派の残党の餌食になりかねない。中米のコスタリカにエコ・ツアーにやってくるドイツ人は、隣国のグアテマラのゲリラの越境がいかにたやすいかを学ぶ必要がある。
本書は、インド・パンジャブ州で起こっている誘拐事件を縦軸に、世界中の事例を拾い上げている。あまり緊迫感がある交渉場面は出てこない。それは別書に任せるべきで、概観を得るには好書だといえる。
M/世界の、憂鬱な先端 吉岡忍:文藝春秋:2000円
 昭和が終わり、平成というどこまでもなだらかだが、確実にかたむいいて行く時代を迎え、その年の夏、永遠の29歳が逮捕された。
昭和が終わり、平成というどこまでもなだらかだが、確実にかたむいいて行く時代を迎え、その年の夏、永遠の29歳が逮捕された。
宮崎勤について、書かれたものを読むと、概して違和感を覚えるのは、彼のいた位置に距離的にも、年齢的にも、精神的にも近いせいなのだろうか。そのためなのか、著作者のポジションを明確にしないと、彼の事件は見えてこないと確信している。多くのものが何の役にも立たない中で
この本は、ましな部類に入る。
この事件で問われているのは、わたしたちすべてであって、それを誰も高台の絶対安全地帯から裁くことはできない。その立場に立った途端に、「言葉」がこぼれていくからだ。ここで作者が問題にしているのは、裁判官、精神判定、ジャーナリズムである。宮崎勤に関する本で、三本のそれぞれ正反対の結論の出た、精神鑑定書について、詳しく論じたものは無かった。ここで吉岡は、
自らのジャーナリストの取材の手法から精神鑑定のやり方の杜撰さを指摘する。ここで警察の事情聴取とも違うはずの任意の発言を求めるはずの精神鑑定は、自らの役割を放棄してしまう。ようするに、自分の見たい姿しか求めない先例を旨とする学問の限界を露呈しているのだ。唯一マシな多重人格論以外は、世論と裁判所の無言の圧力に負け、彼に既存のレッテルを貼り付けたに過ぎなかった。結果として何も聞き取ることが出来ない調書に解釈を下すという「群盲象を撫でる」をやっているのだ。ジャーナリズムでは絶対許されない、事実についての推定をしているのだ。この指摘は非常に的確である。吉岡は少ない3つの異なる鑑定書をバラして、もう一度宮崎像を捉えなおしている。しかし、どこか限界がある。
また、吉岡自身の資質として、どうしても世代的な隔たり、彼自身の方法論の限界というのも見えてくる。宮崎の実像に迫ろうとしながら、どこかわからないことがあると、精神分析の歴史の講釈や、世界情勢から見た経験的、あるいは世間では学問としては、こう解釈していると大上段に振りかぶるので、どこか外している。これが団塊の世代くらいの方法論の限界なんだけど。
どこか大きいところから見ないと気が済まないところが本質を見えにくくしている。
宮崎の言う「流行っているから」集める。その無意味とも思える収集への執念をどう捉えたらよいのか戸惑っている。そのヲタクどう思うのか(吉岡はほとんどこの都合の良い言葉を使わない)、それについては、答えを出していない。ただ、巻末にある、神戸の事件のあと、行われた学園祭における生徒と教師のものがたりや、酒鬼薔薇の父の出身をめぐる南の島のものがたりなど、ここに集約していきたいという著者の想いはわかる。でも、わたしたちにはそれじゃ足りないんだ。
肉体的なものに集約して解決するのでは。
著者は、同世代の人間が大塚英司いがいは逃げたと糾弾している。確かにそうだ。大塚は「宮崎を擁護する気持ちはない。ただ、ヲタクにもいいヲタクと悪いヲタクがいるみたいな論議で切り抜けようとするのは間違っている。わたしは、才能がなく、それでもヲタクとしてしか生きていけない、圧倒的多数のひとのために発言する」と言っている。確かに、「俺は宮崎よりビデオを持っている」とか、「そのエネルギーを別のものに使え」とかの声もあるがそんなものは無意味である。何で無意味かというと最初に書いたように、
そこから「言葉」がこぼれるからである。賢明かどうかわからないけど、その「言葉」を発しないものたちはオウム的なものへと流れて行ったことは確かだ。そして、すべてはショー(見世物)になった。ここから先は吉岡には書けないだろう。まだナイーブに何かに絶対的な価値を求めるジャーナリストでは。
カリフォルニア・オデッセイ1
LAハードボイルド 海野弘:グリーンアロー出版社:2381円
 かつて、東京論が流行ったころ、いくつもの書物が出版され、わたしも嫌いじゃない分野なので読み漁ったけど、いまも残っているひとは、別の研究フィールドを確固として持っていたひとだけだな、と改めて思う。その中で海野弘は、ふらふらとさまよい続けている感がある。1920年代のアール・ヌーヴォ、ワイマール時代、ニューヨークなどなど色々発掘はしてくるのだけど、
目端の利く連中にパクラレルコト数限りなし。そのひとつには、文章が平易すぎて(これは誉め言葉だよ)、誰でもアクセスできるネタを使い、突っ込みが足りない。文章の魅力に欠けるってことだろうか。
かつて、東京論が流行ったころ、いくつもの書物が出版され、わたしも嫌いじゃない分野なので読み漁ったけど、いまも残っているひとは、別の研究フィールドを確固として持っていたひとだけだな、と改めて思う。その中で海野弘は、ふらふらとさまよい続けている感がある。1920年代のアール・ヌーヴォ、ワイマール時代、ニューヨークなどなど色々発掘はしてくるのだけど、
目端の利く連中にパクラレルコト数限りなし。そのひとつには、文章が平易すぎて(これは誉め言葉だよ)、誰でもアクセスできるネタを使い、突っ込みが足りない。文章の魅力に欠けるってことだろうか。
その著者がようやく鉱脈を掘り当てた。カリフォルニア=ロサンゼルスである。なんでいまさらと驚かれる方は(わたしもだけど)、読んでもっと驚かれるがよい。ここには見たことの無いLAがあるのだから。
第1作目の本書はそのプロローグにすぎない。まだ著者も手探り状態なので、こなれてないところがあるが、3作目になると非常にスリリングに論が展開されて行く。それは、追って書くので、この第1作について絞って行きたい。
LAは実はものすごく古い歴史があるのだけど、ここでは、ハード・ボイルドに絞っているので、チャンドラー、マクドナルド、エルロイと30、40、50年代と照らし合わせている。それぞれを石油の時代、ハイウエイの時代、腐敗の時代として文章を引用しているのだけど、微妙にずれているところもあって、「?」となるところもあるが、切り口がおもしろい。たとえば、マクドナルドの「死のプール」と50年代邸宅にプールを作ることが流行るところの考察など感心する。ネタ本としての
「レイモンド・チャンドラーのロサンゼルス」という、たぶんモデルの地はここだろうと、当時の写真を集めた写真集があるのだけど、これはぜひ手に入れたい。『ブレード・ランナー』のネタ元でもあるらしい。
また、エルロイの章では、市警察の腐敗が現実の事件の部分が語られるので、いかにモデル小説としてエルロイが書いているか、読み返すのもおもしろい。
まだ、手探りの段階なので、映画『チャイナタウン』や『ブレード・ランナー』は、あまり触れられていない。それぞれ、70年代、80年代と呼応すると思うのだけど。
その他にも、黒人暴動として有名なワッツ地区の歴史的変遷や、ヴェニス地区(オーソン・ウエルズの『黒い罠』やデニス・ホッパーの『カラーズ』のロケ地)が本当にヴェニスを目指したので運河があったことなどへーっと思う。
この十年はロスが流行るからこのシリーズで予習しておくように。
カリフォルニア・オデッセイ2
ハリウッド幻影工場 海野弘:グリーンアロー社:2381円
 シリーズ第二作では、ハリウッドを取り上げている。ここにあるハリウッドは、どちらかというと、ケネス・アンガーの「ハリウッド・バビロン」に近い。ただ、ゴッシップというよりは、アウトサイダーの視点に重きを置いたため、いくつかのハリウッドを描いた小説「ラスト・タイクーン」、「いなごの日」などからの引用があり、いまひとつ面白みに欠ける。ネタとしてもギャングとハリウッド、赤狩りなどいまひとつ新鮮味がすくないが、いままで知らなかったネタは少しはあると思う。
シリーズ第二作では、ハリウッドを取り上げている。ここにあるハリウッドは、どちらかというと、ケネス・アンガーの「ハリウッド・バビロン」に近い。ただ、ゴッシップというよりは、アウトサイダーの視点に重きを置いたため、いくつかのハリウッドを描いた小説「ラスト・タイクーン」、「いなごの日」などからの引用があり、いまひとつ面白みに欠ける。ネタとしてもギャングとハリウッド、赤狩りなどいまひとつ新鮮味がすくないが、いままで知らなかったネタは少しはあると思う。
翻訳されていない本の紹介が拾い物です。ジョン・ヒューストンの失敗作『勇者の赤いバッジ』のメイキングのリリアン・ロス著
「picture」、『タクシードライバー』、『未知との遭遇』のプロデューサー、ジュリア・フィリップの70年代のスピルバーグやスコセッシを描いた
、デ・パルマの失敗作、『虚栄の篝火』のメイキング 「the Devils Candy The Bonefire of Vanities
Goes to Hollywood」
またいまも主流のコンセプトだけのプロデュース手法が、80年代「ハイコンセプト」といって、企画だけで金を集めて作品を作るやりかたが、『アメリカン・ジゴロ』から始まった(プロデューサーは『アルマゲドン』のブラッカイマー)といのは初耳。その後『トップ・ガン』に続くといえば、わかりやすいか。
あと、編集部の校正が甘いのか、邦訳されている本が、原書扱いだったり、記述にいくつか間違いがある。映画だからわかったのだけど、他の書は大丈夫なのか心配である。
カリフォルニア・オデッセイ4
癒しとカルトの大地 神秘のカリフォルニア 海野弘:グリーンアロー社:2381円
 第3作目に来てようやく、本シリーズが見えてきた。著者はたぶんこれがやりたかったのだと思う。非常にノッテイルのがわかる。スポーツ用品の始祖スポルディング氏の晩年、カルフォルニアの神秘宗教家に入れ揚げる様子から本書は始まる。
カルフォルニアは神秘主義と相性が良いことが語られる。ヨーロッパで受け入れられない教えが、流れ流れてここにたどり着くのだと。また、インディアンをはじめとして、
様々な聖地であることも指摘される。その流れと、温泉(保養所とSPA)があり、癒しを求める人々が集う場所としても有名であることが開かされる。
第3作目に来てようやく、本シリーズが見えてきた。著者はたぶんこれがやりたかったのだと思う。非常にノッテイルのがわかる。スポーツ用品の始祖スポルディング氏の晩年、カルフォルニアの神秘宗教家に入れ揚げる様子から本書は始まる。
カルフォルニアは神秘主義と相性が良いことが語られる。ヨーロッパで受け入れられない教えが、流れ流れてここにたどり着くのだと。また、インディアンをはじめとして、
様々な聖地であることも指摘される。その流れと、温泉(保養所とSPA)があり、癒しを求める人々が集う場所としても有名であることが開かされる。
それらの集大成として、60年代のヒッピー 70年代のニューエイジが花開く土壌として説明される。
日本はこれの10年遅れだよね。この流れがわかると、60年代のマリファナとヒッピーの時代の終わりに、チャールズ・マンソン事件が起こり、70年代にティモシー・リアリーとLSDが花開くことがわかる。そして、80年代のコカイン汚染とAIDSの時代が来る。
ここで貴重な証言として、「ハリウッド・バビロン」の著者であり、映画監督のケネス・アンガーの『ルシファー・ライジング』に多くのハリウッドの黒魔術師が参加していることがあげられる。ハリウッドと魔術の暗いつながりが感じられる。そして黒魔術師の弟子として、究極のカルトのサイエントロジーの創始者、ロン・ハバートが現れる。
そして、東洋からも、チベット仏教や禅が浸透し、アレンキンズバーグら60年代に終わったと思われた、ビート派詩人を再生させる役割を果たす。
はっきりいってこれ一冊で、「エスクワイア」や「スイッチ」(池澤夏樹かなぁ)は特集が組めるし、「不思議発見!」の一本は作れるだろう。旅行ツアーもできるな。でも著者に敬意を払って簡単にパクッちゃだめよ。
左腕の誇り 江夏豊自伝 江夏豊 波多野勝構成:草思社:1500円
 昨今のスポーツジャーナリズムのつまらなさは、記事および取材の底の浅さに、選手が飽きるとともに、提灯記事を書きながら選手に近づき
独占的な取材をしていく癒着型ジャーナリズムの横溢にある。 だれとは書かないがあまりに多過ぎる。それでなければ、数字の羅列により、その選手を追いかける分析型だ。
昨今のスポーツジャーナリズムのつまらなさは、記事および取材の底の浅さに、選手が飽きるとともに、提灯記事を書きながら選手に近づき
独占的な取材をしていく癒着型ジャーナリズムの横溢にある。 だれとは書かないがあまりに多過ぎる。それでなければ、数字の羅列により、その選手を追いかける分析型だ。
本書は、インタビューをしているが、なにひとつ江夏豊の言葉を引き出していない。どこからも江夏のすごさが感じ取れないのだ。人間ドキュメントとしても失敗しているし、浅い。多角的な取材をしているわけでもなく、なにを描きたかったのかわからない。大学の先生の仕事だからこんなものなのだろうか。ほんとうにこの本を書きたかったのならすくなくとも、覚せい剤事件のあと、もう一度江夏に取材を申し込むべきではないか。それを逃げて客観的に書いていることでこの本は致命的なまでに価値を失っている。
マードック 世界のメディアを支配する男 ウィリアム・ジョークロス:文藝春秋:2667円
 タブロイド紙のように、スキャンダラスで、卑俗な謎のメディア王の姿が描かれてる。さすが、マードック非公認伝記だ。
80年代なにが世界のマスメディアで起こっていたかを知るには格好の一冊だ。 あとCNN世界を変えたニュースネットワークを読めば良い。
タブロイド紙のように、スキャンダラスで、卑俗な謎のメディア王の姿が描かれてる。さすが、マードック非公認伝記だ。
80年代なにが世界のマスメディアで起こっていたかを知るには格好の一冊だ。 あとCNN世界を変えたニュースネットワークを読めば良い。
オーストラリアのアデレードという田舎町に生まれた男は、父の経営する新聞がその理想ゆえに没落し、ライバルに買い取られるのを目にする。イギリスに留学するもその階級意識を徹底的に意識させられる。金をかき集めては新聞社を買収して行く、その手口はいつも同じで、その土地に詳しい弱小新聞社を見つけては、ライバルを徹底的に叩き、弱まったところですかさず交渉。ダメならさっさと引き上げる。かつてのテレビ朝日株取得事件のときも孫正義と組んだことも、官僚制度がきついとわかると、CS放送も売ってしまうなど、典型的なマードック商法だ。
話を戻すと、オーストラリアで力をつけた彼は、イギリスに進出する。まずは弱小タブロイド紙から始める。 マードックの新聞は、テレビでも同じだが、いわゆる扇情的タブロイド新聞で、イギリスなら労働者層が買う新聞「SUN」などが代表だけど、いわゆる皇室スキャンダル、ダイアナバッシング、日本の天皇バッシング、新聞にヌードをはじめて掲載したのも彼である。
やがてひとつが軌道に乗ると、一流紙も買収にかかる。新聞印刷工組合(かれらが版を組み新聞を印刷する)を敵に回し、編集部にコンピュータを導入して、彼らを排除する手口は、レーガン=サッチャーの保守の時代の背景もあり、新しい印刷工場を警察に守らせながら新聞を発行するというとんでもないやりかたで勝負をつける。
最後の砦、アメリカでの一番大きな仕事は、20世紀フォックス社の買収と、FOXテレビネットワークを作り上げたことだろう。ここで、作者は80年代の巨大メディアの誕生についておもしろい見解をみせる。映画『ウオール街』のモデルとなった、仲買人マイケル・ミルケンのジャンク債とよばれる怪しい債権の大量調達による、資金の流入が買収ゲームを可能にしたというのだ。ターナーのCNNの急成長も同じような恩恵のためと指摘する。
そのようにして、アメリカで成功するためには、外国人のメディア保有をいう障害も、アメリカ市民籍を取ることであっさり解決されてしまう。FOXテレビが3大ネットワークに追いつくには時間はかからなかった。大衆の望むもの、スポーツ、バイオレンス、スキャンダル、とFOXの番組をみればその過激さは一目瞭然だ。
次の標的は、中国らしいが、衛星放送が日本以外でようやくうまくいき出したマードック、彼の錬金術はいまのメディアを変えたことは確かである。でもそれが良い方にじゃないことも確かである。
黄沙の楽土 石原莞爾と日本人が見た夢 佐高信:朝日新聞社:1600円
良日本主義の政治家 いま、なぜ石橋湛山か
佐高信:東洋経済新社:1400円
 著者は、これらを対として構想していたという。佐高は石原莞爾と同郷、山形の出身である。いまも語られる「石原莞爾伝説」に、日本人の勝手な歴史観を見ていらだつ。伝説曰く「石原さん東条英機にはめられ失脚した。石原の掲げた五族協和の理想や日米が戦う世界最終戦争の予言は外れていなかった」ゆえに石原は従来の日本人のスケールを越えた人物だったと。
著者は、これらを対として構想していたという。佐高は石原莞爾と同郷、山形の出身である。いまも語られる「石原莞爾伝説」に、日本人の勝手な歴史観を見ていらだつ。伝説曰く「石原さん東条英機にはめられ失脚した。石原の掲げた五族協和の理想や日米が戦う世界最終戦争の予言は外れていなかった」ゆえに石原は従来の日本人のスケールを越えた人物だったと。
しかし佐高は、それは日本人から見た考えであり、結果、盧溝橋事件を起こして日中戦争を引き起こしたのは石原と喝破する。軍隊という組織が
、国益をかってに考え直接行動するのは、一般庶民にとっては胸のすく思いだろが、軍事からしかみていない外交はいずれ破綻するものだ。
その意味で断罪していかないとおかしな話になってしまう。
石原が好き放題している時代にジャーナリストとして、不戦論を書きつづけた男がいた。石橋湛山である。彼は博学の経済ジャーナリストであったが、のちに国会議員に転進する。戦後は保守政治の抗争にまきこまれ、自由党と民主党の保守合同を画策したり、吉田茂おろしに一役買っている。しかし、総理大臣に選ばれるもすぐに病気で辞任してしまう。政治家としての功績はすくない。本書は、戦後の政治家活動に多くを割いているので、ジャーナリストの湛山の行ったことがあまり出てこない。しかしながら、「石橋湛山なもの」を再考することで、保守しかないいまの政治状況の閉塞に対して、自分の意見をもてるのではないだろうか。
ルーブルにピラミッドを作った男 マイケル・キャネル:三田出版:3200円
戦前の中国の良家に生まれ、建築を学びにアメリカに渡り、バウハウスの薫陶を受け、戦後はアメリカの巨大都市開発プロジェクトをいくつも手がけ、モダニズム建築の大家となる。仕上げはルーブル美術館の再生プロジェクトだ。この中国の大人(たいじん)を思わせる、柔和な笑みを絶やさずに、政治家から何百人の建築職人までを引っ張る男、建築家I・M・ペイ。
この魅力的な男をどうすれば理解できるだろうか。彼が唯一話ができるという日本の建築家をだすのがいいだろう。「丹下健三」。東京都庁を設計した男。一説には30年先まで世界中で彼の設計を待っている建物のリストがあるという。彼をもっと大きくするとペイになる。
アメリカの中西部の大都市デンバーは、戦後は古びた田舎町だったのを、十数年かけて巨大複合ビルを建てて、アメリカ有数の都市にしたのも彼だ。街にどでかいビルを作り人口を増やす手法、いまや世界中どこでもやっているやりかた、を成功させたのもペイだ。
かれの政治家を動かし権謀術数を駆使して設計を勝ち取る手腕。建築に注ぐ情熱は賛否両論あるだろうが、モダニズムの建築家としての存在は無視はできない。
問題は彼の作ったコンクリートとガラスの建造物が、ゴシック建築の教会のように何百年も持つかということだ。これは他のコンクリート打ちっぱなしのコンセプトだらけで使いにくい建物を設計する建築家たちにもいえることではあるけど。
なぜ人はニセ科学を信じるのか マイクル・シャーマー:早川書房:2500円
 ナチスドイツによるユダヤ人虐殺いわゆるホロコーストだけど、殺したユダヤ人の皮膚から石鹸を作ったという話は嘘だって知ってた?実は、
ユダヤ人絶滅の公式文書や、虐殺の証拠写真が一枚もないことを知っていましたか。ガス室と呼ばれるところからなにもその証拠が検出されていないことは?ほんとうにホロコーストはあったのか…。
ナチスドイツによるユダヤ人虐殺いわゆるホロコーストだけど、殺したユダヤ人の皮膚から石鹸を作ったという話は嘘だって知ってた?実は、
ユダヤ人絶滅の公式文書や、虐殺の証拠写真が一枚もないことを知っていましたか。ガス室と呼ばれるところからなにもその証拠が検出されていないことは?ほんとうにホロコーストはあったのか…。
ダーゥインの掲げた新化論。サルが進化したものが人間ということがありうるのか。ならば、その証拠の化石でも見せてみろ。進化論は誤った教育として教えられている…。
最初のは「ホロコースト否定論者」、月刊マルコポーロを廃刊に追い込んだ、あの記事の参考文献にも入っている1派の主張ね。次のは、「クリスチャン・サイエンス(創造科学)」という、神がこの世を創ったと言っている人たちね。
わたしたちの学んでた、科学および科学的思考法は、実のところは非常にもろいもので、上記の主張に対して、バカバカしいと思いつつもひょっとしてと考え出したら相手の思う壺で丸め込まれてしまう。
オカルトを含む、トンデモ発言に対抗するには、いかに自分の中に情報、知識、そして反証的な論法をいつも飼いならしているかどうかで、勝負はつく。まあ、無視するというのも選択肢のひとつだけど、この世の中、たとえば宗教の勧誘、自己開発セミナーなどいくつものわなが潜んでる。なまじの知識ではオウムの上祐みたいなかたちで言いくるめられてしまう可能性はいつでもある。
本書は、そんなあなたが罠に陥らないためのサバイバル・ブックとしての実用性は高いことを保証する。
ホロコーストについては、マルコポーロ事件までフォローしているし、クリスチャン・サイエンスとの論争については、数日間かけて論破する。その準備段階から、論争で相手のどこをどうつくかを詳しく分析している。小学校で進化論を教えるかについても、いまだアメリカでは裁判で係争中の州がいくつもあるしね。
ところで、わたしはUFOと幽霊は見たことあると自認しているんで、この二つに対しては、錯覚とは一言で片付けるわけにはいかないのですよ(実話)。
CIA洗脳実験室 ハービー・ワインスタイン:駿台社:1900円
 「洗脳」は、Brain washの直訳で、朝鮮戦争で中国の捕虜となったアメリカ兵が、共産思想を植え付けられて帰ってきたことから、一般的になったのだけど、この実験を
国家レベルで民間人を実験台にしていたという内容が本書だ。
「洗脳」は、Brain washの直訳で、朝鮮戦争で中国の捕虜となったアメリカ兵が、共産思想を植え付けられて帰ってきたことから、一般的になったのだけど、この実験を
国家レベルで民間人を実験台にしていたという内容が本書だ。
洗脳というとわかりやういけど、ここで行われていることは、大学の心理学概説には必ず出てくる実験の応用なのだ。いわゆるパターンおよびデ・パターンについての実験。被験者をベッドに横にして、目、耳、指先、など知覚できる器官を覆い放置すると、パターン認識が崩壊して、人の言うことを受け入れやすくなるという実験。この実験を考案した学者は、数日であまりの効果におそろしくなってやめたが、それを何年も断続的に続けた科学者がいた。
カナダの認知心理学の権威である彼は、軽いうつの患者を無理矢理、被検者にして感覚遮断=洗脳の実験をした。その結果、何人もの人間が廃人となり、家族が崩壊した。作者もその一人である。彼は父の崩壊する様子をなすすべも無く、治るようにとマッド・サイエンティストのもとへ父を通わせていたのだ。
この不条理な状況がカナダ精神医学界の重鎮がおこない、アメリカの情報機関CIAが資金援助していた事実。しかも、効果はあげられずプロジェクトは終了し、科学者も裁かれることなくこの世を去った。
まあ、話を敷衍すると、この感覚遮断=洗脳の方法っていまや、自己開発セミナーとか、宗教儀式に緩用されているんだよね。
「あたらしい自分を見つけた!」なぞほざく前に、こういう歴史をよく見といたほうがいい。脳を洗う恐ろしさを。
クルーグマン教授の経済入門 ポール・クルーグマン:主婦の友社:2200円
 山形浩生による桃尻語訳のMIT経済学部教授の経済入門書だ。あまりにあまりに啓蒙的におもしろく刺激的である本書は、入門書はかくあるべきとの見本のような本だ。本書を読んだ後には、この本を基準として大学教授の書いたものを判断しよう。知的ということとおもしろいということとわかりやすいということは矛盾しないことがわかるだろう。そんなものを書けない学者はダメだね。
山形浩生による桃尻語訳のMIT経済学部教授の経済入門書だ。あまりにあまりに啓蒙的におもしろく刺激的である本書は、入門書はかくあるべきとの見本のような本だ。本書を読んだ後には、この本を基準として大学教授の書いたものを判断しよう。知的ということとおもしろいということとわかりやすいということは矛盾しないことがわかるだろう。そんなものを書けない学者はダメだね。
なにがおもしろいって、「80年代に先進国の経済成長率がヒトケタになった理由はだれにもわかっていない」
とか「G7にはなんの意味も無い」とか「アメリカの貿易赤字はなくならない」とか「世界経済は思ったよりグローバル化していない」など、いままでしたり顔で常識といわれていたことをポンポンとひっくり返す。痛快このうえない。
こんな人がノーベル賞取るだろうといわれているのだからおもしろい。彼のホーム・ページもシンプルなので覗いてみたらいかが。学生さんとか参考になるかも。
増補新版
ひめゆり忠臣蔵 吉田司:太田出版:2000円
 沖縄をめぐるルポルタージュが増補新版!になるほど売れることはない。実は毀誉褒貶問題で大問題になり、削除、訂正加筆の結果なのだ。
沖縄をめぐるルポルタージュが増補新版!になるほど売れることはない。実は毀誉褒貶問題で大問題になり、削除、訂正加筆の結果なのだ。
吉田司のオチョクル姿勢は、今回も日本人、沖縄人ともに皮肉な視線を浴びせる。彼の一貫して問いかける視線は、神聖化の阻止でしかない。なにごとも、お涙頂戴の物語に置きかえる、センチメンタル・ジャーナリズムといえる日本のジャーナリズム、日本人の感性。そんなものを笑い飛ばす井戸端会議のようなふざけた口調。取材相手が怒り狂うのもわかるね。
しかしそんな彼の低空飛行の手法は危ういところもあり、真正面の事項には太刀打ちできないし、本分で無い。映画評論家の松田政男の故郷、与那国島の騒動では、勘違いをして土下座して謝るハメになる。それはそれで彼の好きな物語にはまった艶噺だったので、というオチがつくんだけど、反面それが、吉田の危うさでもあると思うね。
しかし、彼の告発するのは、善意の被害者のふりをする無意識の加害者である。それを歴史の観点からだけでは学者であり、現在とどう結びつけるのか戯作するのが彼のやりかた。
沢木とか猪瀬のような、文学に命を売った格好つけジャーナリズムでなく、地べたにしゃがみこむ吉田の見方から見えてくるものはたくさんある。
ニッポンの舞台裏 吉田司:洋泉社:1500円
 冒頭で、雑誌「宝島30」に掲載した、「ビートたけし論」がいまも一人歩きしてたけしが困っているらしいと聞いて、呵々と笑う作者の姿が描かれている。作者にしてみれば、「そーんなこともわからねえで、取材受けてたのかょ」、あるいは「なんで、次の別の論がいつまでも出てこねえのかねえ」だろう。
冒頭で、雑誌「宝島30」に掲載した、「ビートたけし論」がいまも一人歩きしてたけしが困っているらしいと聞いて、呵々と笑う作者の姿が描かれている。作者にしてみれば、「そーんなこともわからねえで、取材受けてたのかょ」、あるいは「なんで、次の別の論がいつまでも出てこねえのかねえ」だろう。
本書は、平成の有名人のプロフィールから、人物はおろか日本が明らかになっていくルポルタージュだ。アエラ誌の「現代の肖像」のページといえば、ああ、と思う方もいるだろう。特に安室奈美恵(沖縄の呪縛からの離脱)、中曽根康弘(永遠の青年将校)、横山ノック(上昇志向と欲望の原点)のレポートは秀逸だ。
人物に対する予断と紙一重の斬りクチの鮮やかさ。その人物の磁場に引き寄せられながらも、スタンスを保つやり方は誰にも真似できない。
さいごに、彼の提唱する「アームチェアー・ジャーナリズム」について書いてある。かれがいうには、「ジャーナリストはそれぞれの視線を持って事象を見るので、現場に言ってもみな同じものを見るとは限らない。自分の視点があれば、現場に行かなくてもルポルタージュは書ける」という冗談とも本気ともいえるジャーナリストへの挑発で、これに呼応して競作を受け入れたのは吉岡忍だけだったが、それも同じ題材とはならなかったので厳密には実験は成功していない。
大宅壮一文庫通いで、記事を埋めるジャーナリズムに対しての警鐘であるとともに、彼自身の現場通いの手法に対するひとつの答えであり、スタンスの表明とも思える(「下々戦記」参照)。そのあたりが、ドキュメンタリー映画集団・小川プロとの決別にも一因があるのではないか。そのあたりについてもいずれ語ってほしい。ほかのジャーナリストがひいても、同文庫の創始者の、「一億総白痴化」を言った男だったらこの挑戦、おもしろがって受けて立っただろう。
ぼっけえ、きょうてえ 岩井志麻子:角川書店:1400
 岡山という土地を縦断していくと、山の合間に黒色の屋根瓦の屋並みが続き、横溝正史の世界に近づく、そしてあきらかに空気が変わる地点がある。瀬戸内の開けた空気が、陰鬱な山の空気に変化する地点がある。そこでは美しい黒々として緑の森が続く中、鳥の声もしない森閑とした世界がひとを包む。岡山の山間がこの作品の背景にはある。
岡山という土地を縦断していくと、山の合間に黒色の屋根瓦の屋並みが続き、横溝正史の世界に近づく、そしてあきらかに空気が変わる地点がある。瀬戸内の開けた空気が、陰鬱な山の空気に変化する地点がある。そこでは美しい黒々として緑の森が続く中、鳥の声もしない森閑とした世界がひとを包む。岡山の山間がこの作品の背景にはある。
たしかに瀬戸内の話もある。が標題の作品をはじめ、作品世界を覆う空気の重さはなんだ。ストーリーなどに新奇なものはないが、寝物語としては、悪夢を見るには絶好の子守唄だ。その文体を愉しめば良い。短編集としてよくできているし、非常にいやな気分になる。それは面白い小説を読んだ高揚と相殺されるので心配はいらない。
それにしても横溝正史は偉大だと思う。かれがいなければ、田舎の猟奇を美しく描く小説のカタチは生まれなかったのではないだろうか。
第三閲覧室 紀田順一郎:新潮社:1900
 大体、本の収集家なんて人種にまともな奴がいるはずがない。作者の古書探偵シリーズを読めばそれがわかる。今回は多摩ニュータウンに新設された大学図書館で起きる殺人事件だ。ここでも本に魅入られすべての失って行く人間たちが描かれる。滑稽でありながら容赦のない人物の造型は作者の世界の特徴だろう。北村薫とそれほど世界は変わらないのにこの落差はなんなのかと思った次第です。
大体、本の収集家なんて人種にまともな奴がいるはずがない。作者の古書探偵シリーズを読めばそれがわかる。今回は多摩ニュータウンに新設された大学図書館で起きる殺人事件だ。ここでも本に魅入られすべての失って行く人間たちが描かれる。滑稽でありながら容赦のない人物の造型は作者の世界の特徴だろう。北村薫とそれほど世界は変わらないのにこの落差はなんなのかと思った次第です。
巷説百物語 続 京極夏彦:角川書店:2000
 探偵小説の欺瞞とジレンマは、「なぜ探偵は殺人犯人の行動を最後まで止めることができないのか」ということだ。なぜなら、途中で犯人を捕まえてしまうと物語がおわってしまう。では殺人を止められないのに名探偵と呼ばれるのは矛盾していないか。それじゃ探偵小説自体を否定する結果となってしまう。
探偵小説の欺瞞とジレンマは、「なぜ探偵は殺人犯人の行動を最後まで止めることができないのか」ということだ。なぜなら、途中で犯人を捕まえてしまうと物語がおわってしまう。では殺人を止められないのに名探偵と呼ばれるのは矛盾していないか。それじゃ探偵小説自体を否定する結果となってしまう。
そのようなことは、探偵小説を書いている小説家は少なからず感じていることだ。
本書はこのジレンマに一石を投じている。ここでは、探偵は犯人を見つけるのではなく、自ら事件を作り上げて、別の解決方法を見つけ出して、妖怪の仕業として煙に巻くのだ。言い様によっては出来の悪いディスクン・カーとも考えられる。そこに衒学とオカルトが入り乱れる大時代な読み物となっている。シャーロックホームズを読み終えた中学生から、カーが好きなゴリゴリの本格派まで楽しめます。
斧 ドナルド・E・ウエストレイク:文春文庫:667
 どちらかというと、ウエストレイク名義なのかは大いに疑問があるところだけども、敢えて言うなら、初期の「雇われた男」などの、辛い読後感のある作品にテイストは近い。そこに作家としての語り口の充実さを加えたところに、ほかのブロック・バスターの作家なら上下巻にしてしまうのをさらりと書き連ねる余裕を感じさせる。
どちらかというと、ウエストレイク名義なのかは大いに疑問があるところだけども、敢えて言うなら、初期の「雇われた男」などの、辛い読後感のある作品にテイストは近い。そこに作家としての語り口の充実さを加えたところに、ほかのブロック・バスターの作家なら上下巻にしてしまうのをさらりと書き連ねる余裕を感じさせる。
失業中の主人公が、自分の就職を成功させるために、自分に似た職歴の相手(求職のライバルね)を殺して行く。ありえないことではない、アメリカのサバイバル事情を衝いているかれのある種のオブセッションがもしれない
(「悪党パーカー 人狩り」の冒頭の、パーカーと対比される通勤するサラリーマンの描写を思い出す) 。
過剰な暴力の正当化と不条理さをバランス良く配置して、主人公の傍目に狂気、本人は本気という、古典的な心理の流れを全うしており(最近はこれができない作家が多すぎる)、そこに練られたストーリーの奇抜さがより興味を深め、ほんとうのエンターテインメントとして成立している。この奇抜なアイディアを説得力ある語り口で読ませるところが、さすがだ。このずれてなさは貴重ですらある。日本の職業作家はほぼ全滅だものね。
ねじまき鳥クロニクル
第一部 泥棒かささぎ編 1600
第二部 予言する鳥編 1800
第三部 鳥刺し男編 2100
村上春樹:新潮社
1980年代初頭にYMOが音楽をはじめとしてあらゆる部分を席巻した時に、近田春夫がかれらの人気について「YMOは、逆輸入の左ハンドルの日本車だ」と喝破した。そして90年代、小室哲哉が徹底的にそれを、大量生産可能なものとして以来、音楽はなにか別のものとなってしまった。
村上春樹についても同じことが言える。かれを構成していた、スティーブン・キングとレイモンド・チャンドラーの手法の翻訳と、蓮実重彦の「小説から遠く離れて」で言及された、「不在と妹の力」によるストーリーの骨子が、80年代的であったかどうかは、90年代の沈滞がそれを物語っているとは言えないだろうか。
コムロテツヤ的な部分は、肥大化したミステリー分野に吸収されて、より日本的な文体に拡散され (馳星周、宮部みゆき)、もう一方の翻訳の部分は分厚いだけのエンターテインメントに行きついた(小野不由美、瀬名秀明)。
そこには、村上春樹の出番はあるのだろうか。政治や風俗にコミットしているようかにみえて、実はノスタルジーとセンチメンタリズムに変換していった手法は限界に来ていることは本人がわかっていたと思う
(かれのエッセーが保守的・通俗的なのをみればそれがわかるだろう) 。
結果かれは、同じものがたりをだらだらと書きつづけることを選んだ。小説家としてではなく、村上ブランドとしてファンを慰撫することに徹することにしたようだ。
ここには、謎の過去の事件や、謎の金持ち、ひとが良いけど結果なにを考えているのかわからない主人公、失踪する女性、かれを助ける変わっているけど美しい女性が出てくる。「羊をめぐる冒険」から「世界の終わりとハード・ボイルド・ワンダーランド」へと続く小説群と同じだ。かれのファンであるなら、期待は裏切られない。ただお得意の固有名詞の羅列は止めたようで、逆に、それが時代を80年代の話のように思わせている。
睡魔 梁日石:幻冬社:1800
 これは作者のクロニクルでいうと、「血と骨」の中盤で、東京に逃げた長男が、「タクシー狂騒曲」の舞台を、事故で去ったあとの事件である。
これは作者のクロニクルでいうと、「血と骨」の中盤で、東京に逃げた長男が、「タクシー狂騒曲」の舞台を、事故で去ったあとの事件である。
何度も指摘しているが、梁日石は実体験を基にしたものが抜群におもしろい。それは裏返すと著者の欠点でもあるのだけれども。
事故でタクシー運転手を辞めた在日の作家でもある、主人公はかれと同じく出身地の大阪を追われ、東京に出てきた友人とともに、健康磁気ベッドの販売にはまって行く。
時期はバブルの前夜、お判りだと思うが、ただの訪問販売ではない。ネズミ講式のマルチ商法なのである。最初は嫌がっていた主人公は、売上を伸ばしていくうちに、どんどん金銭感覚が麻痺して行く。と同時に人間的にもボロボロになっていく。
この商法は、自己開発セミナーとセットになっており、その講習会の様子がこと細かに書かれ圧巻だ。後半、販売組織がヤクザ紛いの集団になっていくところなど、
悪が悪を呼ぶ、一流のピカレスクロマンになっている。このアクの強さがこの小説のおもしろさ。
作者の分身の主人公が、この仕事に批判的である割には金儲けの中枢にいたりする矛盾があるのだが、それが読み手を混乱させられる。主人公が格好良すぎてキタナイことしないように書かれるのが、作者の小説の限界であるんだけど、それを突っ放せればもっとおもしろくなるんだけどなあ。
奇術探偵曾我佳城 泡坂妻夫:講談社:3200
 最後の一行を読む。しばらく絶句したあとに、うーんと唸る。前の文章を読み、さらに前の章に戻り、舌打ちをしながら、その前の短編を読みなおし、パラパラとページをめくり一番最初に戻りためいきをつきながら、表紙の裏カバーを剥がし、じっと見てから地団駄を踏む。まただ、また泡坂妻夫のマジックに見事にやられてしまった。
最後の一行を読む。しばらく絶句したあとに、うーんと唸る。前の文章を読み、さらに前の章に戻り、舌打ちをしながら、その前の短編を読みなおし、パラパラとページをめくり一番最初に戻りためいきをつきながら、表紙の裏カバーを剥がし、じっと見てから地団駄を踏む。まただ、また泡坂妻夫のマジックに見事にやられてしまった。
本書は、いままでに出た女奇術師、曾我佳城シリーズを一冊にまとまたものである。奇術研究家としても著名な作者がその愛情を注ぎ込んだ集大成であり、泡坂魔術健在です。
この本自身がトリックともいえるので、なにも書きません。ただゲーム性以外の倫理観を探偵小説に求める松本清張な方にはお薦めできません。エラリー・クイーンが好きでない人は読まないほうがいいです。はっきり言ってかなりすれっからしの愛好家じゃないとたのしめませんよ。
それにしても、毎回出る凝った名前はどういう裏があるのだろうか。だれか解明したかなあ。情報求む。
子猫が読む乱暴者日記 中原昌也:河出書房新社:1200円
 あいかわらずのの狂暴さはわかりにくく、どこにも組しない孤高あるいは孤独さを巻き散らしている点では、かれの評論集
「ソドムの映画市」の続編ともいえよう。その語り口は鬱屈を評論という形にこだわらず、不機嫌なまでのつぶやきに変えながら唐突に枚数になったから投げ出すように終わる。
あいかわらずのの狂暴さはわかりにくく、どこにも組しない孤高あるいは孤独さを巻き散らしている点では、かれの評論集
「ソドムの映画市」の続編ともいえよう。その語り口は鬱屈を評論という形にこだわらず、不機嫌なまでのつぶやきに変えながら唐突に枚数になったから投げ出すように終わる。
これを小説の流れに位置させるかどうかは、評論家次第なのだけど、著者はたぶんそのようなカテゴリー分類をも拒否する
ことを視野に入れながら書いているのだろう。かれにとって小説は、なにかを表現する昇華されたアウトプット・ツール(情念)ではなく、選択肢のひとつ(怨念)に過ぎないのだから。映画や音楽のように様々な解釈は甘受するが、体験することによってのみたのしめることを書き示しているといえる。
サバイバー チャック・パラニューク:早川書房:1900円
 「ファイトクラブ」でそのヴィジュアルイメージの強烈さを読者に印象付け、ここ数年で図抜けた才能を見せてくれた
感のある作者が前作以上の、巧緻さで塗り上げたありとあらゆるFUCKOFFな文学に向けた挑戦状である。これを受け取るか受け取らないかはあなたの自由だが、
これを読まずして、今後の文学を語ることは無意味だと断言しておこう。
「ファイトクラブ」でそのヴィジュアルイメージの強烈さを読者に印象付け、ここ数年で図抜けた才能を見せてくれた
感のある作者が前作以上の、巧緻さで塗り上げたありとあらゆるFUCKOFFな文学に向けた挑戦状である。これを受け取るか受け取らないかはあなたの自由だが、
これを読まずして、今後の文学を語ることは無意味だと断言しておこう。
たとえば、極東の島国では80年代の半ばごろ、高橋源一郎が「さよならギャングたち」でデビューし、「中島みゆきソングブック」へ向かったように、ある種の強暴さを放った読み物が存在できた。そのころの彼を国電の中で目撃したことがあるんだけど、座席に座り、肉体労働を糧にしていたことを物語るガタイのいいその身体を米軍放出のダーク・オリーブのジャケットに包み、ビニール製の袋を脇に、一心不乱に文庫本を読みふける姿は、人を寄せ付けない不機嫌さをまとっていた。その後、そのあたりの輩はテレビとかカラー写真がいっぱい載っている雑誌に取込まれてつまらなくなるんだけどね。いまなら中原昌也かなあ。あと、別な意味で梁日石。
そういう居心地の悪さをぎりぎりのセンスに置きかえる趣味のよさ、「悪趣味」といえる露悪さでいえば、憐憫のかけらも無い不快さにこの小説は突き進む。スティーブ・エリクソンなどの、不幸な振りをした、心地よい予定調和とは違う世界を目指していることは確かだ。
そう、ストーリーだ。ストーリーが大切だ。物語は、いきなり、墜落しそうになっているジャンボジェット機の中で男が独白を始めるシーンから始まる。
この男は、集団自殺したカルト教団の唯一の生き残りなのだ。独特な世界における教義のなかで育った男は、ただひとり取り残される。それが、なぜジャンボ・ジェットにいるかって?彼の生涯がフラッシュバック形式で描かれて行く。
これ以上は、楽しみを奪うので書けないのだが、資本主義の寓話、すべてがショーになる、不幸でさえも商品だという世界を道化ではなく、「ならざるを得なかった無垢」、恐ろしい言い方を敢えてすれば、
すべてを見てしまった子供という大胆な視点を持って語られる。それはイブリン・ウォーの「囁きの霊園」のような異邦人の受身の被害者的な立場ではなく、確信犯的な受身の加害者、「生まれたときから手は汚れている」存在を無理なく語り手として作り出している。そして、現実の不条理ではなく、不条理の現実を過不足無く浮き彫りにする。
キーパーソンの女性が出てくるのだが、この全能の女性は、村上春樹をはじめとして、いまもだが日本の男性作家たちが描けなかった、「小説から遠く離れて」の蓮実重彦というか柳田国男の言葉を借りるなら「妹の力」を越えた女性として登場する。今後も日本では出てくるだろう、「曖昧な力をもった謎の女性」というのはすべて粉砕されるくらいの練られた登場人物だ。
最後に言う、この小説がデヴィッド・フィンチャーによって映画化される前に読まなければならない。賞味期限つきの傑作である。
希望の国のエクソダス 村上龍:文藝春秋:1571円
 いつも思うんだけど、村上龍の小説っていつも宣伝文句以上であった試しがないんじゃないか。 キャッチコピーに書かれていることはないのね。今回は確か、「2002年、全国の中学生が日本を後にする」みたいなものだと思ったけど、まさにそれ以外のこと書いてないんだよ。それは小説として破綻がないということでもあるし、尻つぼみと言ったほうが正解かもしれない。大風呂敷をひろげたは良いけど閉じられなくなる、しかしこのまま突っ走ったら、批判を受けるので自爆装置を作動させる。いつもこのパターンだ。でなければ、だらだらとした連作小説体となる。
いつも思うんだけど、村上龍の小説っていつも宣伝文句以上であった試しがないんじゃないか。 キャッチコピーに書かれていることはないのね。今回は確か、「2002年、全国の中学生が日本を後にする」みたいなものだと思ったけど、まさにそれ以外のこと書いてないんだよ。それは小説として破綻がないということでもあるし、尻つぼみと言ったほうが正解かもしれない。大風呂敷をひろげたは良いけど閉じられなくなる、しかしこのまま突っ走ったら、批判を受けるので自爆装置を作動させる。いつもこのパターンだ。でなければ、だらだらとした連作小説体となる。
前者は「コインロッカーズ・ベイビー」、「愛と幻想のファシズム」、「昭和歌謡大全集史」、「五分後の世界」など。後者は、「テニスボーイの憂鬱」、「トパーズ」、「ラブ・アンド・ポップ」、「だいじょうぶマイフレンド」、「ラッフルズホテル」、「ライン」、など。
前者で致命的なのは、いつも音楽や映画を特権的なものとして神聖化し、持ち上げすぎて降りてこられなくなってしまう感がある。芸術的な才能を持つ人間を
「全能神=天才」と称するのでストーリーが進まなくなるのだ。彼らのやることは、いつも成功して大衆の支持を簡単に受けられスター化するので、その後彼らのすることはすべてうまくいく。そのため、後半になるとストーリー展開がどんどん安易になっていく。そして肥大化するだけして、空中分解する。後者の場合も、特権的な主人公を軸に据えるが、同じ話でも連作のため、看板を替えるので一応飽きないようにはされている。
結局、それは村上龍の小説がキャッチコピー的な発見、電通的なウリをカリスマ的な人物に仮託するからだ
。そのため語りやすく、読みやすく、議論されやすい、消費物に転換されるのだ。
ここで、問題なのは、小説としての問題ではなく、小説のまわりの問題にすりかわることだ。 それは最終的に、中田英寿とオトモダチの作者の仕掛けをどう思うか、その意見を強要することにつながる。いわば、新聞と同じく、別にその記事に対してなんの意見もないけど、無関心は許さないという、極めて戦後民主主義的な強制参加を求められるのだ。
だから、結末は出せないのだ。だって高校の多数決と同じなんだもん。無意味な議論は延々と続けられるけどね。でもこの人は、公平とか、進歩的とか装っているが、実はそんなこと考えてないで、「一人の天才だけががすべてを変える(自分を含む)ことができる」と考えているのだ。
この矛盾した考えのため村上龍の小説はいつも空中分解せざるを得ないのだ。まあそこら辺に、彼の映画に対する永遠のコンプレックスがあるのかもしれない。「特権的な俺様が芸術的な映画が作れないはずがない!」そんなことないのは、証明されているいるんだけどなあ。
あ、最後になるけど、本書は、「愛と幻想のファシズム」の構成に、「電脳ナイトクラブ」の会員となる中学生が出てくる話である。おわり。
誇りへの決別 ギャビン・ライアル:早川書房:2100円
 シリーズ第二作。イギリス情報部黎明期、第一次世界大戦前の欧州情勢をめぐる権謀術数、今回の目玉は飛行機とイタリアである。飛行機好きのライアルとしては本領発揮だ。まだ海のものとも山のものともわからない新兵器をどう料理するのか見もの。
シリーズ第二作。イギリス情報部黎明期、第一次世界大戦前の欧州情勢をめぐる権謀術数、今回の目玉は飛行機とイタリアである。飛行機好きのライアルとしては本領発揮だ。まだ海のものとも山のものともわからない新兵器をどう料理するのか見もの。
またイタリアは新興国家としてオーストリア王国との対立も描かれる。 ここら辺を読むと昨今のユーゴ情勢も少し見えてくる。
愛国的詩人として三島由紀夫も入れ揚げていたダヌンツィオも登場し、いつものやるきのないスパイ大尉と、アイルランド革命家くずれの彼の部下、美貌のアメリカ人富豪のトリオも活躍する。
本格的冒険間諜小説をご堪能あれ。
ハイスクール・パニック リチャード・バックマン:扶桑社文庫:590円
コロラド州、コロンバイン高校の大虐殺は、少年犯罪上エポック・メイキングな事件であったが、ショットガンで自分のアタマをぶち抜いた少年たちは、
この本を読めばもうちょっとましなことできたのではないだろうか。スタローンとかシュワルツネッガーの爆発
映画が蔓延する前の、ビジュアル先行型小説(余計な描写のため50ページほど意味なく長い)以前のつつましいアクション型小説である。高校生の妄想の限界はいかにビジュアルの肥大化とともに増大していくかを示す、70年代から80年代への「ペーパー・バック=現実」の証拠の一冊といえよう。
死のロングウォーク リチャード・バックマン:扶桑社文庫:667円
キング版「バトルロヤイアル」というか、こっちが本家なんだけどね。独裁国家アメリカで17才の少年が最後の一人になるまで歩きつづけるという作者が大学時代に書いた習作を屋根裏から引きずり出して出版したらしいということでわかるように、非常に類型的で粗い出来。短編としてのアイディアでどこまで書けるかを試したようなもので、バックマンシリーズの常として身も蓋も救いも無い読後感となっている。1時間くらいで読めるのでキング=バックマンを研究する人にはお薦めします。
キングのお里がいかに50年代ドライブイン・B級ホラーであったかが構造的に透けて見えて、 「なぜキングの原作の映画はつまらないのか?」
が理解できるヒントにもなります。
ハード・タイム サラ・パレツキー:早川書房:2000
 いつも水準点を越える出来なので安心して読める少ないシリーズとして重宝しています。登場人物が自分たちとともに歳を取って行くのは続き物ミステリーのひとつの特権とも言えます
(まあ、そういうのを拒否するミステリー通連中もいるけど) 。
いつも水準点を越える出来なので安心して読める少ないシリーズとして重宝しています。登場人物が自分たちとともに歳を取って行くのは続き物ミステリーのひとつの特権とも言えます
(まあ、そういうのを拒否するミステリー通連中もいるけど) 。
たぶんに、シカゴの風俗小説として読みつづけるのがよいのだろうが、今回は刑務所問題というホットな問題が全面に出てくる。
このウォーシャウスキー・シリーズが魅力的なのは、被害者や脇役を含め、登場人物が魅力的に肉付けされているからだろう、もちろん主人公の彼女は相変わらず魅力的なのだが。
今回、シカゴで撮影がはじまるテレビシリーズの、オープニング・パーティーが謎の発端となる。ここからいろんな事件が膨らんで行く。主人公の無茶な行動を笑ってすませるために、全巻読んで彼女のファンとなろう。
ボーン・コレクター ジェフリー・ディーヴァー:文藝春秋:1857円
 「アームチェアー・ディティクティブ」という探偵小説の分野があり、非常に古典的なものだが、成功しているものは少ない。なぜかというと、パズル型犯人当てミステリーでは、絶対的なんでも当てる探偵「デウス・エキス・マテナ」(全能神)の存在が不可欠なのだが、この時代そんな人間がリアリティを持つはず無いし、いわば証拠隠匿にならざるを得ない。
「アームチェアー・ディティクティブ」という探偵小説の分野があり、非常に古典的なものだが、成功しているものは少ない。なぜかというと、パズル型犯人当てミステリーでは、絶対的なんでも当てる探偵「デウス・エキス・マテナ」(全能神)の存在が不可欠なのだが、この時代そんな人間がリアリティを持つはず無いし、いわば証拠隠匿にならざるを得ない。
ということで、なんの解決も出来ず書かれてしまった本書は、脳みそを働かせずに、受身で読む分にはなんの問題も無い。先まわって読もうとすると、
主人公の馬鹿さ加減と、作者のご都合主義に辟易する。ひまつぶしには最適の一冊。
夢へのレクイエム ヒューバート・セルビーJR:河出書房新社:2400円
 『レクイエム・フォー・ドリームス』として映画化されたので、期待半分で読んでみたけど、すでに出てからかなり経っている事に気づいた
。典型的な80年代のドラッグがらみで壊れて行くニューヨークの若者たち を描いた、そのまんまの内容であった。いまとなっては、だらだらの地と会話とモノローグを分けない書き方ももう懐かしい感じだ(スティーブン・エリクソンとかね)。
『レクイエム・フォー・ドリームス』として映画化されたので、期待半分で読んでみたけど、すでに出てからかなり経っている事に気づいた
。典型的な80年代のドラッグがらみで壊れて行くニューヨークの若者たち を描いた、そのまんまの内容であった。いまとなっては、だらだらの地と会話とモノローグを分けない書き方ももう懐かしい感じだ(スティーブン・エリクソンとかね)。
なにが古いのかというと、閉じられた孤独の世界を描いていることなんだよね。これって、日本で言えばオウム事件、アメリカならオクラホマ連邦ビル爆破、その原因のブランチ・デビアン教会事件で、終止符を打たれた時代だと思う。うーん例えてみれば、
「終末論」で世界観を語れる時代の終焉なのかなあ。すべてをそれが背景にある小説は、21世紀を越えられないと思うんだ。それより先に進めないと思う。これはあらゆる芸術において同じではないだろうか。
デスペレーション スティーヴン・キング:新潮社:3000円
レギュレイション リチャード・バックマン:新潮社:2300円
 スティーブン・キングにはしばらく愛想を尽かしていた。「IT」以降、あのシャベリ文体が翻訳のせいだけじゃなくホント鼻についていたのだ。それが、「ローズ・マーダー」など、異常者の脳みそに入り込んだような文章がのた打ち回っているのをながめているうちに読む気がなくなってしまうのであった。「グリーン・マイル」は制約があったせいか、以前のキング節が復活していた。
スティーブン・キングにはしばらく愛想を尽かしていた。「IT」以降、あのシャベリ文体が翻訳のせいだけじゃなくホント鼻についていたのだ。それが、「ローズ・マーダー」など、異常者の脳みそに入り込んだような文章がのた打ち回っているのをながめているうちに読む気がなくなってしまうのであった。「グリーン・マイル」は制約があったせいか、以前のキング節が復活していた。
さあ、この二作であるが、位置付けがあいまいなんだよね。「レギュレイション」はバックマンの賑やかしである。なんの裏もないけどね。読み物としてもちょっと半端だ。ネタとしては短編なんだけど、まあバックマン名義がみんなそうだけどね。
わたしが感心したのが、「デスペレーション」。ハイウエイから外れた寂れた鉱山町に現れた古代の邪悪な神が復活し、そこに偶然、必然的に集まった人たちが戦うというシンプルな物語。
登場人物のひとりが何度もつぶやく「神は残酷だ」というセリフに代表されるように、善と悪の物語である。
それをディーン・クーンツのような薄っぺらい舞台を背景にしながら、人物に犠牲と再生という古典的、神話的な枠組を与えることで物語を深化させることに成功した。
物語のテンションの高さは保証する。
ただわかったら教えて欲しいのだけど、主人公の作家が泣くところがあるのだけど、あのきっかけの事件がよくわからなかった。一番重要なシーンなのにちょっと不明なのだ。情報と解釈を求む。

ポップ1280 ジム・トンプスン:扶桑社:1429円
 「雑貨屋のドストエフスキー」と呼ばれ、ようやく再評価され出した、ジム・トンプスン。この小説、実は読むのにというか、読み始めるのに異常に時間がかかった。なぜか。こんな文章を小説として読んだことが無いからだ。主人公の目を通してみた田舎街の描写、これがなんか変だ。アタマが悪い人間がスローモーションのようにふわふわと歩いている、そんな印象なのだ。
「雑貨屋のドストエフスキー」と呼ばれ、ようやく再評価され出した、ジム・トンプスン。この小説、実は読むのにというか、読み始めるのに異常に時間がかかった。なぜか。こんな文章を小説として読んだことが無いからだ。主人公の目を通してみた田舎街の描写、これがなんか変だ。アタマが悪い人間がスローモーションのようにふわふわと歩いている、そんな印象なのだ。
こんな語り口ってあり?!と驚く暇も無く、事件は欲望のままに進んでいるように見えた。典型的ないなかの事件の展開である。セックス、金、暴力。パルプフィクションとしてストーリーが展開しながらも、人物造型が複雑に現代的だ。チャンドラーほど、気取ってなく、マクドナルドほど陰鬱ではなく、スピレーンよりも頭の良い主人公、ハリード・チェイスの女たちよりも淫乱。
どこの塑型にもはまらず、孤独な作品。
以前「ゲッタ・ウエイ」を読んだとき映画と違いなんて暗い小説なんだと思ったけど、いま読みなおしたらおもしろいと思う。
ハード・ボイルドずれをしたみなさまに送る、絶対に後悔させない一冊。
内なる殺人者 ジム・トンプスン:河出書房新社:1400円
 ひとの中にある邪悪な本質を識るのに、「罪と罰」のような三文メロドラマを読む必要は無い。ジム・トンプスンがあればいい。ここには、
ロシアの文豪もたどり着けなかった地点が凝縮されて描かれている。 ハードボイルドの始祖としてのダシール・ハメットも結局は19世紀の人間であって、小説に浪漫主義的な理想部分をどこか捨てきれないでいたと思う。
ひとの中にある邪悪な本質を識るのに、「罪と罰」のような三文メロドラマを読む必要は無い。ジム・トンプスンがあればいい。ここには、
ロシアの文豪もたどり着けなかった地点が凝縮されて描かれている。 ハードボイルドの始祖としてのダシール・ハメットも結局は19世紀の人間であって、小説に浪漫主義的な理想部分をどこか捨てきれないでいたと思う。
そこから入った読者はこのトンプスンのあまりにもそっけなく、救いのない物語舞台に、なにかを見出すことはむずかしい。受け入れるか嫌うかどちらしかない。どちらにしても今までの世界が壊れることは確かだ。その覚悟がおありならこの本は絶対に読むべきだ。覚悟が無ければ、卑しい街を男がひとり歩いていく小説を読みつづけることだ。
俺、南進して。 町田町蔵 荒木経惟:新潮社:1900円
 町田町蔵の軽薄重調文章は好きだ。やるせないほど駄目男も良い。だけど、アラーキーとのコラボレーションはちょっと企画としては面白いけど、結果お互いに、自分のテリトリーを守りつつ、この辺で手打ちにするかのような、
中途半端な心地良さを目指してしまったために、刺激的な読み物には程遠い出来となった。
町田町蔵の軽薄重調文章は好きだ。やるせないほど駄目男も良い。だけど、アラーキーとのコラボレーションはちょっと企画としては面白いけど、結果お互いに、自分のテリトリーを守りつつ、この辺で手打ちにするかのような、
中途半端な心地良さを目指してしまったために、刺激的な読み物には程遠い出来となった。
町田町蔵の小説のおもしろさは、彼自身がモデルかもしれないけど、まさかこんなことは、あるまいと読者が笑える、その法螺話に魅力があったのだけど、アラーキーの写真に彼自身が出ることによって、法螺話が想像できる高さにしかならないので、法螺じゃないのでおかしくもなんともないのである。
またアラーキーの写真の小説性も、一見無関係な写真を並び替えただけで、エロスやストーリーを生み出すのがその真骨頂ではないだろうか。まあ大阪との相性があまりよくない気もするけどね(大阪でも難波だけど、その辺のこだわりは関西人で無いわたしにはわからないです)。
結果として、荒木の写真は、町田の文章に合わせたものとなった。逆に、町田の文章は、荒木の写真に合わせたものとなったでもいいのだけど。
ふたりでやることが相乗ではなく、相殺効果となった。
妖怪馬鹿 京極夏彦 多田克巳 村上健司:新潮OH!文庫:695円
 こういうだらだらとした本をだすのがいいかは別として、売れるためなら何でもやる新潮社の姿勢に脱帽。
こういうだらだらとした本をだすのがいいかは別として、売れるためなら何でもやる新潮社の姿勢に脱帽。
内容は、水木しげる原理論者の三人が、妖怪についてだべるという、暇つぶしには最適な本書。カタログ的でさらに進むためには、本格書をそれぞれ読めという暗黙のメッセージを発しているところが良い。まあ良く読むと
、怪獣博士で物足りないヒトが妖怪馬鹿になるのだなあとわかる。京極夏彦による、パロディー模写漫画が絶品。これだけでも読む価値がある。ちなみに、水木しげる、いしいひさいち、楳図かずお、高橋留美子、永井豪、赤塚不二夫、藤子A不二雄、川崎のぼる、諸星大二郎、田川水泡、しりあがり寿、吉田戦車、つげ義春、喜国雅彦、松本零士、石森章太郎、さいとうたかお、みうらじゅん、手塚治虫、山上たつひこ、鳥山明、つのだじろう、東洲斎写楽。
突破者流・ 勝ち残りの鉄則 宮崎学:ダイヤモンド社:1500円
 宮崎学はたくさん書きすぎて、読み終わったら忘れてしまうものも多いけど、作者自身が金のためとそうでないものを分けているので読者としても心構えができる。
わたしは彼を梶山季之、藤原審爾、竹中労の系列に置きたい。実践的文学ルポルタージュとでも呼ぼうか。前者三人もほとんどいまは忘れられているし、本も手に入りにくい。わたしは彼らを忘れてはならないと考える。いずれも汎的視点を持つ人たちだった。
宮崎学はたくさん書きすぎて、読み終わったら忘れてしまうものも多いけど、作者自身が金のためとそうでないものを分けているので読者としても心構えができる。
わたしは彼を梶山季之、藤原審爾、竹中労の系列に置きたい。実践的文学ルポルタージュとでも呼ぼうか。前者三人もほとんどいまは忘れられているし、本も手に入りにくい。わたしは彼らを忘れてはならないと考える。いずれも汎的視点を持つ人たちだった。
本書は、雑誌に書かれた反語的ビジネス提言であり、本文はいままで言っていることの繰り返し部分が多い。ただし最後にある佐高信氏との対談は示唆に富んでいて、いまの状態を計り知るに良いガイドになる。この国は一部のエスタブリッシュメントの、利益保持のために存在しているという指摘が刺激的だ。
 ビジネス礼賛本か、週刊誌暴露本か、という二者択一しかなかった、現在進行形の人物評伝の世界にようやっと、すこしはまともな本が出たことは非常に喜ばしい。これが
この手の本のスタンダードとなることを期待する。というか少なくともこの本のレベルを指針としてほしい。
ビジネス礼賛本か、週刊誌暴露本か、という二者択一しかなかった、現在進行形の人物評伝の世界にようやっと、すこしはまともな本が出たことは非常に喜ばしい。これが
この手の本のスタンダードとなることを期待する。というか少なくともこの本のレベルを指針としてほしい。 アメリカ人の実直なところは、このように自分のテクニックを多くの人にわかりやすく述べて行こうとする姿勢にある。決して秘伝としないところだ。キングは、小説作法といっても、決して一筋縄ではいかないテクニックで読むものを引きつける。
アメリカ人の実直なところは、このように自分のテクニックを多くの人にわかりやすく述べて行こうとする姿勢にある。決して秘伝としないところだ。キングは、小説作法といっても、決して一筋縄ではいかないテクニックで読むものを引きつける。 長らく待たれた作者のテレビゲームに対する著作が遂に出た。予想以上の濃い充実した内容なので、コンピュータ文化関係の概論について学ぶには最適な書ではないだろうか。
長らく待たれた作者のテレビゲームに対する著作が遂に出た。予想以上の濃い充実した内容なので、コンピュータ文化関係の概論について学ぶには最適な書ではないだろうか。 このシリーズの第5弾はカリフォルニアを北から車で海岸沿いに下りて来る。そこにあるひとつひとつのビーチが、どのような背景から生まれてきたのかを示している。特にカリフォルニアの
ベニス・ビーチの変遷はカルフォルニア伝説のひとつだろう。
このシリーズの第5弾はカリフォルニアを北から車で海岸沿いに下りて来る。そこにあるひとつひとつのビーチが、どのような背景から生まれてきたのかを示している。特にカリフォルニアの
ベニス・ビーチの変遷はカルフォルニア伝説のひとつだろう。 ジャッキーチェンの個人通訳として、また料理の鉄人をはじめさまざまなテレビ雑誌の取材コーディネーターを勤める作者が薦める、「香港には二度以上来ている人のため」の旅行ガイド
である。なかなか一筋縄に行かない香港の裏まで知り尽くしたひとだけが知る香港の姿が見えます。
ジャッキーチェンの個人通訳として、また料理の鉄人をはじめさまざまなテレビ雑誌の取材コーディネーターを勤める作者が薦める、「香港には二度以上来ている人のため」の旅行ガイド
である。なかなか一筋縄に行かない香港の裏まで知り尽くしたひとだけが知る香港の姿が見えます。 作者は、輝かしいSASでの経歴の途中で、突如除隊してしまう。そして、そこにあるモノを、ソビエトが侵攻していたアフガニスタン
に運んで欲しいというアメリカ人が現われる。作者はパキスタンから国境を越えて山岳地帯を休まずに三日歩きつづけて、ゲリラ部隊に合流する。そこでソビエトを相手に戦うゲリラの姿。捕虜を虐殺する様子を目撃する。そしてようやくゲリラに持ってきた対空ミサイル砲の使い方を教える。
作者は、輝かしいSASでの経歴の途中で、突如除隊してしまう。そして、そこにあるモノを、ソビエトが侵攻していたアフガニスタン
に運んで欲しいというアメリカ人が現われる。作者はパキスタンから国境を越えて山岳地帯を休まずに三日歩きつづけて、ゲリラ部隊に合流する。そこでソビエトを相手に戦うゲリラの姿。捕虜を虐殺する様子を目撃する。そしてようやくゲリラに持ってきた対空ミサイル砲の使い方を教える。 断片的にしか見えてこなかった赤瀬川が、カタログになって現われるお得な一冊である。「トマソン」から入った者としては、前衛作家としての赤瀬川のクレバーさに驚かされる。その大胆な思考が、本人のキャラクターとは異なり、帝都を揺るがす大犯罪者の末裔となって行く様がオカシイ。
断片的にしか見えてこなかった赤瀬川が、カタログになって現われるお得な一冊である。「トマソン」から入った者としては、前衛作家としての赤瀬川のクレバーさに驚かされる。その大胆な思考が、本人のキャラクターとは異なり、帝都を揺るがす大犯罪者の末裔となって行く様がオカシイ。 この街を生きる誰もが、驚くようなドラマチックな過去を持っている。著者はカメラマンであるが、中国本土返還またぐ時期に、香港に住みながら、大学の語学教室に通う。街に出て様々な人と語り合って行くうちに出てきた言葉が、冒頭のものだ。
この街を生きる誰もが、驚くようなドラマチックな過去を持っている。著者はカメラマンであるが、中国本土返還またぐ時期に、香港に住みながら、大学の語学教室に通う。街に出て様々な人と語り合って行くうちに出てきた言葉が、冒頭のものだ。 そこにカネがある。これは、シリコンバレーの成立から、ネットスケープが、ナビゲーターのシェアがマイクロソフトのエクスプローラーに食われ、没落する頃までを描いている。
そこにカネがある。これは、シリコンバレーの成立から、ネットスケープが、ナビゲーターのシェアがマイクロソフトのエクスプローラーに食われ、没落する頃までを描いている。
 ひとりの作家の生涯を描くのに、二冊の本は相互に補完し合っている。それぞれの描く作家像は、同じ人物かどうか疑うくらいに違う。いや、それぞれが描こうとする人物像はそれほど違っていない。猥雑で有名人が好きで、俗物でありながら繊細な部分もある。そんなポートレイトではある。
ひとりの作家の生涯を描くのに、二冊の本は相互に補完し合っている。それぞれの描く作家像は、同じ人物かどうか疑うくらいに違う。いや、それぞれが描こうとする人物像はそれほど違っていない。猥雑で有名人が好きで、俗物でありながら繊細な部分もある。そんなポートレイトではある。 ジャン=ボールド・リヤールは中東の戦争中に「湾岸戦争はなかった」と書いて、非難を受けまくって、その学者生命を危機に晒した。その後の状況をみていると、かれの発言はあながち間違いではなかったと思う。しかし現実の戦争(たとえテレビでしか見ていないにしろ)、に対して、不可視の戦争を提言しては分が悪すぎた。消え行くメディアの上では、感情にかなうものはないからだ。
ジャン=ボールド・リヤールは中東の戦争中に「湾岸戦争はなかった」と書いて、非難を受けまくって、その学者生命を危機に晒した。その後の状況をみていると、かれの発言はあながち間違いではなかったと思う。しかし現実の戦争(たとえテレビでしか見ていないにしろ)、に対して、不可視の戦争を提言しては分が悪すぎた。消え行くメディアの上では、感情にかなうものはないからだ。 本書はものを売るための指南書ではない。もうひとつ余分に買わせるための指南書である。もっとも、どのような方法を取るにせよ、売上が上がることには変わりはないのだが。それを著者は「衝動買いの重要さ」として上げている。もはや情報やものが行き渡った社会では、消費者が商品についての知識は持っており、商品は、在庫がちゃんとあれば、勝手に客が選んで買われる。問題はその客にもう一度財布を開かせることだ。そのためにはレジの近くに安いこまごまとした商品を置いたり、通路を迂回させて、他の商品に目がいったりするようにする。などのヒントが多く書かれている。
本書はものを売るための指南書ではない。もうひとつ余分に買わせるための指南書である。もっとも、どのような方法を取るにせよ、売上が上がることには変わりはないのだが。それを著者は「衝動買いの重要さ」として上げている。もはや情報やものが行き渡った社会では、消費者が商品についての知識は持っており、商品は、在庫がちゃんとあれば、勝手に客が選んで買われる。問題はその客にもう一度財布を開かせることだ。そのためにはレジの近くに安いこまごまとした商品を置いたり、通路を迂回させて、他の商品に目がいったりするようにする。などのヒントが多く書かれている。 神戸の事件が起きた時に世界の事例として取り上げられたのが、リバプール郊外に住む、8才の少年2人が、2才のこどもを殺害したこの
ジェームズ・バルガー殺人事件だ。すでにふたりは8年の刑期を終え保護観察処分で出所して、名前を変えて生活しているという。
神戸の事件が起きた時に世界の事例として取り上げられたのが、リバプール郊外に住む、8才の少年2人が、2才のこどもを殺害したこの
ジェームズ・バルガー殺人事件だ。すでにふたりは8年の刑期を終え保護観察処分で出所して、名前を変えて生活しているという。
 「言うだけ番長」これが、作者には一番似合う渾名ではないだろうか。天の巻では、作者の属するフィールドワーク、民俗学、文化人類学の書評。地の巻では、マンガ、一般の本、特に90年代の同時代の作者に対する書評。そこに底通する罵倒は、芸としても未熟であり、読んでいて鼻白む。はたして、
大月はかれの仕事に対して他者が同じような罵声を浴びせた時に耐えられるような仕事をしているのだろうか。これが第一の疑問。
「言うだけ番長」これが、作者には一番似合う渾名ではないだろうか。天の巻では、作者の属するフィールドワーク、民俗学、文化人類学の書評。地の巻では、マンガ、一般の本、特に90年代の同時代の作者に対する書評。そこに底通する罵倒は、芸としても未熟であり、読んでいて鼻白む。はたして、
大月はかれの仕事に対して他者が同じような罵声を浴びせた時に耐えられるような仕事をしているのだろうか。これが第一の疑問。 いわゆるグローバリゼーションについて、胡散臭さを感じているのはわたしだけだろうか。グローバリゼーションを考える時に、トヨタのレクサスのように、全世界規格を目指すのか、それとも裏庭にあるオリーブの木を大切にするのかを国際ジャーナリストの視点から見てみるという謳い文句なのだが、どうも乗りきれずに最後まで読んで行くと、あーら吃驚、「グローバリゼーションは必然で、アメリカは一番進んでいる。だから世界に対して指導的な地位を占めるべきだ」の一節で閉じられている。なんだ、
カタチを変えたグローバリゼーション礼賛書じゃねえか。
いわゆるグローバリゼーションについて、胡散臭さを感じているのはわたしだけだろうか。グローバリゼーションを考える時に、トヨタのレクサスのように、全世界規格を目指すのか、それとも裏庭にあるオリーブの木を大切にするのかを国際ジャーナリストの視点から見てみるという謳い文句なのだが、どうも乗りきれずに最後まで読んで行くと、あーら吃驚、「グローバリゼーションは必然で、アメリカは一番進んでいる。だから世界に対して指導的な地位を占めるべきだ」の一節で閉じられている。なんだ、
カタチを変えたグローバリゼーション礼賛書じゃねえか。 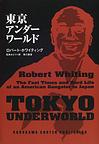 あっと驚くような人物が出てくるわけでもない。ものすごいドラマがあるわけでもない。ただ丹念にその人物を追いかける手法がロイ・ホワイディングの作品を支える。
あっと驚くような人物が出てくるわけでもない。ものすごいドラマがあるわけでもない。ただ丹念にその人物を追いかける手法がロイ・ホワイディングの作品を支える。 「暮らしの手帖」の名編集長のもとで、数年間働いた著者がから見た、花森像である。限定された編集の現場、名功成ったかれをみる作者の視線は、包括的ではなく断片的な記憶からなる。
「暮らしの手帖」の名編集長のもとで、数年間働いた著者がから見た、花森像である。限定された編集の現場、名功成ったかれをみる作者の視線は、包括的ではなく断片的な記憶からなる。 世界で最も謎で、その発言に影響力のある人物、アメリカ連邦準備銀行(FRB)理事の、アラン・グリーンスパンの、理事になってからクリントン時代までのあいだに何が起こり、何を決断し、なにを決断しなかったのかを、本人以外の関係者へのインタビューや公開記録を基に構成した書である。作者ボブ・ウッドワードは、湾岸戦争への開戦プロセスを明らかにした「指導者たち」と同じ手法を駆使する。
世界で最も謎で、その発言に影響力のある人物、アメリカ連邦準備銀行(FRB)理事の、アラン・グリーンスパンの、理事になってからクリントン時代までのあいだに何が起こり、何を決断し、なにを決断しなかったのかを、本人以外の関係者へのインタビューや公開記録を基に構成した書である。作者ボブ・ウッドワードは、湾岸戦争への開戦プロセスを明らかにした「指導者たち」と同じ手法を駆使する。 かれのノンフィクションは伝えたい事象に対して通俗化することをおそれないし、対象を求め作者が希薄になっても構わない。昨今の作者が煩わしい似非ノンフィクション作家とは歴然と違う。題材にしてもすぐ「スーパーテレビ特捜最前線」にネタとしてパクラれそうであっても躊躇しない。そこには伝えることに対する潔さがあるので読みやすいし、押し付けでないので読者自ら考える余地がある。
かれのノンフィクションは伝えたい事象に対して通俗化することをおそれないし、対象を求め作者が希薄になっても構わない。昨今の作者が煩わしい似非ノンフィクション作家とは歴然と違う。題材にしてもすぐ「スーパーテレビ特捜最前線」にネタとしてパクラれそうであっても躊躇しない。そこには伝えることに対する潔さがあるので読みやすいし、押し付けでないので読者自ら考える余地がある。 バブルの終わりのころ、ある人と議論になり、このあとの日本はどんな社会になるかとの問いに、わたしが「これからは、特権意識と金銭意識がはっきりと分かれ、階級社会になる」と言ったのに対し、かれは「いや、階層社会になるだろう。それは日本にはヨーロッパのように階級がはっきりとないからだ」と反論した。なるほど確かに「一億総中流」になったバブル期、そのあとにはいままではっきりとして見えなかった社会格差が見えてくるだろうという部分では同じことを言っていたわけで、ようするに
「持つもの」と「持たざるもの」はとてつもなく大きな差になって社会的に認知されてくるだろうという結論だった。ただそれをどう呼ぶかでのヲタクと団塊での意識の差はあったと思うが。
バブルの終わりのころ、ある人と議論になり、このあとの日本はどんな社会になるかとの問いに、わたしが「これからは、特権意識と金銭意識がはっきりと分かれ、階級社会になる」と言ったのに対し、かれは「いや、階層社会になるだろう。それは日本にはヨーロッパのように階級がはっきりとないからだ」と反論した。なるほど確かに「一億総中流」になったバブル期、そのあとにはいままではっきりとして見えなかった社会格差が見えてくるだろうという部分では同じことを言っていたわけで、ようするに
「持つもの」と「持たざるもの」はとてつもなく大きな差になって社会的に認知されてくるだろうという結論だった。ただそれをどう呼ぶかでのヲタクと団塊での意識の差はあったと思うが。 ノンフィクションライターの吉田司はバブルを「第二の敗戦」と定義した。本書もそれを様々な視点から
「なぜバブルがはじまり、人が踊り、はじけたか」を例証し、なにが起こりなにが失われたかを追っている。
ノンフィクションライターの吉田司はバブルを「第二の敗戦」と定義した。本書もそれを様々な視点から
「なぜバブルがはじまり、人が踊り、はじけたか」を例証し、なにが起こりなにが失われたかを追っている。 原題を「VOODOO SCIENCE」という。なんと魅力的なタイトルではないか。いわゆるインチキ科学を斬る書なのだが、単純に笑うあげつらうのではなく非常に啓蒙的である。
中学生や高校生にぜひ読んでほしい。
原題を「VOODOO SCIENCE」という。なんと魅力的なタイトルではないか。いわゆるインチキ科学を斬る書なのだが、単純に笑うあげつらうのではなく非常に啓蒙的である。
中学生や高校生にぜひ読んでほしい。 かれのノンフィクションは、人物インタビューにより切り取って行く手法と資料の読みこみが、事象の新しい側面を浮き上がらせて行く。
でもこの本はわたし的には?。映画興行についての本も?だったけどね。
かれのノンフィクションは、人物インタビューにより切り取って行く手法と資料の読みこみが、事象の新しい側面を浮き上がらせて行く。
でもこの本はわたし的には?。映画興行についての本も?だったけどね。 カルトとは、組織や個人がある教えを絶対であると教え込み、それを実践される過程で、人権侵害あるいは破壊行為を引き起こす集団である。
カルトとは、組織や個人がある教えを絶対であると教え込み、それを実践される過程で、人権侵害あるいは破壊行為を引き起こす集団である。
 いまも世界中で、誘拐されている人間は数万人いるというショッキングな情報からこの本ははじまる。
いまも世界中で、誘拐されている人間は数万人いるというショッキングな情報からこの本ははじまる。 昭和が終わり、平成というどこまでもなだらかだが、確実にかたむいいて行く時代を迎え、その年の夏、永遠の29歳が逮捕された。
昭和が終わり、平成というどこまでもなだらかだが、確実にかたむいいて行く時代を迎え、その年の夏、永遠の29歳が逮捕された。 かつて、東京論が流行ったころ、いくつもの書物が出版され、わたしも嫌いじゃない分野なので読み漁ったけど、いまも残っているひとは、別の研究フィールドを確固として持っていたひとだけだな、と改めて思う。その中で海野弘は、ふらふらとさまよい続けている感がある。1920年代のアール・ヌーヴォ、ワイマール時代、ニューヨークなどなど色々発掘はしてくるのだけど、
目端の利く連中にパクラレルコト数限りなし。そのひとつには、文章が平易すぎて(これは誉め言葉だよ)、誰でもアクセスできるネタを使い、突っ込みが足りない。文章の魅力に欠けるってことだろうか。
かつて、東京論が流行ったころ、いくつもの書物が出版され、わたしも嫌いじゃない分野なので読み漁ったけど、いまも残っているひとは、別の研究フィールドを確固として持っていたひとだけだな、と改めて思う。その中で海野弘は、ふらふらとさまよい続けている感がある。1920年代のアール・ヌーヴォ、ワイマール時代、ニューヨークなどなど色々発掘はしてくるのだけど、
目端の利く連中にパクラレルコト数限りなし。そのひとつには、文章が平易すぎて(これは誉め言葉だよ)、誰でもアクセスできるネタを使い、突っ込みが足りない。文章の魅力に欠けるってことだろうか。 シリーズ第二作では、ハリウッドを取り上げている。ここにあるハリウッドは、どちらかというと、ケネス・アンガーの「ハリウッド・バビロン」に近い。ただ、ゴッシップというよりは、アウトサイダーの視点に重きを置いたため、いくつかのハリウッドを描いた小説「ラスト・タイクーン」、「いなごの日」などからの引用があり、いまひとつ面白みに欠ける。ネタとしてもギャングとハリウッド、赤狩りなどいまひとつ新鮮味がすくないが、いままで知らなかったネタは少しはあると思う。
シリーズ第二作では、ハリウッドを取り上げている。ここにあるハリウッドは、どちらかというと、ケネス・アンガーの「ハリウッド・バビロン」に近い。ただ、ゴッシップというよりは、アウトサイダーの視点に重きを置いたため、いくつかのハリウッドを描いた小説「ラスト・タイクーン」、「いなごの日」などからの引用があり、いまひとつ面白みに欠ける。ネタとしてもギャングとハリウッド、赤狩りなどいまひとつ新鮮味がすくないが、いままで知らなかったネタは少しはあると思う。 第3作目に来てようやく、本シリーズが見えてきた。著者はたぶんこれがやりたかったのだと思う。非常にノッテイルのがわかる。スポーツ用品の始祖スポルディング氏の晩年、カルフォルニアの神秘宗教家に入れ揚げる様子から本書は始まる。
カルフォルニアは神秘主義と相性が良いことが語られる。ヨーロッパで受け入れられない教えが、流れ流れてここにたどり着くのだと。また、インディアンをはじめとして、
様々な聖地であることも指摘される。その流れと、温泉(保養所とSPA)があり、癒しを求める人々が集う場所としても有名であることが開かされる。
第3作目に来てようやく、本シリーズが見えてきた。著者はたぶんこれがやりたかったのだと思う。非常にノッテイルのがわかる。スポーツ用品の始祖スポルディング氏の晩年、カルフォルニアの神秘宗教家に入れ揚げる様子から本書は始まる。
カルフォルニアは神秘主義と相性が良いことが語られる。ヨーロッパで受け入れられない教えが、流れ流れてここにたどり着くのだと。また、インディアンをはじめとして、
様々な聖地であることも指摘される。その流れと、温泉(保養所とSPA)があり、癒しを求める人々が集う場所としても有名であることが開かされる。 昨今のスポーツジャーナリズムのつまらなさは、記事および取材の底の浅さに、選手が飽きるとともに、提灯記事を書きながら選手に近づき
独占的な取材をしていく癒着型ジャーナリズムの横溢にある。 だれとは書かないがあまりに多過ぎる。それでなければ、数字の羅列により、その選手を追いかける分析型だ。
昨今のスポーツジャーナリズムのつまらなさは、記事および取材の底の浅さに、選手が飽きるとともに、提灯記事を書きながら選手に近づき
独占的な取材をしていく癒着型ジャーナリズムの横溢にある。 だれとは書かないがあまりに多過ぎる。それでなければ、数字の羅列により、その選手を追いかける分析型だ。 タブロイド紙のように、スキャンダラスで、卑俗な謎のメディア王の姿が描かれてる。さすが、マードック非公認伝記だ。
80年代なにが世界のマスメディアで起こっていたかを知るには格好の一冊だ。 あとCNN世界を変えたニュースネットワークを読めば良い。
タブロイド紙のように、スキャンダラスで、卑俗な謎のメディア王の姿が描かれてる。さすが、マードック非公認伝記だ。
80年代なにが世界のマスメディアで起こっていたかを知るには格好の一冊だ。 あとCNN世界を変えたニュースネットワークを読めば良い。 著者は、これらを対として構想していたという。佐高は石原莞爾と同郷、山形の出身である。いまも語られる「石原莞爾伝説」に、日本人の勝手な歴史観を見ていらだつ。伝説曰く「石原さん東条英機にはめられ失脚した。石原の掲げた五族協和の理想や日米が戦う世界最終戦争の予言は外れていなかった」ゆえに石原は従来の日本人のスケールを越えた人物だったと。
著者は、これらを対として構想していたという。佐高は石原莞爾と同郷、山形の出身である。いまも語られる「石原莞爾伝説」に、日本人の勝手な歴史観を見ていらだつ。伝説曰く「石原さん東条英機にはめられ失脚した。石原の掲げた五族協和の理想や日米が戦う世界最終戦争の予言は外れていなかった」ゆえに石原は従来の日本人のスケールを越えた人物だったと。 ナチスドイツによるユダヤ人虐殺いわゆるホロコーストだけど、殺したユダヤ人の皮膚から石鹸を作ったという話は嘘だって知ってた?実は、
ユダヤ人絶滅の公式文書や、虐殺の証拠写真が一枚もないことを知っていましたか。ガス室と呼ばれるところからなにもその証拠が検出されていないことは?ほんとうにホロコーストはあったのか…。
ナチスドイツによるユダヤ人虐殺いわゆるホロコーストだけど、殺したユダヤ人の皮膚から石鹸を作ったという話は嘘だって知ってた?実は、
ユダヤ人絶滅の公式文書や、虐殺の証拠写真が一枚もないことを知っていましたか。ガス室と呼ばれるところからなにもその証拠が検出されていないことは?ほんとうにホロコーストはあったのか…。 「洗脳」は、Brain washの直訳で、朝鮮戦争で中国の捕虜となったアメリカ兵が、共産思想を植え付けられて帰ってきたことから、一般的になったのだけど、この実験を
国家レベルで民間人を実験台にしていたという内容が本書だ。
「洗脳」は、Brain washの直訳で、朝鮮戦争で中国の捕虜となったアメリカ兵が、共産思想を植え付けられて帰ってきたことから、一般的になったのだけど、この実験を
国家レベルで民間人を実験台にしていたという内容が本書だ。 山形浩生による桃尻語訳のMIT経済学部教授の経済入門書だ。あまりにあまりに啓蒙的におもしろく刺激的である本書は、入門書はかくあるべきとの見本のような本だ。本書を読んだ後には、この本を基準として大学教授の書いたものを判断しよう。知的ということとおもしろいということとわかりやすいということは矛盾しないことがわかるだろう。そんなものを書けない学者はダメだね。
山形浩生による桃尻語訳のMIT経済学部教授の経済入門書だ。あまりにあまりに啓蒙的におもしろく刺激的である本書は、入門書はかくあるべきとの見本のような本だ。本書を読んだ後には、この本を基準として大学教授の書いたものを判断しよう。知的ということとおもしろいということとわかりやすいということは矛盾しないことがわかるだろう。そんなものを書けない学者はダメだね。 沖縄をめぐるルポルタージュが増補新版!になるほど売れることはない。実は毀誉褒貶問題で大問題になり、削除、訂正加筆の結果なのだ。
沖縄をめぐるルポルタージュが増補新版!になるほど売れることはない。実は毀誉褒貶問題で大問題になり、削除、訂正加筆の結果なのだ。 冒頭で、雑誌「宝島30」に掲載した、「ビートたけし論」がいまも一人歩きしてたけしが困っているらしいと聞いて、呵々と笑う作者の姿が描かれている。作者にしてみれば、「そーんなこともわからねえで、取材受けてたのかょ」、あるいは「なんで、次の別の論がいつまでも出てこねえのかねえ」だろう。
冒頭で、雑誌「宝島30」に掲載した、「ビートたけし論」がいまも一人歩きしてたけしが困っているらしいと聞いて、呵々と笑う作者の姿が描かれている。作者にしてみれば、「そーんなこともわからねえで、取材受けてたのかょ」、あるいは「なんで、次の別の論がいつまでも出てこねえのかねえ」だろう。 岡山という土地を縦断していくと、山の合間に黒色の屋根瓦の屋並みが続き、横溝正史の世界に近づく、そしてあきらかに空気が変わる地点がある。瀬戸内の開けた空気が、陰鬱な山の空気に変化する地点がある。そこでは美しい黒々として緑の森が続く中、鳥の声もしない森閑とした世界がひとを包む。岡山の山間がこの作品の背景にはある。
岡山という土地を縦断していくと、山の合間に黒色の屋根瓦の屋並みが続き、横溝正史の世界に近づく、そしてあきらかに空気が変わる地点がある。瀬戸内の開けた空気が、陰鬱な山の空気に変化する地点がある。そこでは美しい黒々として緑の森が続く中、鳥の声もしない森閑とした世界がひとを包む。岡山の山間がこの作品の背景にはある。 大体、本の収集家なんて人種にまともな奴がいるはずがない。作者の古書探偵シリーズを読めばそれがわかる。今回は多摩ニュータウンに新設された大学図書館で起きる殺人事件だ。ここでも本に魅入られすべての失って行く人間たちが描かれる。滑稽でありながら容赦のない人物の造型は作者の世界の特徴だろう。北村薫とそれほど世界は変わらないのにこの落差はなんなのかと思った次第です。
大体、本の収集家なんて人種にまともな奴がいるはずがない。作者の古書探偵シリーズを読めばそれがわかる。今回は多摩ニュータウンに新設された大学図書館で起きる殺人事件だ。ここでも本に魅入られすべての失って行く人間たちが描かれる。滑稽でありながら容赦のない人物の造型は作者の世界の特徴だろう。北村薫とそれほど世界は変わらないのにこの落差はなんなのかと思った次第です。 探偵小説の欺瞞とジレンマは、「なぜ探偵は殺人犯人の行動を最後まで止めることができないのか」ということだ。なぜなら、途中で犯人を捕まえてしまうと物語がおわってしまう。では殺人を止められないのに名探偵と呼ばれるのは矛盾していないか。それじゃ探偵小説自体を否定する結果となってしまう。
探偵小説の欺瞞とジレンマは、「なぜ探偵は殺人犯人の行動を最後まで止めることができないのか」ということだ。なぜなら、途中で犯人を捕まえてしまうと物語がおわってしまう。では殺人を止められないのに名探偵と呼ばれるのは矛盾していないか。それじゃ探偵小説自体を否定する結果となってしまう。 どちらかというと、ウエストレイク名義なのかは大いに疑問があるところだけども、敢えて言うなら、初期の「雇われた男」などの、辛い読後感のある作品にテイストは近い。そこに作家としての語り口の充実さを加えたところに、ほかのブロック・バスターの作家なら上下巻にしてしまうのをさらりと書き連ねる余裕を感じさせる。
どちらかというと、ウエストレイク名義なのかは大いに疑問があるところだけども、敢えて言うなら、初期の「雇われた男」などの、辛い読後感のある作品にテイストは近い。そこに作家としての語り口の充実さを加えたところに、ほかのブロック・バスターの作家なら上下巻にしてしまうのをさらりと書き連ねる余裕を感じさせる。 これは作者のクロニクルでいうと、「血と骨」の中盤で、東京に逃げた長男が、「タクシー狂騒曲」の舞台を、事故で去ったあとの事件である。
これは作者のクロニクルでいうと、「血と骨」の中盤で、東京に逃げた長男が、「タクシー狂騒曲」の舞台を、事故で去ったあとの事件である。 最後の一行を読む。しばらく絶句したあとに、うーんと唸る。前の文章を読み、さらに前の章に戻り、舌打ちをしながら、その前の短編を読みなおし、パラパラとページをめくり一番最初に戻りためいきをつきながら、表紙の裏カバーを剥がし、じっと見てから地団駄を踏む。まただ、また泡坂妻夫のマジックに見事にやられてしまった。
最後の一行を読む。しばらく絶句したあとに、うーんと唸る。前の文章を読み、さらに前の章に戻り、舌打ちをしながら、その前の短編を読みなおし、パラパラとページをめくり一番最初に戻りためいきをつきながら、表紙の裏カバーを剥がし、じっと見てから地団駄を踏む。まただ、また泡坂妻夫のマジックに見事にやられてしまった。 あいかわらずのの狂暴さはわかりにくく、どこにも組しない孤高あるいは孤独さを巻き散らしている点では、かれの評論集
「ソドムの映画市」の続編ともいえよう。その語り口は鬱屈を評論という形にこだわらず、不機嫌なまでのつぶやきに変えながら唐突に枚数になったから投げ出すように終わる。
あいかわらずのの狂暴さはわかりにくく、どこにも組しない孤高あるいは孤独さを巻き散らしている点では、かれの評論集
「ソドムの映画市」の続編ともいえよう。その語り口は鬱屈を評論という形にこだわらず、不機嫌なまでのつぶやきに変えながら唐突に枚数になったから投げ出すように終わる。 「ファイトクラブ」でそのヴィジュアルイメージの強烈さを読者に印象付け、ここ数年で図抜けた才能を見せてくれた
感のある作者が前作以上の、巧緻さで塗り上げたありとあらゆるFUCKOFFな文学に向けた挑戦状である。これを受け取るか受け取らないかはあなたの自由だが、
これを読まずして、今後の文学を語ることは無意味だと断言しておこう。
「ファイトクラブ」でそのヴィジュアルイメージの強烈さを読者に印象付け、ここ数年で図抜けた才能を見せてくれた
感のある作者が前作以上の、巧緻さで塗り上げたありとあらゆるFUCKOFFな文学に向けた挑戦状である。これを受け取るか受け取らないかはあなたの自由だが、
これを読まずして、今後の文学を語ることは無意味だと断言しておこう。 いつも思うんだけど、村上龍の小説っていつも宣伝文句以上であった試しがないんじゃないか。 キャッチコピーに書かれていることはないのね。今回は確か、「2002年、全国の中学生が日本を後にする」みたいなものだと思ったけど、まさにそれ以外のこと書いてないんだよ。それは小説として破綻がないということでもあるし、尻つぼみと言ったほうが正解かもしれない。大風呂敷をひろげたは良いけど閉じられなくなる、しかしこのまま突っ走ったら、批判を受けるので自爆装置を作動させる。いつもこのパターンだ。でなければ、だらだらとした連作小説体となる。
いつも思うんだけど、村上龍の小説っていつも宣伝文句以上であった試しがないんじゃないか。 キャッチコピーに書かれていることはないのね。今回は確か、「2002年、全国の中学生が日本を後にする」みたいなものだと思ったけど、まさにそれ以外のこと書いてないんだよ。それは小説として破綻がないということでもあるし、尻つぼみと言ったほうが正解かもしれない。大風呂敷をひろげたは良いけど閉じられなくなる、しかしこのまま突っ走ったら、批判を受けるので自爆装置を作動させる。いつもこのパターンだ。でなければ、だらだらとした連作小説体となる。 シリーズ第二作。イギリス情報部黎明期、第一次世界大戦前の欧州情勢をめぐる権謀術数、今回の目玉は飛行機とイタリアである。飛行機好きのライアルとしては本領発揮だ。まだ海のものとも山のものともわからない新兵器をどう料理するのか見もの。
シリーズ第二作。イギリス情報部黎明期、第一次世界大戦前の欧州情勢をめぐる権謀術数、今回の目玉は飛行機とイタリアである。飛行機好きのライアルとしては本領発揮だ。まだ海のものとも山のものともわからない新兵器をどう料理するのか見もの。 いつも水準点を越える出来なので安心して読める少ないシリーズとして重宝しています。登場人物が自分たちとともに歳を取って行くのは続き物ミステリーのひとつの特権とも言えます
(まあ、そういうのを拒否するミステリー通連中もいるけど) 。
いつも水準点を越える出来なので安心して読める少ないシリーズとして重宝しています。登場人物が自分たちとともに歳を取って行くのは続き物ミステリーのひとつの特権とも言えます
(まあ、そういうのを拒否するミステリー通連中もいるけど) 。 「アームチェアー・ディティクティブ」という探偵小説の分野があり、非常に古典的なものだが、成功しているものは少ない。なぜかというと、パズル型犯人当てミステリーでは、絶対的なんでも当てる探偵「デウス・エキス・マテナ」(全能神)の存在が不可欠なのだが、この時代そんな人間がリアリティを持つはず無いし、いわば証拠隠匿にならざるを得ない。
「アームチェアー・ディティクティブ」という探偵小説の分野があり、非常に古典的なものだが、成功しているものは少ない。なぜかというと、パズル型犯人当てミステリーでは、絶対的なんでも当てる探偵「デウス・エキス・マテナ」(全能神)の存在が不可欠なのだが、この時代そんな人間がリアリティを持つはず無いし、いわば証拠隠匿にならざるを得ない。 『レクイエム・フォー・ドリームス』として映画化されたので、期待半分で読んでみたけど、すでに出てからかなり経っている事に気づいた
。典型的な80年代のドラッグがらみで壊れて行くニューヨークの若者たち を描いた、そのまんまの内容であった。いまとなっては、だらだらの地と会話とモノローグを分けない書き方ももう懐かしい感じだ(スティーブン・エリクソンとかね)。
『レクイエム・フォー・ドリームス』として映画化されたので、期待半分で読んでみたけど、すでに出てからかなり経っている事に気づいた
。典型的な80年代のドラッグがらみで壊れて行くニューヨークの若者たち を描いた、そのまんまの内容であった。いまとなっては、だらだらの地と会話とモノローグを分けない書き方ももう懐かしい感じだ(スティーブン・エリクソンとかね)。 スティーブン・キングにはしばらく愛想を尽かしていた。「IT」以降、あのシャベリ文体が翻訳のせいだけじゃなくホント鼻についていたのだ。それが、「ローズ・マーダー」など、異常者の脳みそに入り込んだような文章がのた打ち回っているのをながめているうちに読む気がなくなってしまうのであった。「グリーン・マイル」は制約があったせいか、以前のキング節が復活していた。
スティーブン・キングにはしばらく愛想を尽かしていた。「IT」以降、あのシャベリ文体が翻訳のせいだけじゃなくホント鼻についていたのだ。それが、「ローズ・マーダー」など、異常者の脳みそに入り込んだような文章がのた打ち回っているのをながめているうちに読む気がなくなってしまうのであった。「グリーン・マイル」は制約があったせいか、以前のキング節が復活していた。
 「雑貨屋のドストエフスキー」と呼ばれ、ようやく再評価され出した、ジム・トンプスン。この小説、実は読むのにというか、読み始めるのに異常に時間がかかった。なぜか。こんな文章を小説として読んだことが無いからだ。主人公の目を通してみた田舎街の描写、これがなんか変だ。アタマが悪い人間がスローモーションのようにふわふわと歩いている、そんな印象なのだ。
「雑貨屋のドストエフスキー」と呼ばれ、ようやく再評価され出した、ジム・トンプスン。この小説、実は読むのにというか、読み始めるのに異常に時間がかかった。なぜか。こんな文章を小説として読んだことが無いからだ。主人公の目を通してみた田舎街の描写、これがなんか変だ。アタマが悪い人間がスローモーションのようにふわふわと歩いている、そんな印象なのだ。 ひとの中にある邪悪な本質を識るのに、「罪と罰」のような三文メロドラマを読む必要は無い。ジム・トンプスンがあればいい。ここには、
ロシアの文豪もたどり着けなかった地点が凝縮されて描かれている。 ハードボイルドの始祖としてのダシール・ハメットも結局は19世紀の人間であって、小説に浪漫主義的な理想部分をどこか捨てきれないでいたと思う。
ひとの中にある邪悪な本質を識るのに、「罪と罰」のような三文メロドラマを読む必要は無い。ジム・トンプスンがあればいい。ここには、
ロシアの文豪もたどり着けなかった地点が凝縮されて描かれている。 ハードボイルドの始祖としてのダシール・ハメットも結局は19世紀の人間であって、小説に浪漫主義的な理想部分をどこか捨てきれないでいたと思う。 町田町蔵の軽薄重調文章は好きだ。やるせないほど駄目男も良い。だけど、アラーキーとのコラボレーションはちょっと企画としては面白いけど、結果お互いに、自分のテリトリーを守りつつ、この辺で手打ちにするかのような、
中途半端な心地良さを目指してしまったために、刺激的な読み物には程遠い出来となった。
町田町蔵の軽薄重調文章は好きだ。やるせないほど駄目男も良い。だけど、アラーキーとのコラボレーションはちょっと企画としては面白いけど、結果お互いに、自分のテリトリーを守りつつ、この辺で手打ちにするかのような、
中途半端な心地良さを目指してしまったために、刺激的な読み物には程遠い出来となった。 こういうだらだらとした本をだすのがいいかは別として、売れるためなら何でもやる新潮社の姿勢に脱帽。
こういうだらだらとした本をだすのがいいかは別として、売れるためなら何でもやる新潮社の姿勢に脱帽。  宮崎学はたくさん書きすぎて、読み終わったら忘れてしまうものも多いけど、作者自身が金のためとそうでないものを分けているので読者としても心構えができる。
わたしは彼を梶山季之、藤原審爾、竹中労の系列に置きたい。実践的文学ルポルタージュとでも呼ぼうか。前者三人もほとんどいまは忘れられているし、本も手に入りにくい。わたしは彼らを忘れてはならないと考える。いずれも汎的視点を持つ人たちだった。
宮崎学はたくさん書きすぎて、読み終わったら忘れてしまうものも多いけど、作者自身が金のためとそうでないものを分けているので読者としても心構えができる。
わたしは彼を梶山季之、藤原審爾、竹中労の系列に置きたい。実践的文学ルポルタージュとでも呼ぼうか。前者三人もほとんどいまは忘れられているし、本も手に入りにくい。わたしは彼らを忘れてはならないと考える。いずれも汎的視点を持つ人たちだった。