映画本 2003
脚本(シナリオ)通りにはいかない! 君塚良一:キネマ旬報社:1900円
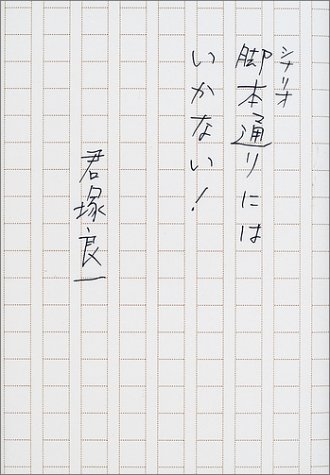 映画が好きでシナリオに興味がある、書きたいけどちゃんとベンキョーせんといけないんだろうなぁと怯んでいる人には最適です。
映画が好きでシナリオに興味がある、書きたいけどちゃんとベンキョーせんといけないんだろうなぁと怯んでいる人には最適です。
君塚良一は萩本欽一の弟子でドラマの人についた訳ではなく、欽ちゃんに「なんでも好きなことをしなさい」と言われひたすら映画ばかりものすごい数を観ていたというのは伝説だ。
彼は、いままでのシナリオライターの金科玉条のテーマ主義、文学趣味をやんわりと退けて、徹底的に記号的な、あるいはハリウッド的なひたすら快楽的に観客がこう観られたらおもしろいはずだという視点からシナリオを書く。
そんな彼独自のシナリオの発想方法とシナリオライターとしての映画の見方をじっくりと解説してくれる好書。
連載時の順番を再構成し、分かりやすくシナリオ論としても通用するように書き直しています。その時々の映画ばかりでなく、自分映画史からも出してきて(『野獣狩り』『約束』『静かなる決闘』『フランケンシュタイン対地底怪獣』『県警対組織暴力』『ピンクサロン 好色五人女』『鉄砲玉の美学』)、なるほどねと思わせる部分が多いです。また講演スタイルのシナリオ創作教室はあらこんなに気軽に考えていいのかしらんと目からウロコで必読。
割り切った視点と発想が君塚シナリオの魅力だと思うんだけどね。私自身は完成度よりは、パクリばかりのドラマの中で、孤独に実験的なシナリオを出してくるところが好きですね。それでいながら商業的なスタイル(泣かせどころ)も踏まえている。まあ彼が言っているほど、映画やドラマのシナリオが成功しているかを読み手がどう評価するかどうかなのではありますが…。
ハワード・ホークス―ハリウッド伝説に生きる偉大な監督 トッド・マッカーシー:キネマ旬報社:6500円
 映画といえばハリウッド映画、なんでも楽しく観ていたのに、ある日ハワード・ホークスの名前を知ってからは、監督によってこれほど映画のおもしろさが違うことに気付き、以前と同じように喜んで観ることができなくなった貴方にはぜひ読んでもらいたいです。
映画といえばハリウッド映画、なんでも楽しく観ていたのに、ある日ハワード・ホークスの名前を知ってからは、監督によってこれほど映画のおもしろさが違うことに気付き、以前と同じように喜んで観ることができなくなった貴方にはぜひ読んでもらいたいです。
作家主義からも距離を置き、監督のホラ話にもまゆつばを付けながら、資料にあたりその実像に探りをいれた労作です。ホークスという人物は性格の歪みとか政治信条に右寄りな偏りとかはあるが、それが作品にどう影響したというような安易な分析はしていない。
興業成績、撮影所のプロデューサーやエージェント、同業者の監督との関係。システムがすべての夢の工場のなかでいかにしてサバイバルをしてきたか。特定の撮影所には属さずメジャーはすべて渡り歩いている特異な経歴。
セックスを暗示する大胆な表現での検閲との闘い(時代の先をいっていたと言うこと)、予算超過との闘い(必ず撮影日数が予定の倍はかかっているスローペース)。それらを伝説と事実を分けて、彼の実像である孤独なハリウッドの洒落者を浮き上がらせている。
驚くべきは、ホークスはそれほど語るストーリーのバリエーションを持っていなかったという指摘だ。「危険な仕事に就くふたりの男が同じ女を取り合い、最後には片方が死ぬか、譲ることで終わる」。これを生涯繰り返していたというのだ。『リオ・ブラボー』三部作が同じというのは有名な話だけど、観客はそれに気付かないあるいは気にしなかった。なぜか?ひとつひとつのエピソードが面白く、演出が良いからだ。逆に言えば、ストーリー・ラインが浮かび上がるような、テーマが見て取れるような構造にはなっていないのからだ。
関連して興味深い指摘は、ある意味集大成であった『リオ・ブラボー』の出演者はジョン・ウェイン以外は、ウォルター・ブレナンを含む全員が当時のテレビドラマの人気者だったということだ。もちろんホークスはそれを承知でキャスティングをしている。
それで思い出したのは、『リオ・ブラボー』をはじめて映画館で観たとき「こんなに長い作品だったんだ」と気づき、テレビで観ても実は印象がそれほど変わらないことだった。ということはエピソードがいくつかカットされてもストーリーにはなんの影響が無いと言うことだ。その意味ではホークスの話法はテレビドラマに似て、エピソードの積み重ねや寄り道でキャラクターをふくらませて楽しませていくもので、だからキャスティングが弱いと作品自体がつまらなくみえてしまうことがあるのだろう。
その他にも、そのキャリアを自らが出資してプロデューサーからはじめるという金持ちならではの掟破りなやり方だったり、ホークスを映画業界に招き、彼が監督の姿としてマネをしたのがビクター・フレミング(かれも大学出のレーサー)だったというのには驚いた。
また男性的で明るい映画しか撮らない印象があるが、実はヘミングウェイと同じ「失われた世代」ひきずっていて、モノクロ時代はやたら登場人物が自殺していたりする。第二の妻のスリムが離婚した後にNYの社交界に入り、トルーマン・カポティの短編「ラ・コート・バスク」で悪く書かれていたというのも発見。
なにはともあれ、そのキャリアで何度も頂点に立ち傑作を作ったことは間違いはない。そのような映画監督はいないのだから。またその製作者としての嗅覚で観客の嗜好を嗅ぎ分けたのも確かだ。いまはスピルバーグがまったくホークスの真似をしているのはご愛嬌か、それともハリウッドの伝統なのか。高橋千尋の監訳なので安心して読めます。
マジック・アワー ジャック・カーディフ:愛育社:2800円
 イギリスの撮影監督および監督であるジャック・カーディフのフィルモグラフィーは謎だらけだった。技巧の極致のマイケル・パウエルの『赤い靴』を撮ったと思うと、ジャングルロケの『アフリカの女王』リチャード・フライシャーと組んだと思うと、監督としてマリアンヌ・フェイスフル主演の『あの胸にもう一度』とかB級作品を作っていたりする。その謎が本書を読むとほとんど明かされる。
イギリスの撮影監督および監督であるジャック・カーディフのフィルモグラフィーは謎だらけだった。技巧の極致のマイケル・パウエルの『赤い靴』を撮ったと思うと、ジャングルロケの『アフリカの女王』リチャード・フライシャーと組んだと思うと、監督としてマリアンヌ・フェイスフル主演の『あの胸にもう一度』とかB級作品を作っていたりする。その謎が本書を読むとほとんど明かされる。
サイレント時代からキャリアがはじまり、テクニカラー・キャメラの名手として名を馳せるようになる。そこでのエピソードにハリウッドとは違うヨーロッパの映画界が垣間見える。
また彼が会った女優たちのポートレイトも素晴らしい。マレーネ・ディートリヒ、エヴァ・ガードナー、特にマリリン・モンロー!ほかにも出会った俳優、画家、監督たちのエピソードもイギリス人らしいユーモアを含んで読ませる。訳文がちょっとピント外れなところもある。あと三色分解のテクニカラー・キャメラについて解説があっても良かった。
サム・ペキンパーガーナー・シモンズ:河出書房新社:3800円
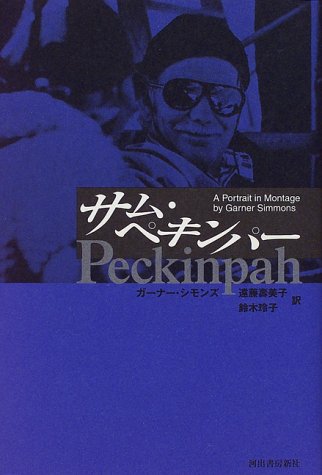 実は原書を持っているのだけど、読まないうちに邦訳が出てしまった。一本一本の映画に沿って、離れた視点から書いているので滅茶苦茶な人だった神話度は低いが、ペキンパーの粘着質で疑り深い性格がよくわかる。
実は原書を持っているのだけど、読まないうちに邦訳が出てしまった。一本一本の映画に沿って、離れた視点から書いているので滅茶苦茶な人だった神話度は低いが、ペキンパーの粘着質で疑り深い性格がよくわかる。
作品の予算超過にしても、結局は逆説的にハリウッド・スタイルのやり方でしか映画を撮れない人、その意味ではまさにオールド・ハリウッド、または滅び行く西部の男を実践していたことがわかる。
作品が完成して上映される前に興業成績に対して自信を失い、急いで次の作品の契約をしたがり、結果として自分を弱い立場に置いてしまう悪循環の繰り返すという部分があることも意外だった。『キラー・エリート』はアクション映画のパロディとしたと言ってもあの鈍さ加減ではねえ。
読めもしない原書を買ったのは、本書358ページにも載っている写真が好きだったからです。
剣 三隅研次の妖艶なる映像美 野沢一馬:四谷ラウンド:1800円
 客観的な伝記ではなく読み物仕立てになっているのですが、それほど気にならなかったのは三隅研次についてあまり知識が無いからでしょうか。
客観的な伝記ではなく読み物仕立てになっているのですが、それほど気にならなかったのは三隅研次についてあまり知識が無いからでしょうか。
彼の経歴で衣笠貞之助の専属助監督が長かったというのも驚いたし、血しぶきをやたら上げる作風になったのも勝プロの時代からであり、その一作目の『子連れ狼 子を貸し腕貸しつかまつる』の撮影中に大映倒産の報が入ったというドラマも劇的だ。
角川映画第一作になったかもしれない『オイディプスの刃』を監督するはずだったというハナシや、『斬る』のアタマのシーンを新藤兼人のシナリオとできた映画を較べ、その解釈というか創造力を解読するところなど圧巻です。
またカラー、70mmと技術にものすごいカネを掛けまくった大映という会社についてもわかって興味深い。
将軍と呼ばれた男 映画監督山下耕作 山下耕作 円尾敏郎:ワイズ出版:2800円
 山下耕作の最後の聞き語りが大半をしめるのだが、この作業の途中で逝去したためなのか、テープ起こしのまま編集されたみたいで、話がポンポン飛んでいて読みづらい。まあそういう記録というのならそれでも良いのかも知れないが。資料的な価値が下がってしまうのではないかなあ。かなりの人を一方的に罵倒しているしね。
山下耕作の最後の聞き語りが大半をしめるのだが、この作業の途中で逝去したためなのか、テープ起こしのまま編集されたみたいで、話がポンポン飛んでいて読みづらい。まあそういう記録というのならそれでも良いのかも知れないが。資料的な価値が下がってしまうのではないかなあ。かなりの人を一方的に罵倒しているしね。
ひまわりとキャメラ
撮影監督・岡崎宏三一代記 石渡均編:三一書房:3500円
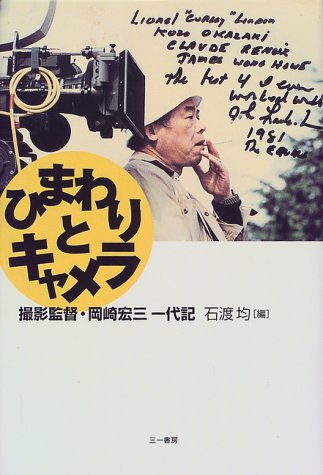 ジョゼフ・フォン・スタンバーグの遺作の『アナタハン』をはじめ、『ザ・ヤクザ』などの海外スタッフや、川島雄三、豊田四郎、小林正樹、木下恵介と組んできて、いまも現役の大正8年生まれのキャメラマン。
ジョゼフ・フォン・スタンバーグの遺作の『アナタハン』をはじめ、『ザ・ヤクザ』などの海外スタッフや、川島雄三、豊田四郎、小林正樹、木下恵介と組んできて、いまも現役の大正8年生まれのキャメラマン。
エピソードのおもしろさもあるが、彼の個人史の前にそれぞれの時代背景の説明があるていねいな作りなのでわかりやすい。また「キャメラマンとルックの変遷」では撮影監督というものがどういうものかもわかります。
デジタル映画撮影術 ポール・ウェラー:
フィルムアート社:2800円
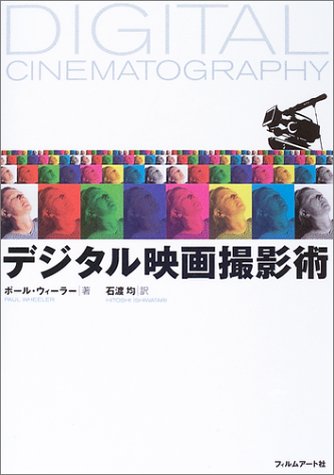 まず題名に異議あり!ここに書かれているのは、プロ用のソニー、デジタル・ベータカム・カメラについてのノウハウであって、デジタル・シネマ・カメラについてではない。両者がどう違うかは端的にいうと、前者はテレビでは高品質な画面を作り出すのには使えるが、後者のように映画フィルムの代わりになるような品質のものではないということだ。(まあ使い分けが一慨にそうも言えないのが苦しいが… 例)『木更津キャッツアイ日本シリーズ』>ありゃ、アナログのベータカム(ようするに普通のテレビカメラ)だけどなあ>商品以前のハナシだろうが!)
まず題名に異議あり!ここに書かれているのは、プロ用のソニー、デジタル・ベータカム・カメラについてのノウハウであって、デジタル・シネマ・カメラについてではない。両者がどう違うかは端的にいうと、前者はテレビでは高品質な画面を作り出すのには使えるが、後者のように映画フィルムの代わりになるような品質のものではないということだ。(まあ使い分けが一慨にそうも言えないのが苦しいが… 例)『木更津キャッツアイ日本シリーズ』>ありゃ、アナログのベータカム(ようするに普通のテレビカメラ)だけどなあ>商品以前のハナシだろうが!)
しかし、著者のBBCで長年ドラマ、ドキュメンタリーのビデオ撮影をして映画キャメラも使えるので両者の長所がわかっている。具体的な使用法だけではなく、美学的な照明、色、光、電気工学部分をも含め、貴重な事例がたくさん載っている。註訳もわかりやすい。
どういう人向けかというと、専門学校等で撮影を勉強中または撮影助手をはじめましたという人にはお薦めです。そうでなくとも基本的な部分は参考になります。デジタルヴィデオに興味のある方には、映画、ビデオの技術ブックと併読すると世界が広がります。でもさamazon.comなどみてもアメリカでの類書がたくさんあるけどなぜイギリスなのかねえ?
監督中毒 三池崇史:ぴあ:1600円
 この本を読んでも彼の映画作法は少しも解明されない、映画界に入る前の生い立ちや私生活についてもまったく触れられていないので、その方面から映画を解釈する方々には資料としての価値はありません。
この本を読んでも彼の映画作法は少しも解明されない、映画界に入る前の生い立ちや私生活についてもまったく触れられていないので、その方面から映画を解釈する方々には資料としての価値はありません。
ただ彼が一緒に仕事をしてきた映画人たちへの、愛憎が入り交じった視線の延長に三池作品があるのはよくわかる。彼が冷静な観察者だったと言っているのではない、そういう時代だったということだ。フィルム撮りの1時間テレビドラマや2時間サスペンス、Vシネから、劇場用作品を作ったことのあるベテラン映画監督たちが排除されていく最後の時代であり、最後の徒弟制度の体育会系が通用した時代。ちょうど浮かれバブルの終わりであり、何一つ新しくないトレンディ・ドラマという言葉が出てきた時代に、いろんなものを見てきたのだと思う。
テレビに乗れない監督たちやだれがどう撮っても変わらない連続ドラマ。それが良いとか悪いとかじゃない、仕上げなければ放映に間に合わないし、そういう仕事なのだから。ただ秘かにそれだけじゃダメでもっとやり方はあるはずだとは助監督として感じているだろうが。
三池はセカンド助監督としてものすごく優秀だったんじゃなかろうか。本人もそのポジションが心地良かったと思う。遊軍的な位置であり、製作における裁量も大きく、言い換えれば制作部としてのチカラも必要とされる。チーフ助監督のスケジューリングや監督の補助という仕事から逃れて、純粋に現場と立ち向かうことができる、それも長年やっていればいるほど手練れになっていく。
ある意味、三池の監督のやり方はセカンド助監督のフットワークの軽さで撮影を進めているとは考えられないだろうか。時間がなければどんどん撮影方法や、間に合わない小道具は映らないようにするし、現場で面白いと思ったことはどんどん変更していくやり方。それでいてどこまで冒険できるかを見極める眼。いつもそのぎりぎりのところを試しているように思える。自分が映画を作っているんじゃなくて、ただ自分は映画の現場で撮影を進めているだけだ。それがうまく行けば面白くなることもあるんじゃないのというスタンス。それは「自分が創造主であり、作家でありたい」という概念からは明らかにもっとも遠いところにいる。それを理解しない限りあらゆる評論は空を切ると思う。『牛頭』はそんな遊軍的スタンスの傑作だけど、反面そこまでやるとオモシロがるところはもう無いねという限界も一応は見えてきたのではないだろうか。次はプロデューサーとしての仕掛けを入れてくるのか、それともシナリオをもっと引きつけて撮るのか、どちらせよ、楽しみだなあ。『着信あり』と『ゼブラーマン』。
エクスプローリング・ザ・マトリックス カレン・ヘイバー編:小学館プロダクション:1800円
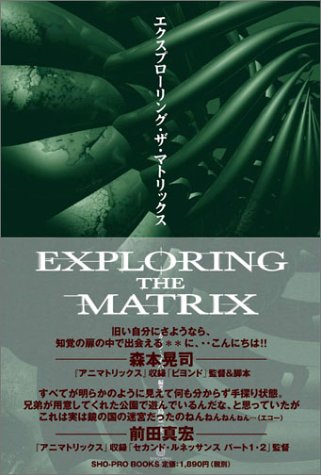 『マトリックス』についてSF作家やSF関係者が語る評論本。『マトリックス・リローデッド』の前に書かれていたようので、続編についての言及はなく絶賛の嵐ばかりで白ける。
『マトリックス』についてSF作家やSF関係者が語る評論本。『マトリックス・リローデッド』の前に書かれていたようので、続編についての言及はなく絶賛の嵐ばかりで白ける。
しかしここまで、『マトリックス』を構成しているパクリを大々的に肯定するスタンスに立っているのに吃驚した。SFな人たちは基本的にヌルいと思っていたけど、ここまでなあ、画期的とか賛辞ばかり並ぶのもどうよ?難解さを引用して、ハードコアに仕上げているからイイみたいな論調はねえ。これが同年に封切られた『ファイト・クラブ』のB面だという指摘の欠片もなく、『スター・ウォーズ』は子供向けだけど、こっちはもっと深いみたいな調子ばかりだ。日本人はすでにエヴァ騒動を体験しているから醒めつつ読めるんだけどね。
興味深かったのは、ブルース・スターリングが『マトリックス』と現実社会の相似性の考察を、彼が参加した911直後のニューヨークで行われた世界経済フォーラムから紐解くエッセー。借り物のカッコいい外見が生み出す興奮と、それが消費されカネの成る木になることを浮かれずシビアに書いている。いわゆる『マトリックス』現象の本質をついていると思う。SF作家ケヴィン・J・アンダーソンは、『マトリックス』やゲームと現実の暴力との無関係さについての考察で、「暴力的な映画やゲームが犯罪を引き起こすと言うのならば、カード会社のCMは、カード破産に対して責任を負わなければならないはずだ」というのがおもしろかった。
小津安二郎周游田中眞澄:文藝春秋:2667円
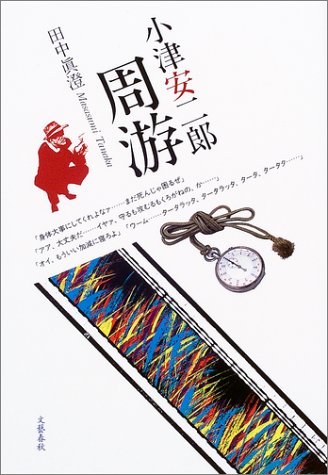 生誕百年ということで、神格化に神格化が重ねられている小津だけど、この本を読まずに語るのはモグリとしか言えない!そんな細かい趣向が山盛りの内容です。いわば小津をめぐるミステリーというスリリングな構成に唸る。いわゆる小津神話をもう一度徹底的に資料を掘り起こすところから作業ははじまる。
生誕百年ということで、神格化に神格化が重ねられている小津だけど、この本を読まずに語るのはモグリとしか言えない!そんな細かい趣向が山盛りの内容です。いわば小津をめぐるミステリーというスリリングな構成に唸る。いわゆる小津神話をもう一度徹底的に資料を掘り起こすところから作業ははじまる。
たとえば、海外から来た小津ファンが必ず訪れる、鎌倉円覚寺にある墓碑に刻まれた「無」という文字は無常の世界を描く小津が気に入っていた言葉である。−−−−−−答えはダウト。死後に兄弟が集まり相談して、戦地の中国から送られてきた手紙に書かれていた文字が「無」だったので故人の好みの文字だろうと推量して決めたということ。
その他にもいくつかのキーワードが出てくる。「野戦瓦斯隊」「ボクサー」「非常時と東京音頭」などなど。著者は資料を紐解きながら、当時の時代や映画史も同時に解読して、小津のその時代の中での位置づけ、松竹や映画界での位置づけを再確認する。そして総体でいままでそこにあるのに見えていなかった、巨匠小津の姿を、時代に生きるひとりの人間であり映画監督を職業とした男として、彼の内面に迫ろうとする。そこに現れたのは、したたかであり偶然も作用して(もちろん才能はあるが)、日本映画の一時代を担った人物が浮かび上がる。
そしてこれははじめてだろう、いままで誰も問題にしていなかった彼の従軍体験がどのような影響を与えたかだが、ドキッとするくらいの事実が発見されている。またいかにして大正のモダン・ボーイが長屋の喜八ものへと作風を変え、戦後は山の手のホームドラマを何度も作るようになったのか、その変化の背景、ミッシング・リンクが見えてきて、いままでバラバラだった作風がなるほどというくらい繋がってくる。
当たり前のことだけど、小津は1930年代から日本映画の巨匠であり、興行成績はいまひとつだが、往事のインテリ層(「大学は出たけれど」な人たち)にだけ受ける一貫して評価は高い監督であり、決して彼が理解されないとか不遇の作家であったことはない。もっと言えばそのローアングルというスタイルだから評価されたわけでもない。
彼の作品が同時代の人間に訴えるものを持っていたということだ。
一時期いかに小津が日本的でないかを、ドナルド・リチーの本を引き合いにして語られたことがあったが、「監督 小津安二郎」のような思いつきのキーワードだけで、いかに非日本的だから本当のところは理解されず、逆に汎世界的だから時代を越えて偉大なのだと書かれた本は、評論としてはちょっと面白いがあまりにも誘導的だと思う。
著者の姿勢はそれと反する。いかにして映画と映画人と観客が同時代を生きたか、その証を平たく資料を集め解読していく。そこから現代に通ずるものを見いだしていく。お陰で読み終わると関連した歴史の本や別の映画の本を読みたくなる。そんな遠近感の広がりを持っていて、読み手を泳がせてくれる。
国際シネマ獄門帖 中野貴雄:有学書林:1500
 「1909年、カナダで5億年前の不思議な化石小動物群が発見された。当初、節足動物と思われたその奇妙奇天烈、妙ちくりんな生きものたちはしかし、既存の分類体系のどこにも収まらず、しかもわれわれが抱く生物進化観に全面的な見直しを迫るものだった…」というのはスティーヴン・ジェイ
グールド著「ワンダフルライフ」の惹句であり、NHKの番組でCGの奇妙な生物アノマロカリスの泳ぐ姿を見た人は多いだろう。
「1909年、カナダで5億年前の不思議な化石小動物群が発見された。当初、節足動物と思われたその奇妙奇天烈、妙ちくりんな生きものたちはしかし、既存の分類体系のどこにも収まらず、しかもわれわれが抱く生物進化観に全面的な見直しを迫るものだった…」というのはスティーヴン・ジェイ
グールド著「ワンダフルライフ」の惹句であり、NHKの番組でCGの奇妙な生物アノマロカリスの泳ぐ姿を見た人は多いだろう。
まわりくどい言い方だけど中野貴雄はまさにそれだ。ヲタクは基本的にぐだぐら文句言っているだけでモノを作らないし、同人誌的は作ることはあるが、模倣(パクリ)だけでがオリジナリティとセンスはない、近頃では世間に適合しているようにみえる種類も発見されている(例:村上隆、宇多田ダンナ)。また最近の老齢化した種ではカネがあるとオトナ買いに走る現象も見られる。などなど。みなさまのまわりにも多く生息していて、その進化の過程は体系立てられ、次世代へと続く揺るぎないものと思われた。
が、彼は違った。種族はヲタクでありながら、ヲタクを罵倒して、オリジナリティ溢れる作品を作りながら、しょーもない部分に心血を注ぐ。アダルトな世界のはずなのに、ガキのバカさ加減で無茶苦茶に突っ走るという、ヲタク生物史では元来存在しないはずのいきものなのだ。
それでいながら映画批評文の辛らつなユーモアは抜群で的確過ぎる。はじめて映画秘宝のムックで文章を読んで以来、いつも驚かされ笑わされてしまう。本書には「デラべっぴん」に書かれたちょっと以前の時評と「秘宝」に紹介されたバカアジア映画が収録されている。その視点は紹介している映画よりおもしろかったりする。
ただね、彼の場合は、ジョン・ウォーターズ的な悪趣味じゃなくて、どちらかというと荒川区の町工場で作られ、夜店の景品として飾ってあって子供も欲しがらない、オリジナルなソフビの怪獣みたいな「本物のバッタモノ」という考えようによっては激レアなヒトなのだけどね…。やっぱ進化の歴史から外れていますなあ。
(でもさ、誰かが人造人間キャシャーンとかアニメ実写化するニュースを聞いても「ふーん」としか思わないけど、これが中野貴雄だったらと考えるとわくわくしてしまうのは正しい反応だと思うんだけど)
映画はやくざなり 笠原和夫:新潮社:1500円
 著者が生前、小説新潮に書いた脚本家生活の「わがやくざ映画」人生、映画芸術に書かれた『あの夏一番静かな海』に対する脚本家としての怒りと見方を示した「秘伝 シナリオ骨法十箇条」、未映画化のシナリオ「『沖縄進撃作戦』」で構成される。「昭和の劇」を読んでいないので比較は出来ないけど、おもしろいです。
著者が生前、小説新潮に書いた脚本家生活の「わがやくざ映画」人生、映画芸術に書かれた『あの夏一番静かな海』に対する脚本家としての怒りと見方を示した「秘伝 シナリオ骨法十箇条」、未映画化のシナリオ「『沖縄進撃作戦』」で構成される。「昭和の劇」を読んでいないので比較は出来ないけど、おもしろいです。
『仁義なき戦い』はある意味では作者にとっては通過点にしか過ぎないし、実録ものは所詮、任侠もののアンチテーゼなので長く続かないと思っていたのは、現場の方々の共通認識だったようですね。個人的には、『顔役』のシナリオで深作と揉めて、「あとの直しはてめえでやれ!」と言って帰ったら、深作が血を吐いて倒れてしまって、部屋で困っているとのそりと、「エー、石井でございますけれどよろしゅうございますでしょうか」と石井輝男が現われ、さっさとホンをまとめて撮ってしまったエピソードが笑える。
「秘伝 シナリオ骨法十箇条」は古いかもと本人が思いながらも、長い間シナリオライターたちが練り上げてきた日本映画の劇作術の肝を余ることなく記録として纏め上げているので必見です。いまはたぶんこれだけじゃ足りないのだけどもね。いまは映像と音響が良いので、「一ヌケ、ニスジ、三役者」なのだろうけど、でもやはりスジが良いに越したことはない(当たり前か)。基本がクリア出来ていない映画は結局つまらないことも確かだ。
笠原和夫がやくざ映画が嫌いだと言っている事は周知の事実だけど、でも一番面白いドラマとしてのネタはやはりやくざであることも事実だとおもう。
ワイルダーならどうする? ビリー・ワイルダーとキャメロン・クロウの対話 ビリー・ワイルダー キャメロン・
クロウ:キネマ旬報社 : 4700
 映画監督キャメロン・クロウが晩年のワイルダーにインタビューをしたもの。ほぼ初めての肉声が聞け、彼らしい警句が満載されていて思わずにんまりしてしまう。いろんな時代に飛びながら確たるテーマ
やクロニクルで編纂されているわけではないが、お喋り感覚が良いです。本人もこれが最後のインタビューだと考えていたようで、鋭い本音が随所にあるように思える。マリリン・モンローとオードリ・ヘップ
バーンの捉え方も感心させられる。
映画監督キャメロン・クロウが晩年のワイルダーにインタビューをしたもの。ほぼ初めての肉声が聞け、彼らしい警句が満載されていて思わずにんまりしてしまう。いろんな時代に飛びながら確たるテーマ
やクロニクルで編纂されているわけではないが、お喋り感覚が良いです。本人もこれが最後のインタビューだと考えていたようで、鋭い本音が随所にあるように思える。マリリン・モンローとオードリ・ヘップ
バーンの捉え方も感心させられる。
『情婦』の撮影の時、リハーサルにチャールズ・ロートンがやってきて、シーンを20通りの演じ方をしてみせて、これとこれを組み合わせたやり方でというと、翌日さらに21番目の演じ方を見つけたといって、昨
日の分と組み合わせて完璧に演じたというのを読んで驚いた。さらにインタビューアーが「ロートンの目だけにきちんと照明が当たってますね」というと「照明をあてたんじゃない。彼が当たるように動いたんだ」と語る。さすが
『夜の狩人』の監督だ。
キネマ旬報の本はいつも高く割りには編集のセンスが悪く、付属資料や写真がひどいのが難点だ。
一言いうたろか 新伍の日本映画大改造 山城新伍: 廣済堂出版 :1359
彼は昔からずっと日本映画について限界を知りながらまともなことをメディアで言い続ける監督だ。この本は北野武 が第二作を撮った頃、タレント監督がわんさと出て、バブルの名残があって、伊丹十三が顔を切られた時代に書かれた
エッセー集だ。作者の日本映画に対する提言は、役者だけでなく製作・監督もやるためにその視点は多岐に及んでいる。
ハリウッドにできないで日本映画にできるものはなにか。どんどん、なにも知らない新人に撮らせてこそ新しい発想が 生まれると言い切るなど、真面目なものが多い。その合間の昔話も面白い。『実録共産党』はスタッフキャストも決まって
いたが、代々木方面で前売り券が捌けそうもないので中止になっただけだとか、中島貞夫は『893愚連隊』でスポニチの賞を取ってから映画がおかしくなった、マキノ映画は長屋民主主義なので、殿様や歴史上の偉人の出てくる話は描か
なかった。勝新が勅使河原宏の映画に出たり、中村錦之助が難しい映画に出たら、二度と大衆の客足は戻らなくなってしまった。そこを切り抜けられたのは市川雷蔵だけだと。ためになります。
エド・ウッド 史上最低の映画監督 ルドルフ・グレイ:早川書房: 2330
エド・ウッドについて生涯を関係者の証言を基に描き出す本書の前半部のダイジェストは、映画『エドウッド』で観る事 ができる。ただ資料が残っていたからカルト監督としていまも語られるのだが、妻がよく捨てずに取っておいたものだ。
仕事で関わりのあった女性がほとんど悪口を言っていないことからも、彼が女性から庇護されていたことがわかる。
雷蔵好み 村松 友視:ホーム社 : 1600
 映画の評伝本には2種類ある。相手を顕揚しその素晴らしさを読者に伝えようとするもの。それとは別に作者が如何にその人物が好きで、それよりも「その人物が好きな自分が好き」という自分についてど
こまでもナルシズムで語るだけで資料的な価値がなんともない、まあ言ってしまえばタレントムックかファン本と変わりのないものがある。本書がそれだ。数人の映画人(それも雷蔵にそれほど近くない人)にイ
ンタビューしてあとはちょっと資料を読んで当時の私はこうで、雷蔵はこうだったろう、と推論に推論を重ねるだけで、人物像にも迫ってない。もちろん新発見もない。こんな本誰が読むんだ?
映画の評伝本には2種類ある。相手を顕揚しその素晴らしさを読者に伝えようとするもの。それとは別に作者が如何にその人物が好きで、それよりも「その人物が好きな自分が好き」という自分についてど
こまでもナルシズムで語るだけで資料的な価値がなんともない、まあ言ってしまえばタレントムックかファン本と変わりのないものがある。本書がそれだ。数人の映画人(それも雷蔵にそれほど近くない人)にイ
ンタビューしてあとはちょっと資料を読んで当時の私はこうで、雷蔵はこうだったろう、と推論に推論を重ねるだけで、人物像にも迫ってない。もちろん新発見もない。こんな本誰が読むんだ?
伊福部昭 音楽家の誕生 木部与巴仁:新潮社: 2600
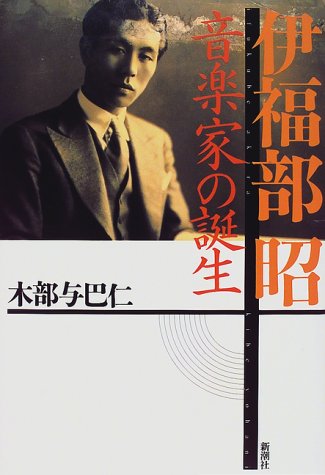 自分の好きな人を顕揚するのにこれほど丹精こめた文章はそうない。本当にやさしい言葉で書かれてこの人の素晴らしさを伝えたいという謙譲の姿勢で書かれている。それだけ伊福部昭も素敵な人なので
あろう。 彼の祖先はオオクニヌシノミコトまで遡れる神官の家。 北海道で生まれ、10代から亡命ロシア人の現代音楽家に見出され、当時から黒沢映画の作曲家として後に有名になる
早坂文雄と交友を結ぶ。そして今も延々と作曲を続ける。300近くも書いたという映画音楽は実は彼の一部でしかないのだ。若い頃に夢中になったのが、ほぼリアルタイムでエリック・サティというのもええっ、と思わせるがよく読む
と理解できるようになってくるし、伊福部という現代作曲家のスタンスも見えてくる。 東京芸大で教鞭を取った最初の授業での言葉がすごい、‘終戦直後の食うや食わずの時代というのに、ダンディな蝶
ネクタイ姿で、開口一番 「定評のある美しか認めぬ人を私は軽蔑する」というアンドレ・ジイドの言葉を引用し「芸術家たるものは、道ばたの石の地蔵さんの頭に、カラスに糞をたれた。その跡を美しいと思うような新鮮な感覚と心を持た
なければならない」’と言ったと生徒の黛敏郎が書き残している。こんなことを言われたら学生は参っちゃうよね。さらに伊福部本人に聞くと、‘もっとも、ジイドの言葉には続きがあるんです。これもまた美しいということを、人よりも先に美
の刻印を押す人、それも私は芸術家と呼ぶ、と。’なぞと平然と言う。うーん。そんな言葉が一杯です。彼の曲を聴きたくなること請け合いです。
自分の好きな人を顕揚するのにこれほど丹精こめた文章はそうない。本当にやさしい言葉で書かれてこの人の素晴らしさを伝えたいという謙譲の姿勢で書かれている。それだけ伊福部昭も素敵な人なので
あろう。 彼の祖先はオオクニヌシノミコトまで遡れる神官の家。 北海道で生まれ、10代から亡命ロシア人の現代音楽家に見出され、当時から黒沢映画の作曲家として後に有名になる
早坂文雄と交友を結ぶ。そして今も延々と作曲を続ける。300近くも書いたという映画音楽は実は彼の一部でしかないのだ。若い頃に夢中になったのが、ほぼリアルタイムでエリック・サティというのもええっ、と思わせるがよく読む
と理解できるようになってくるし、伊福部という現代作曲家のスタンスも見えてくる。 東京芸大で教鞭を取った最初の授業での言葉がすごい、‘終戦直後の食うや食わずの時代というのに、ダンディな蝶
ネクタイ姿で、開口一番 「定評のある美しか認めぬ人を私は軽蔑する」というアンドレ・ジイドの言葉を引用し「芸術家たるものは、道ばたの石の地蔵さんの頭に、カラスに糞をたれた。その跡を美しいと思うような新鮮な感覚と心を持た
なければならない」’と言ったと生徒の黛敏郎が書き残している。こんなことを言われたら学生は参っちゃうよね。さらに伊福部本人に聞くと、‘もっとも、ジイドの言葉には続きがあるんです。これもまた美しいということを、人よりも先に美
の刻印を押す人、それも私は芸術家と呼ぶ、と。’なぞと平然と言う。うーん。そんな言葉が一杯です。彼の曲を聴きたくなること請け合いです。
最後に、ゴジラの映画音楽について‘まあ、自分の背中を見ることができないのは世界で私一人ですから。ゴジラの音楽になぜ人気があるのか。私はこうではなかろうかと感ずるだけで、本当の理由は違うところにあると思います’
テレビの黄金時代 小林信彦:文藝春秋社:1857
 昔出ていた、著者の編纂の「テレビの黄金時代」と同一の書名だが、中身は違う。小林の最近の 芸人ノンフィクションの手法で彼がテレビの現場にいた時代を書いている。これを読むとディープな小林
信彦マニアは(私だ!)、あのフィクションのあの人物は彼がモデルだったのねというのがさらにわかる。逆に読んだ事のあるネタも多いことも確かだ。
冒頭に書かれている「イグアナドンの卵」という芸術祭参加バラエティー番組(!)を有楽町読売ホールで見たことがある。印象は薄い大学生が文化祭でやる観念的な劇のように思えた。ちょっと持ち上げ
過ぎのような気もするのだがその当時を思えば画期的な番組だったのだろう。ただテレビと言う舞台に飛び込み、駈け抜けて行った人たちが活写されてあの人がテレビをどう使ったのか、いわゆるタレントの姿が現われて
いる。青島、永、巨泉、前武、作者自身、もしイレブン PMの司会を引き受けていたらといまでも考えることがあるのだろう。その人間観察も見事だ。今回、日本テレビ内の派閥争いについてもはじめてキチンと書いている。なにがあったの
か。しかし作者の粘着質はすごいと思う。政治風刺をしていながら、実は変節漢だった放送作家三木トリローの実像について、近くにいた神吉拓郎は死ぬまで口を開かなかったことを非難しているところなぞ、執念だなあと思う。他の芸人
シリーズよりも一歩引いた位置から書いているので、いつものセンチさとお友達理解者感覚が前面に出ていないので鼻につくこともない。テレビの通史としてもオモシロイ。
昔出ていた、著者の編纂の「テレビの黄金時代」と同一の書名だが、中身は違う。小林の最近の 芸人ノンフィクションの手法で彼がテレビの現場にいた時代を書いている。これを読むとディープな小林
信彦マニアは(私だ!)、あのフィクションのあの人物は彼がモデルだったのねというのがさらにわかる。逆に読んだ事のあるネタも多いことも確かだ。
冒頭に書かれている「イグアナドンの卵」という芸術祭参加バラエティー番組(!)を有楽町読売ホールで見たことがある。印象は薄い大学生が文化祭でやる観念的な劇のように思えた。ちょっと持ち上げ
過ぎのような気もするのだがその当時を思えば画期的な番組だったのだろう。ただテレビと言う舞台に飛び込み、駈け抜けて行った人たちが活写されてあの人がテレビをどう使ったのか、いわゆるタレントの姿が現われて
いる。青島、永、巨泉、前武、作者自身、もしイレブン PMの司会を引き受けていたらといまでも考えることがあるのだろう。その人間観察も見事だ。今回、日本テレビ内の派閥争いについてもはじめてキチンと書いている。なにがあったの
か。しかし作者の粘着質はすごいと思う。政治風刺をしていながら、実は変節漢だった放送作家三木トリローの実像について、近くにいた神吉拓郎は死ぬまで口を開かなかったことを非難しているところなぞ、執念だなあと思う。他の芸人
シリーズよりも一歩引いた位置から書いているので、いつものセンチさとお友達理解者感覚が前面に出ていないので鼻につくこともない。テレビの通史としてもオモシロイ。
虫プロ興亡記 安仁明太の青春 山本暎一:新潮社:1500
 虫プロという日本のテレビ・アニメーションに神話を作り上げた会社がどのように誕生し何が行われ、そして消えて行ったか。その様子を内部に一人のアニメーター、演出家として立ち会った作者が小説として
書いている。 鉄腕アトム誕生云々は資料が出回っているので割愛するが、虫プロは手塚の会社でもマンガ原作をアニメ化する会社ではなく、実験的なアニメーション映画をつくることを目的として作られた。だから
手 塚は長編映画の製作には直接かかわっていなかったりもする。その辺りの距離感がいままで分か らなかった。主人公が、虫プロの一連のアニメーション映画『ある街角の物語』『クレオパトラ』、『千夜一夜物語』などに演出として
立ち会って手塚カラーとは違う作品を発表していく過程。どんどん手塚の手を離れ、その割には社長としての責任の減らないアニメーション製作会社。そのなかで手塚は実験アニメをやらないのか、営利アニメだけでいいのかと社員にアン
ケートを出したり、どんどんアニメーターたちと疎遠になっていく。そのマンガ家の姿が淋しい。初期の海千山千のアニメーターたちが集まりわいわいと作り上げて行く様子は読んでいて楽しいし、最後までアニメーターの仕事の理想を語る
主人公たちは作り手の心意気を失っていない。虫プロの終わりの頃、虫プロ商事の一人としてヤマトの西崎が現われてくるのも時代かなと思う。虫プロの長編アニメーション映画をちゃんと見てみたいです。
虫プロという日本のテレビ・アニメーションに神話を作り上げた会社がどのように誕生し何が行われ、そして消えて行ったか。その様子を内部に一人のアニメーター、演出家として立ち会った作者が小説として
書いている。 鉄腕アトム誕生云々は資料が出回っているので割愛するが、虫プロは手塚の会社でもマンガ原作をアニメ化する会社ではなく、実験的なアニメーション映画をつくることを目的として作られた。だから
手 塚は長編映画の製作には直接かかわっていなかったりもする。その辺りの距離感がいままで分か らなかった。主人公が、虫プロの一連のアニメーション映画『ある街角の物語』『クレオパトラ』、『千夜一夜物語』などに演出として
立ち会って手塚カラーとは違う作品を発表していく過程。どんどん手塚の手を離れ、その割には社長としての責任の減らないアニメーション製作会社。そのなかで手塚は実験アニメをやらないのか、営利アニメだけでいいのかと社員にアン
ケートを出したり、どんどんアニメーターたちと疎遠になっていく。そのマンガ家の姿が淋しい。初期の海千山千のアニメーターたちが集まりわいわいと作り上げて行く様子は読んでいて楽しいし、最後までアニメーターの仕事の理想を語る
主人公たちは作り手の心意気を失っていない。虫プロの終わりの頃、虫プロ商事の一人としてヤマトの西崎が現われてくるのも時代かなと思う。虫プロの長編アニメーション映画をちゃんと見てみたいです。
金城哲夫 ウルトラマン島唄 上原正三:筑摩書房:2200
 沖縄出身のシナリオライター、金城哲夫はウルトラQから、マイティー・ジャックまで円谷プロの文芸部門の長を務めた。上原正三は同郷の金城を頼り、ウルトラQから円谷プロに出入りをしてその作家活動を
はじめる。今回作者は金城の未公開の日記などを読み、あくまでも上原の視点から金城哲夫というウルトラマンを作った男を描き出す。
沖縄出身のシナリオライター、金城哲夫はウルトラQから、マイティー・ジャックまで円谷プロの文芸部門の長を務めた。上原正三は同郷の金城を頼り、ウルトラQから円谷プロに出入りをしてその作家活動を
はじめる。今回作者は金城の未公開の日記などを読み、あくまでも上原の視点から金城哲夫というウルトラマンを作った男を描き出す。
そこには、いままで存在しないテレビ番組を作り出す企画書を持ち歩くエネルギッシュな男の姿がある。怪獣について理解のない者が「最後に怪獣を殺すだけの話だ」というのを、金城は「そうではなく、怪
獣を元のところに戻すのだ」と説明する。これを読むと、 ウルトラマンだけが殺伐とせずにやさしい印象のあることが思い出される。冒頭に引用される実相寺監督の「ウルトラマン――本籍沖縄」というのがわかるような気がした。た
だ沖縄に帰ってからの姿は読んでいて苦しいものがある。
アメリカ映画の文化史(上下) ロバート・スケラー:講談社学術文庫:各900
 アメリカ映画をその最初から1960年代のニューシネマの頃までを社会科学の方向から切って行く。そこにあるキーワードは、 検閲、トラスト、中産階級だ。
アメリカ映画をその最初から1960年代のニューシネマの頃までを社会科学の方向から切って行く。そこにあるキーワードは、 検閲、トラスト、中産階級だ。
移民相手の商売のニッケル・オデオンは、エジソンがフィルムや機材の独占によって作り出されたトラスト(独占企業体)と非トラストの争いの中で繁栄していく。それも結局非トラスト組みが勝ち、それがハリ
ウッドの基になっていく。そこらの叩き上げが撮影所の主、タイクーンたちだ。 観客として映画産業を支えた中産階級(労働者・移民階級)に対しての 20世紀のアメリカ人のモラル
を規定していくのに映画が利用される。というよりもいかがわしい映画というものに行くことができる免罪符として自主検閲が導入される。その制約のために60年代には世界の流れから取り残されてしまうのも事実だ。反対に言えば、
映画 の検閲を通った「アメリカ式生活様式」がアメリカ中流社会のモラルを作り上げたことを指摘する。フランク・キャプラの在り方などが分かりやすいだろう。もうちょっとウォールストリートとの関係が書かれていればもっと複眼的になった
のに。
松本清張の映像世界 林 悦子:ワイズ出版 :2,200
 松本清張の原作を映像化するための会社、霧プロ。そんなプロダクションを切り盛りをした女性からみた清張のまわりの人間模様。ただみんな原作が欲しいから腰が低い。しかし清張の死後の映像化権
の奪い合いは人間関係のどろどろがそれこそ清張作品のようだ。でもそれほど面白いわけでもなく、だからなんだということも無いのだが。
松本清張の原作を映像化するための会社、霧プロ。そんなプロダクションを切り盛りをした女性からみた清張のまわりの人間模様。ただみんな原作が欲しいから腰が低い。しかし清張の死後の映像化権
の奪い合いは人間関係のどろどろがそれこそ清張作品のようだ。でもそれほど面白いわけでもなく、だからなんだということも無いのだが。
映画は陽炎の如く 犬塚稔:草思社:220
 百歳を越えた、脚本家・監督としての筆者の自伝。まわりはみんな死んじゃったから言いたい放題怖いもの無し。でもそれほど映画史的にみて面白いことが書かれているかというところでの資料的な部
分はどれくらいあるかはちょっと疑問。
百歳を越えた、脚本家・監督としての筆者の自伝。まわりはみんな死んじゃったから言いたい放題怖いもの無し。でもそれほど映画史的にみて面白いことが書かれているかというところでの資料的な部
分はどれくらいあるかはちょっと疑問。
戦前、松竹京都に入り、サイレント時代からシナリオを書き始め、長谷川一夫のデビュー作で監督をするようにもなる。その後阪妻のプロダクションに入ったり、日活に行ったりして、座頭市のライターとい
うのがわかりやすいのではないか。
いわゆる有名監督はほとんど出てきません。松竹京都の周辺の人々が主な登場人物です。しかも、シナリオが良くないと映画はダメだと言って監督をしなくなった人ですから、手厳しい。
長谷川一夫の顔 斬り事件の真相(これはマキノの自伝と読み併せるとおもしろい)。衣笠貞之助の人格の悪さ。阪妻のエキセントリック さ。永田雅一のカツドウヤとしての人物像などが描かれる。
またカツシンについては、座頭市の続編をタダでシナリオを書かされたと裁判を起こして敗れるまでを克明に記録し、 墓石をひっくり返す勢いで罵倒する。そして最後にそのシナリオを掲載するしつこさ。
人間さいごまで生き残った者は強いですな。
タチ 「ぼくの伯父さん」ジャック・タチの真実 マルク・ドンテ:国書刊行会:2400
 ジャック・タチという孤高の作家について当時の評論、証言を膨大な写真とともに振りかえる資料本と言っていいだろう。そこには余計な論評やプライベートの詮索はない。ひたすら真面目である。それゆえ
に退屈だけど。タチのどこまでもモダンな作風はだれにも似ていないし、理解はされることはない。同時代のもうひとりの作家ロベール・ブレッソンは、その禁欲さゆえに論評しやすく模倣されやすいのでいま
も語られるが、タチはまるで違う。それは彼の映画を何回見てもわからないことだと思うけど。彼の映画製作の姿勢はいまも見習うことは多いと思う。
ジャック・タチという孤高の作家について当時の評論、証言を膨大な写真とともに振りかえる資料本と言っていいだろう。そこには余計な論評やプライベートの詮索はない。ひたすら真面目である。それゆえ
に退屈だけど。タチのどこまでもモダンな作風はだれにも似ていないし、理解はされることはない。同時代のもうひとりの作家ロベール・ブレッソンは、その禁欲さゆえに論評しやすく模倣されやすいのでいま
も語られるが、タチはまるで違う。それは彼の映画を何回見てもわからないことだと思うけど。彼の映画製作の姿勢はいまも見習うことは多いと思う。
『プレイタイム』を撮影するためにワンブロック分のビル群をふくむ都市の一角を建設した辺りの記述を読むと、「レオス・カラックス……小さい、ちいさい」と呟きたくなる。
スカイウォーキング ジョージ・ルーカス伝 デール・ポロック:ソニー・マガジン:2000
 最近は何かというと、ジョージ・ルーカスは対スピルバーグの図式で語られることが多いが、実はルー カスの対立軸はフランシス・コッポラ
なわけで、この二人の近親憎悪は消えることはないと思われ る。
最近は何かというと、ジョージ・ルーカスは対スピルバーグの図式で語られることが多いが、実はルー カスの対立軸はフランシス・コッポラ
なわけで、この二人の近親憎悪は消えることはないと思われ る。
お互いがそれぞれに一番なりたい人物であり、またそのネガ像でもある。その距離の取り方が映画産業でスタジオに取り込まれずに、どう生きるかが問われている。大っぴらに面と向かって大手スタジオに
逆らったのは、このふたりだけと言ってもいいだろう。そう、このふたりの原点はサンフランシスコに作られた映画作家たちのための独立スタジオ、アメリカン・ゾエトロープだった。
ここで社長職を任されたルーカスは、田舎町の文房具屋の無口な倅であり、倹約の精神をたたき込まれていた。一方の作曲家の息子のコッポラは大言壮語と浪費癖が直らない、というか考えていなかった。
そのふたりの性格が映画に対する情熱以前の現実問題が立ちはだかった。結局のところスタジオは破綻し二人は決別する。ルーカスは『アメリカン・グラフィティ』の企画を通そうとするが、スタジオは首を縦に振らない。そこで『ゴッドファ
ーザー』で当てたコッポラをプロデューサーに据えることでようやくゴーサインが出る。社交的なコッポラと無口なルーカスの奇妙な関係の一例だ。
映画は大ヒットする。すると、ルーカスはコッポラを拒絶する。実利はルーカスというわけだ。それ以前にルーカスが 『THX1138』を作り、お蔵入りとなったときコッポラは『ゴッドファーザー』でハリウッドで影響力を振り回す。芸術と実利が
あったわけだ。
ふたりを決定的に分けるのは、『地獄の黙示録』だろう。ルーカスの低予算リアリズムのアプローチに対して、コッポラ の大型予算かつ芸術的な作品づくり。ここでも結果は見たとおりだ。ルーカスは自身の企画が滅茶苦茶にされたことで
コッポラと離れていく。
しかしいまの二人を見ると、立場が反対になっているようにみえる。『地獄の黙示録』のカーツ大佐のように自分の城 から出てこないルーカス。小回りの利く実験作品ばかり作るようになっているコッポラ。
と見えるが、もう一度よく考えると、スターウォーズ・サガという個人で実験的な映画を作っているルーカスと、大衆から 喝采を受けようとジャンル映画を作り続けるコッポラ。やはり
このふたりの指向性は似ていることがわかる。
本書は、ルーカスの誕生から、『帝国の逆襲』の頃までの伝記で一応ルーカス公認なので暴露本じゃありません。コッポラとの対立あたりを深読みするとさらに楽しめます。
シネマ坊主 松本人志:日経BP:1000
 言っていることは極めてマトモであり、そのこと自体は驚くことではないけれど、それが意外に映画を識っているように思われてしまうのは、この国にマトモな映画評論がない証拠なのだと思う。まあ見てい
ればわかるけど、数年たてば評価が定まる作品ばかりなので、その時に読み返せば、「なんと普通なことを言っているのか」と思うだろう。逆に松本の下らない自慢話だけが鼻に付くというわけだ。タレント本
なんかはみんなそんなものだけどね。だからその時にはバカ売れするけども、あとは見向きもされない。そんなもんだ。
言っていることは極めてマトモであり、そのこと自体は驚くことではないけれど、それが意外に映画を識っているように思われてしまうのは、この国にマトモな映画評論がない証拠なのだと思う。まあ見てい
ればわかるけど、数年たてば評価が定まる作品ばかりなので、その時に読み返せば、「なんと普通なことを言っているのか」と思うだろう。逆に松本の下らない自慢話だけが鼻に付くというわけだ。タレント本
なんかはみんなそんなものだけどね。だからその時にはバカ売れするけども、あとは見向きもされない。そんなもんだ。
彼の見方はそれほど独自のものではなく、オチがないとアカン。外国の風習はようワカラン。簡単に感動はセエヘン。と普通の感覚であって、テレビの作り手としては真っ当な神経だと思います。雑誌の保
守おやじコラムですな、この人の書いているものは。
ハリウッド・ビジネス ミドリ・モール:文春新書:700
 「映画とは芸術性の高い商品である」この一言を認めるかでハリウッドへの道が開かれる。
「映画とは芸術性の高い商品である」この一言を認めるかでハリウッドへの道が開かれる。
著者はハリウッドでエンターテインメント関係の弁護士を務めている。筆者が驚いたのは契約社会アメリカなのに、ハリウッドの契約概念は非常に甘い
ことだ。口約束が多く、作業が終わった後に契約書を 作ることがザラだという。
具体的な例が多くて楽しめる。『オースティン・パワーズ』のマイク・マイヤーは映画を作りたくなくて言い訳を考えていた。契約書には、彼が全権を握りシナリオを決定出来るとあるのを見つけ、シナリオが気に
入らないと言ってシナリオを書いた自分自身にNGを出して映画制作を延ばした。
クリント・イーストウッドの愛人ソンドラ・ロックと別れるとき、彼女が映画監督になるのを助けたら告訴を取り下げると言われて映画会社ワーナーを紹介する。彼女は第一作は撮れたが次が何年経っても企画が却下され映
画化出来ない。映画会社では全く映画を撮らせる気はなく、ウラでイーストウッドが手を回して、ワーナー経由で彼女の事務所経費を立て替えたりしたというのが真相。慰謝料をケチったということだ。
資金を集めるが赤字なので出資者には戻らないカラクリはすごい。ハリウッドには数字の違う帳簿が4冊あるという事実を暴いた『星の王子ニューヨークに行く』裁判の経緯や、パーセンテージ収入のボーナスを巡るディズニーVSカッツ
エンバーグ裁判。ビデオの権利収入に対するハリウッドの考え方を変遷など資料としても目新しい。
海千山千の強者というよりセコイ奴等が立ち回る世界の話だなあと思う。いまのハリウッドを読むサブテキストにお薦 め。
夏草の道 小説浦山桐郎 田山力哉:講談社:1748
小説と書かれているので真偽の程は定かではないが、映画監督、浦山桐郎の想像の源を、ただただかれのコンプレックス意識に求めているフロイド的な解釈は通俗かつ一方的であろう。小説を書いた本人の手柄にはなるが、書かれ
たモデルにとっては不名誉としかならないものだ。
日活時代の浦山作品の素晴らしさはそんなところに留まらないし、説明がつかない。原一男の本も読まないとなあとは思うのだが、本書のような文脈から逃れられるのかねえ。
人は大切なことも忘れてしまうから 松竹大船撮影所物語 山田太一 田中康義 宮川昭司 吉田剛 渡辺浩:マガジンハウス:3600
 日本映画の黄金期をスタジオ経営会社から描くとき、一番多いのが日活だ。なぜかみんな生き生きとして書かれている。その対極にあるのが本書だ。
日本映画の黄金期をスタジオ経営会社から描くとき、一番多いのが日活だ。なぜかみんな生き生きとして書かれている。その対極にあるのが本書だ。
こんなにみんな罵倒している本は読んだことがない。松竹大船の落ち込みをそのまま活字にしているようだ。橋田壽賀子に至っては消したい過去と言う。そのあたりのパースペクティブの歪みがここに表れ
ている。この本ほどかつて大船で働いた人々に給与の話ばかり聞いている本はないだろう。会社がけちで機材を買ってくれないといいながらも他人の懐具合ばかり気にしている部分がいやだなあ。
またここまで小津安二郎の功罪を明らかにしてのもはじめてではないか。それが裏テーマとも読みとれる。最近の本では小津が古き良き日本映画人の象徴のように思われているけれど、大船じゃ別
格の扱いの特異な例であったことがよくわかる。カメラの厚田雄春も他の監督からはボロクソ言われる。一致した意見としては小津は芸術映画を作ったが、誰も後身を育てなかったし、彼の映画は大船調ではないということだろう。その点
で非常に政治的な人間だったのではないか。
のちにチーフ助監督さえ経験していなかった大島渚がいきなり監督になれたのも、社内的政治力に長けていたことと関係があるだろう。
また大船では小津か木下恵介か渋谷実か誰に付くかで、仕事量やギャラに返ってくるという社内の派閥の論理でみんな汲々としていた。だから外から来る人間との確執がすごかったし、外に出てからも松竹出身だからといって仕事を
することもなかったようだ。
全体に、松竹の通史ではなく個人史の集まりなので偏っている部分が多く、小林正樹の『人間の絛件』がやたらピックアップされたり、松竹ヌーベル・バーグへの言及が多いことはそのあたりを体験した助監督連が多いことでもある。
逆に物足りないのは、野村芳太郎や山根成行のような形で松竹を支えた人物の話がないことである。川島雄三に付いて、軽快な庶民派コメディーを山田洋次、前田陽一、森崎東らとともに築いてきた人物も取り上げるべきなんじゃない
か。わたしの嫌いな『砂の器』が大好きという人は案外多い(なぜか地方の公務員や教師に多かったりする)。そのあたりのメンタリティーをどのように松竹が掬い上げたのか結構気になる。
歪んだパースペクティブのなかで武満徹の言葉が引き立つ。「映画音楽っていうのには特定の法則とか美学っていうのはないように思うんですよ。映画の場合は一本一本が、新しい映画音楽の方法論っていうのを作りだすんではないか
と思っている。」「いろんな不自由がありながら面白いっていうのは、自分が書いた音楽が他の映像と、共同の作業のなかで、違うもののようになっていくからです。(中略)そうね、自分でも予測できないような、予測できなかったように動き
はじめるっていうのかな。」
映画監督の未映像化プロジェクト エスクァイアマガジンジャパン:1600
 ムックとしてはおもしろい切り口だけど、レイアウトが滅茶苦茶で詰め込んだだけという感じで読みづらい。いくつかの情報を拾い読みするには良いだろう。なんか昔のキネ旬世界の映画監督シリーズの
ようだ。作り手の愛情が感じられない。未映像化プロジェクトの紹介も中途半端だ。書きっ放しで、 書かれている内容を編集者が理解しているとは思えない。読むよりも持ち歩いて、スターバックスの
屋外テーブルに飾ってひとに見せるのには適している。
ムックとしてはおもしろい切り口だけど、レイアウトが滅茶苦茶で詰め込んだだけという感じで読みづらい。いくつかの情報を拾い読みするには良いだろう。なんか昔のキネ旬世界の映画監督シリーズの
ようだ。作り手の愛情が感じられない。未映像化プロジェクトの紹介も中途半端だ。書きっ放しで、 書かれている内容を編集者が理解しているとは思えない。読むよりも持ち歩いて、スターバックスの
屋外テーブルに飾ってひとに見せるのには適している。
ディートリッヒ マリア・ライヴァ:新潮社:3,500

マレーネ・ディートリヒがセックス・シンボルというのは長年ピンとこなかった。しかし、彼の娘が書いたこの赤裸々な伝記は、マレーネという不思議な生き物が女性を越えた存在として、どのように築き上げ
られたか克明に描かれている。またそれは背筋が寒くなるほど非人間的でもある。生きるハリウッド・ バビロンだ。
ジョセフ=フォン・スタンバーグが『嘆きの天使』に彼女を見出しハリウッドに招いたのは映画史の事実である。そのとき彼女はすでに娘を生んでいて、娘はマレーネの専属のアシスタントになる。毎日スタ
ジオに通い、きらびやかな衣装のために、すでに身動きが取れないほどになっていた装飾過多のマレーネの手伝いをする。マレーネは映画の衣装も自分で創案し、スタンバーグ以外の監督作品では照明
も自分で決めてうるさい照明チームからも一目置かれたという。
しかし『恋のページェント』を頂点としてスタンバーグとのチームはこわれる。それがディートリヒ映画の最期でもあっ た。はっきり言って大根役者の彼女をマジックでイコンと化したのはスタンバーグであり、ディートリヒの人工美はスタン
バーグの骨頂でもあった。いま思うと ディートリヒの美しさは女性のための美しさのような気がする。この世のものではない人工な美しい存在が受けたのだと思う。それが結果として彼女の一生を支配するのだが。
もうひとつ明らかにされたのが、いつも恋愛をしている彼女の姿。毎晩男を替えていた様子が描かれている。それが 日常である感覚もすごいが、相手がジャン・ギャバンからパットン将軍までと多彩だ。
後年のディートリヒはステージで復活する。特にバート・バカラックと組んだ時代が、かつての脚線美を変わらないサイ ボーグのような肉体を売り物にしてオールド・ファンを喜ばせていた。それも服の下にボディースーツを着用して身体の
線を保っていたというから鬼気迫る。
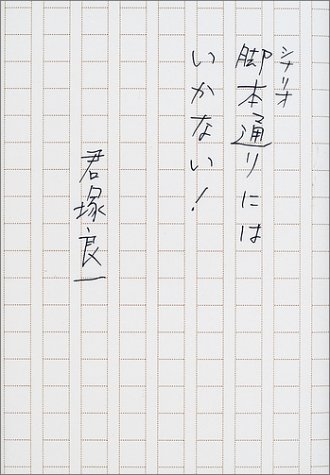 映画が好きでシナリオに興味がある、書きたいけどちゃんとベンキョーせんといけないんだろうなぁと怯んでいる人には最適です。
映画が好きでシナリオに興味がある、書きたいけどちゃんとベンキョーせんといけないんだろうなぁと怯んでいる人には最適です。 映画といえばハリウッド映画、なんでも楽しく観ていたのに、ある日ハワード・ホークスの名前を知ってからは、監督によってこれほど映画のおもしろさが違うことに気付き、以前と同じように喜んで観ることができなくなった貴方にはぜひ読んでもらいたいです。
映画といえばハリウッド映画、なんでも楽しく観ていたのに、ある日ハワード・ホークスの名前を知ってからは、監督によってこれほど映画のおもしろさが違うことに気付き、以前と同じように喜んで観ることができなくなった貴方にはぜひ読んでもらいたいです。 イギリスの撮影監督および監督であるジャック・カーディフのフィルモグラフィーは謎だらけだった。技巧の極致のマイケル・パウエルの『赤い靴』を撮ったと思うと、ジャングルロケの『アフリカの女王』リチャード・フライシャーと組んだと思うと、監督としてマリアンヌ・フェイスフル主演の『あの胸にもう一度』とかB級作品を作っていたりする。その謎が本書を読むとほとんど明かされる。
イギリスの撮影監督および監督であるジャック・カーディフのフィルモグラフィーは謎だらけだった。技巧の極致のマイケル・パウエルの『赤い靴』を撮ったと思うと、ジャングルロケの『アフリカの女王』リチャード・フライシャーと組んだと思うと、監督としてマリアンヌ・フェイスフル主演の『あの胸にもう一度』とかB級作品を作っていたりする。その謎が本書を読むとほとんど明かされる。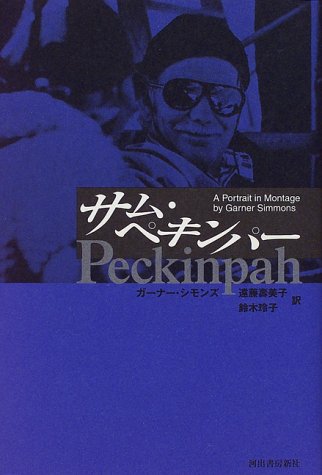 実は原書を持っているのだけど、読まないうちに邦訳が出てしまった。一本一本の映画に沿って、離れた視点から書いているので滅茶苦茶な人だった神話度は低いが、ペキンパーの粘着質で疑り深い性格がよくわかる。
実は原書を持っているのだけど、読まないうちに邦訳が出てしまった。一本一本の映画に沿って、離れた視点から書いているので滅茶苦茶な人だった神話度は低いが、ペキンパーの粘着質で疑り深い性格がよくわかる。 客観的な伝記ではなく読み物仕立てになっているのですが、それほど気にならなかったのは三隅研次についてあまり知識が無いからでしょうか。
客観的な伝記ではなく読み物仕立てになっているのですが、それほど気にならなかったのは三隅研次についてあまり知識が無いからでしょうか。 山下耕作の最後の聞き語りが大半をしめるのだが、この作業の途中で逝去したためなのか、テープ起こしのまま編集されたみたいで、話がポンポン飛んでいて読みづらい。まあそういう記録というのならそれでも良いのかも知れないが。資料的な価値が下がってしまうのではないかなあ。かなりの人を一方的に罵倒しているしね。
山下耕作の最後の聞き語りが大半をしめるのだが、この作業の途中で逝去したためなのか、テープ起こしのまま編集されたみたいで、話がポンポン飛んでいて読みづらい。まあそういう記録というのならそれでも良いのかも知れないが。資料的な価値が下がってしまうのではないかなあ。かなりの人を一方的に罵倒しているしね。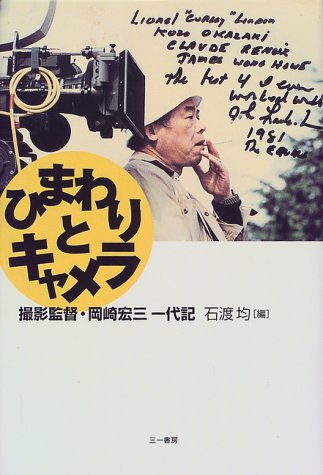 ジョゼフ・フォン・スタンバーグの遺作の『アナタハン』をはじめ、『ザ・ヤクザ』などの海外スタッフや、川島雄三、豊田四郎、小林正樹、木下恵介と組んできて、いまも現役の大正8年生まれのキャメラマン。
ジョゼフ・フォン・スタンバーグの遺作の『アナタハン』をはじめ、『ザ・ヤクザ』などの海外スタッフや、川島雄三、豊田四郎、小林正樹、木下恵介と組んできて、いまも現役の大正8年生まれのキャメラマン。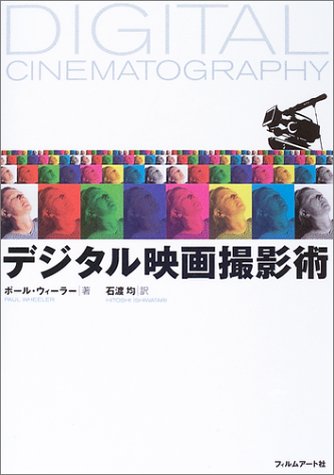 まず題名に異議あり!ここに書かれているのは、プロ用のソニー、デジタル・ベータカム・カメラについてのノウハウであって、デジタル・シネマ・カメラについてではない。両者がどう違うかは端的にいうと、前者はテレビでは高品質な画面を作り出すのには使えるが、後者のように映画フィルムの代わりになるような品質のものではないということだ。(まあ使い分けが一慨にそうも言えないのが苦しいが… 例)『木更津キャッツアイ日本シリーズ』>ありゃ、アナログのベータカム(ようするに普通のテレビカメラ)だけどなあ>商品以前のハナシだろうが!)
まず題名に異議あり!ここに書かれているのは、プロ用のソニー、デジタル・ベータカム・カメラについてのノウハウであって、デジタル・シネマ・カメラについてではない。両者がどう違うかは端的にいうと、前者はテレビでは高品質な画面を作り出すのには使えるが、後者のように映画フィルムの代わりになるような品質のものではないということだ。(まあ使い分けが一慨にそうも言えないのが苦しいが… 例)『木更津キャッツアイ日本シリーズ』>ありゃ、アナログのベータカム(ようするに普通のテレビカメラ)だけどなあ>商品以前のハナシだろうが!) この本を読んでも彼の映画作法は少しも解明されない、映画界に入る前の生い立ちや私生活についてもまったく触れられていないので、その方面から映画を解釈する方々には資料としての価値はありません。
この本を読んでも彼の映画作法は少しも解明されない、映画界に入る前の生い立ちや私生活についてもまったく触れられていないので、その方面から映画を解釈する方々には資料としての価値はありません。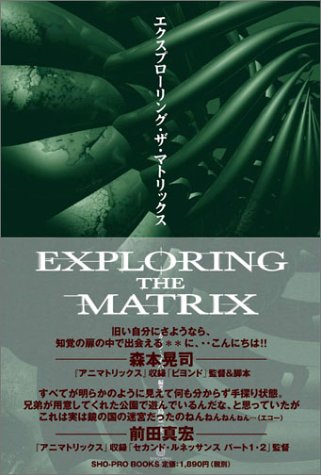 『マトリックス』についてSF作家やSF関係者が語る評論本。『マトリックス・リローデッド』の前に書かれていたようので、続編についての言及はなく絶賛の嵐ばかりで白ける。
『マトリックス』についてSF作家やSF関係者が語る評論本。『マトリックス・リローデッド』の前に書かれていたようので、続編についての言及はなく絶賛の嵐ばかりで白ける。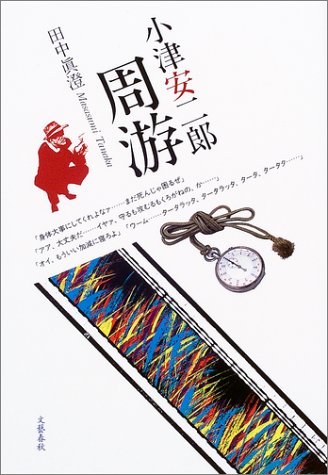 生誕百年ということで、神格化に神格化が重ねられている小津だけど、この本を読まずに語るのはモグリとしか言えない!そんな細かい趣向が山盛りの内容です。いわば小津をめぐるミステリーというスリリングな構成に唸る。いわゆる小津神話をもう一度徹底的に資料を掘り起こすところから作業ははじまる。
生誕百年ということで、神格化に神格化が重ねられている小津だけど、この本を読まずに語るのはモグリとしか言えない!そんな細かい趣向が山盛りの内容です。いわば小津をめぐるミステリーというスリリングな構成に唸る。いわゆる小津神話をもう一度徹底的に資料を掘り起こすところから作業ははじまる。 「1909年、カナダで5億年前の不思議な化石小動物群が発見された。当初、節足動物と思われたその奇妙奇天烈、妙ちくりんな生きものたちはしかし、既存の分類体系のどこにも収まらず、しかもわれわれが抱く生物進化観に全面的な見直しを迫るものだった…」というのはスティーヴン・ジェイ
グールド著「ワンダフルライフ」の惹句であり、NHKの番組でCGの奇妙な生物アノマロカリスの泳ぐ姿を見た人は多いだろう。
「1909年、カナダで5億年前の不思議な化石小動物群が発見された。当初、節足動物と思われたその奇妙奇天烈、妙ちくりんな生きものたちはしかし、既存の分類体系のどこにも収まらず、しかもわれわれが抱く生物進化観に全面的な見直しを迫るものだった…」というのはスティーヴン・ジェイ
グールド著「ワンダフルライフ」の惹句であり、NHKの番組でCGの奇妙な生物アノマロカリスの泳ぐ姿を見た人は多いだろう。 著者が生前、小説新潮に書いた脚本家生活の「わがやくざ映画」人生、映画芸術に書かれた『あの夏一番静かな海』に対する脚本家としての怒りと見方を示した「秘伝 シナリオ骨法十箇条」、未映画化のシナリオ「『沖縄進撃作戦』」で構成される。「昭和の劇」を読んでいないので比較は出来ないけど、おもしろいです。
著者が生前、小説新潮に書いた脚本家生活の「わがやくざ映画」人生、映画芸術に書かれた『あの夏一番静かな海』に対する脚本家としての怒りと見方を示した「秘伝 シナリオ骨法十箇条」、未映画化のシナリオ「『沖縄進撃作戦』」で構成される。「昭和の劇」を読んでいないので比較は出来ないけど、おもしろいです。 映画監督キャメロン・クロウが晩年のワイルダーにインタビューをしたもの。ほぼ初めての肉声が聞け、彼らしい警句が満載されていて思わずにんまりしてしまう。いろんな時代に飛びながら確たるテーマ
やクロニクルで編纂されているわけではないが、お喋り感覚が良いです。本人もこれが最後のインタビューだと考えていたようで、鋭い本音が随所にあるように思える。マリリン・モンローとオードリ・ヘップ
バーンの捉え方も感心させられる。
映画監督キャメロン・クロウが晩年のワイルダーにインタビューをしたもの。ほぼ初めての肉声が聞け、彼らしい警句が満載されていて思わずにんまりしてしまう。いろんな時代に飛びながら確たるテーマ
やクロニクルで編纂されているわけではないが、お喋り感覚が良いです。本人もこれが最後のインタビューだと考えていたようで、鋭い本音が随所にあるように思える。マリリン・モンローとオードリ・ヘップ
バーンの捉え方も感心させられる。 映画の評伝本には2種類ある。相手を顕揚しその素晴らしさを読者に伝えようとするもの。それとは別に作者が如何にその人物が好きで、それよりも「その人物が好きな自分が好き」という自分についてど
こまでもナルシズムで語るだけで資料的な価値がなんともない、まあ言ってしまえばタレントムックかファン本と変わりのないものがある。本書がそれだ。数人の映画人(それも雷蔵にそれほど近くない人)にイ
ンタビューしてあとはちょっと資料を読んで当時の私はこうで、雷蔵はこうだったろう、と推論に推論を重ねるだけで、人物像にも迫ってない。もちろん新発見もない。こんな本誰が読むんだ?
映画の評伝本には2種類ある。相手を顕揚しその素晴らしさを読者に伝えようとするもの。それとは別に作者が如何にその人物が好きで、それよりも「その人物が好きな自分が好き」という自分についてど
こまでもナルシズムで語るだけで資料的な価値がなんともない、まあ言ってしまえばタレントムックかファン本と変わりのないものがある。本書がそれだ。数人の映画人(それも雷蔵にそれほど近くない人)にイ
ンタビューしてあとはちょっと資料を読んで当時の私はこうで、雷蔵はこうだったろう、と推論に推論を重ねるだけで、人物像にも迫ってない。もちろん新発見もない。こんな本誰が読むんだ?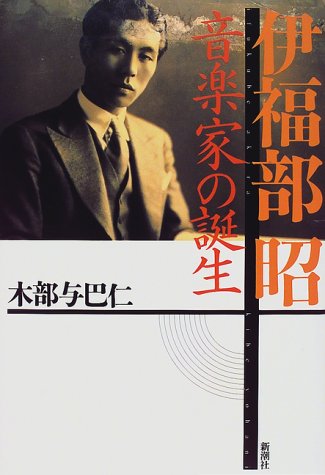 自分の好きな人を顕揚するのにこれほど丹精こめた文章はそうない。本当にやさしい言葉で書かれてこの人の素晴らしさを伝えたいという謙譲の姿勢で書かれている。それだけ伊福部昭も素敵な人なので
あろう。 彼の祖先はオオクニヌシノミコトまで遡れる神官の家。 北海道で生まれ、10代から亡命ロシア人の現代音楽家に見出され、当時から黒沢映画の作曲家として後に有名になる
早坂文雄と交友を結ぶ。そして今も延々と作曲を続ける。300近くも書いたという映画音楽は実は彼の一部でしかないのだ。若い頃に夢中になったのが、ほぼリアルタイムでエリック・サティというのもええっ、と思わせるがよく読む
と理解できるようになってくるし、伊福部という現代作曲家のスタンスも見えてくる。 東京芸大で教鞭を取った最初の授業での言葉がすごい、‘終戦直後の食うや食わずの時代というのに、ダンディな蝶
ネクタイ姿で、開口一番 「定評のある美しか認めぬ人を私は軽蔑する」というアンドレ・ジイドの言葉を引用し「芸術家たるものは、道ばたの石の地蔵さんの頭に、カラスに糞をたれた。その跡を美しいと思うような新鮮な感覚と心を持た
なければならない」’と言ったと生徒の黛敏郎が書き残している。こんなことを言われたら学生は参っちゃうよね。さらに伊福部本人に聞くと、‘もっとも、ジイドの言葉には続きがあるんです。これもまた美しいということを、人よりも先に美
の刻印を押す人、それも私は芸術家と呼ぶ、と。’なぞと平然と言う。うーん。そんな言葉が一杯です。彼の曲を聴きたくなること請け合いです。
自分の好きな人を顕揚するのにこれほど丹精こめた文章はそうない。本当にやさしい言葉で書かれてこの人の素晴らしさを伝えたいという謙譲の姿勢で書かれている。それだけ伊福部昭も素敵な人なので
あろう。 彼の祖先はオオクニヌシノミコトまで遡れる神官の家。 北海道で生まれ、10代から亡命ロシア人の現代音楽家に見出され、当時から黒沢映画の作曲家として後に有名になる
早坂文雄と交友を結ぶ。そして今も延々と作曲を続ける。300近くも書いたという映画音楽は実は彼の一部でしかないのだ。若い頃に夢中になったのが、ほぼリアルタイムでエリック・サティというのもええっ、と思わせるがよく読む
と理解できるようになってくるし、伊福部という現代作曲家のスタンスも見えてくる。 東京芸大で教鞭を取った最初の授業での言葉がすごい、‘終戦直後の食うや食わずの時代というのに、ダンディな蝶
ネクタイ姿で、開口一番 「定評のある美しか認めぬ人を私は軽蔑する」というアンドレ・ジイドの言葉を引用し「芸術家たるものは、道ばたの石の地蔵さんの頭に、カラスに糞をたれた。その跡を美しいと思うような新鮮な感覚と心を持た
なければならない」’と言ったと生徒の黛敏郎が書き残している。こんなことを言われたら学生は参っちゃうよね。さらに伊福部本人に聞くと、‘もっとも、ジイドの言葉には続きがあるんです。これもまた美しいということを、人よりも先に美
の刻印を押す人、それも私は芸術家と呼ぶ、と。’なぞと平然と言う。うーん。そんな言葉が一杯です。彼の曲を聴きたくなること請け合いです。 昔出ていた、著者の編纂の「テレビの黄金時代」と同一の書名だが、中身は違う。小林の最近の 芸人ノンフィクションの手法で彼がテレビの現場にいた時代を書いている。これを読むとディープな小林
信彦マニアは(私だ!)、あのフィクションのあの人物は彼がモデルだったのねというのがさらにわかる。逆に読んだ事のあるネタも多いことも確かだ。
冒頭に書かれている「イグアナドンの卵」という芸術祭参加バラエティー番組(!)を有楽町読売ホールで見たことがある。印象は薄い大学生が文化祭でやる観念的な劇のように思えた。ちょっと持ち上げ
過ぎのような気もするのだがその当時を思えば画期的な番組だったのだろう。ただテレビと言う舞台に飛び込み、駈け抜けて行った人たちが活写されてあの人がテレビをどう使ったのか、いわゆるタレントの姿が現われて
いる。青島、永、巨泉、前武、作者自身、もしイレブン PMの司会を引き受けていたらといまでも考えることがあるのだろう。その人間観察も見事だ。今回、日本テレビ内の派閥争いについてもはじめてキチンと書いている。なにがあったの
か。しかし作者の粘着質はすごいと思う。政治風刺をしていながら、実は変節漢だった放送作家三木トリローの実像について、近くにいた神吉拓郎は死ぬまで口を開かなかったことを非難しているところなぞ、執念だなあと思う。他の芸人
シリーズよりも一歩引いた位置から書いているので、いつものセンチさとお友達理解者感覚が前面に出ていないので鼻につくこともない。テレビの通史としてもオモシロイ。
昔出ていた、著者の編纂の「テレビの黄金時代」と同一の書名だが、中身は違う。小林の最近の 芸人ノンフィクションの手法で彼がテレビの現場にいた時代を書いている。これを読むとディープな小林
信彦マニアは(私だ!)、あのフィクションのあの人物は彼がモデルだったのねというのがさらにわかる。逆に読んだ事のあるネタも多いことも確かだ。
冒頭に書かれている「イグアナドンの卵」という芸術祭参加バラエティー番組(!)を有楽町読売ホールで見たことがある。印象は薄い大学生が文化祭でやる観念的な劇のように思えた。ちょっと持ち上げ
過ぎのような気もするのだがその当時を思えば画期的な番組だったのだろう。ただテレビと言う舞台に飛び込み、駈け抜けて行った人たちが活写されてあの人がテレビをどう使ったのか、いわゆるタレントの姿が現われて
いる。青島、永、巨泉、前武、作者自身、もしイレブン PMの司会を引き受けていたらといまでも考えることがあるのだろう。その人間観察も見事だ。今回、日本テレビ内の派閥争いについてもはじめてキチンと書いている。なにがあったの
か。しかし作者の粘着質はすごいと思う。政治風刺をしていながら、実は変節漢だった放送作家三木トリローの実像について、近くにいた神吉拓郎は死ぬまで口を開かなかったことを非難しているところなぞ、執念だなあと思う。他の芸人
シリーズよりも一歩引いた位置から書いているので、いつものセンチさとお友達理解者感覚が前面に出ていないので鼻につくこともない。テレビの通史としてもオモシロイ。 虫プロという日本のテレビ・アニメーションに神話を作り上げた会社がどのように誕生し何が行われ、そして消えて行ったか。その様子を内部に一人のアニメーター、演出家として立ち会った作者が小説として
書いている。 鉄腕アトム誕生云々は資料が出回っているので割愛するが、虫プロは手塚の会社でもマンガ原作をアニメ化する会社ではなく、実験的なアニメーション映画をつくることを目的として作られた。だから
手 塚は長編映画の製作には直接かかわっていなかったりもする。その辺りの距離感がいままで分か らなかった。主人公が、虫プロの一連のアニメーション映画『ある街角の物語』『クレオパトラ』、『千夜一夜物語』などに演出として
立ち会って手塚カラーとは違う作品を発表していく過程。どんどん手塚の手を離れ、その割には社長としての責任の減らないアニメーション製作会社。そのなかで手塚は実験アニメをやらないのか、営利アニメだけでいいのかと社員にアン
ケートを出したり、どんどんアニメーターたちと疎遠になっていく。そのマンガ家の姿が淋しい。初期の海千山千のアニメーターたちが集まりわいわいと作り上げて行く様子は読んでいて楽しいし、最後までアニメーターの仕事の理想を語る
主人公たちは作り手の心意気を失っていない。虫プロの終わりの頃、虫プロ商事の一人としてヤマトの西崎が現われてくるのも時代かなと思う。虫プロの長編アニメーション映画をちゃんと見てみたいです。
虫プロという日本のテレビ・アニメーションに神話を作り上げた会社がどのように誕生し何が行われ、そして消えて行ったか。その様子を内部に一人のアニメーター、演出家として立ち会った作者が小説として
書いている。 鉄腕アトム誕生云々は資料が出回っているので割愛するが、虫プロは手塚の会社でもマンガ原作をアニメ化する会社ではなく、実験的なアニメーション映画をつくることを目的として作られた。だから
手 塚は長編映画の製作には直接かかわっていなかったりもする。その辺りの距離感がいままで分か らなかった。主人公が、虫プロの一連のアニメーション映画『ある街角の物語』『クレオパトラ』、『千夜一夜物語』などに演出として
立ち会って手塚カラーとは違う作品を発表していく過程。どんどん手塚の手を離れ、その割には社長としての責任の減らないアニメーション製作会社。そのなかで手塚は実験アニメをやらないのか、営利アニメだけでいいのかと社員にアン
ケートを出したり、どんどんアニメーターたちと疎遠になっていく。そのマンガ家の姿が淋しい。初期の海千山千のアニメーターたちが集まりわいわいと作り上げて行く様子は読んでいて楽しいし、最後までアニメーターの仕事の理想を語る
主人公たちは作り手の心意気を失っていない。虫プロの終わりの頃、虫プロ商事の一人としてヤマトの西崎が現われてくるのも時代かなと思う。虫プロの長編アニメーション映画をちゃんと見てみたいです。 沖縄出身のシナリオライター、金城哲夫はウルトラQから、マイティー・ジャックまで円谷プロの文芸部門の長を務めた。上原正三は同郷の金城を頼り、ウルトラQから円谷プロに出入りをしてその作家活動を
はじめる。今回作者は金城の未公開の日記などを読み、あくまでも上原の視点から金城哲夫というウルトラマンを作った男を描き出す。
沖縄出身のシナリオライター、金城哲夫はウルトラQから、マイティー・ジャックまで円谷プロの文芸部門の長を務めた。上原正三は同郷の金城を頼り、ウルトラQから円谷プロに出入りをしてその作家活動を
はじめる。今回作者は金城の未公開の日記などを読み、あくまでも上原の視点から金城哲夫というウルトラマンを作った男を描き出す。 アメリカ映画をその最初から1960年代のニューシネマの頃までを社会科学の方向から切って行く。そこにあるキーワードは、 検閲、トラスト、中産階級だ。
アメリカ映画をその最初から1960年代のニューシネマの頃までを社会科学の方向から切って行く。そこにあるキーワードは、 検閲、トラスト、中産階級だ。 松本清張の原作を映像化するための会社、霧プロ。そんなプロダクションを切り盛りをした女性からみた清張のまわりの人間模様。ただみんな原作が欲しいから腰が低い。しかし清張の死後の映像化権
の奪い合いは人間関係のどろどろがそれこそ清張作品のようだ。でもそれほど面白いわけでもなく、だからなんだということも無いのだが。
松本清張の原作を映像化するための会社、霧プロ。そんなプロダクションを切り盛りをした女性からみた清張のまわりの人間模様。ただみんな原作が欲しいから腰が低い。しかし清張の死後の映像化権
の奪い合いは人間関係のどろどろがそれこそ清張作品のようだ。でもそれほど面白いわけでもなく、だからなんだということも無いのだが。 百歳を越えた、脚本家・監督としての筆者の自伝。まわりはみんな死んじゃったから言いたい放題怖いもの無し。でもそれほど映画史的にみて面白いことが書かれているかというところでの資料的な部
分はどれくらいあるかはちょっと疑問。
百歳を越えた、脚本家・監督としての筆者の自伝。まわりはみんな死んじゃったから言いたい放題怖いもの無し。でもそれほど映画史的にみて面白いことが書かれているかというところでの資料的な部
分はどれくらいあるかはちょっと疑問。 ジャック・タチという孤高の作家について当時の評論、証言を膨大な写真とともに振りかえる資料本と言っていいだろう。そこには余計な論評やプライベートの詮索はない。ひたすら真面目である。それゆえ
に退屈だけど。タチのどこまでもモダンな作風はだれにも似ていないし、理解はされることはない。同時代のもうひとりの作家ロベール・ブレッソンは、その禁欲さゆえに論評しやすく模倣されやすいのでいま
も語られるが、タチはまるで違う。それは彼の映画を何回見てもわからないことだと思うけど。彼の映画製作の姿勢はいまも見習うことは多いと思う。
ジャック・タチという孤高の作家について当時の評論、証言を膨大な写真とともに振りかえる資料本と言っていいだろう。そこには余計な論評やプライベートの詮索はない。ひたすら真面目である。それゆえ
に退屈だけど。タチのどこまでもモダンな作風はだれにも似ていないし、理解はされることはない。同時代のもうひとりの作家ロベール・ブレッソンは、その禁欲さゆえに論評しやすく模倣されやすいのでいま
も語られるが、タチはまるで違う。それは彼の映画を何回見てもわからないことだと思うけど。彼の映画製作の姿勢はいまも見習うことは多いと思う。 最近は何かというと、ジョージ・ルーカスは対スピルバーグの図式で語られることが多いが、実はルー カスの対立軸はフランシス・コッポラ
なわけで、この二人の近親憎悪は消えることはないと思われ る。
最近は何かというと、ジョージ・ルーカスは対スピルバーグの図式で語られることが多いが、実はルー カスの対立軸はフランシス・コッポラ
なわけで、この二人の近親憎悪は消えることはないと思われ る。 言っていることは極めてマトモであり、そのこと自体は驚くことではないけれど、それが意外に映画を識っているように思われてしまうのは、この国にマトモな映画評論がない証拠なのだと思う。まあ見てい
ればわかるけど、数年たてば評価が定まる作品ばかりなので、その時に読み返せば、「なんと普通なことを言っているのか」と思うだろう。逆に松本の下らない自慢話だけが鼻に付くというわけだ。タレント本
なんかはみんなそんなものだけどね。だからその時にはバカ売れするけども、あとは見向きもされない。そんなもんだ。
言っていることは極めてマトモであり、そのこと自体は驚くことではないけれど、それが意外に映画を識っているように思われてしまうのは、この国にマトモな映画評論がない証拠なのだと思う。まあ見てい
ればわかるけど、数年たてば評価が定まる作品ばかりなので、その時に読み返せば、「なんと普通なことを言っているのか」と思うだろう。逆に松本の下らない自慢話だけが鼻に付くというわけだ。タレント本
なんかはみんなそんなものだけどね。だからその時にはバカ売れするけども、あとは見向きもされない。そんなもんだ。 ムックとしてはおもしろい切り口だけど、レイアウトが滅茶苦茶で詰め込んだだけという感じで読みづらい。いくつかの情報を拾い読みするには良いだろう。なんか昔のキネ旬世界の映画監督シリーズの
ようだ。作り手の愛情が感じられない。未映像化プロジェクトの紹介も中途半端だ。書きっ放しで、 書かれている内容を編集者が理解しているとは思えない。読むよりも持ち歩いて、スターバックスの
屋外テーブルに飾ってひとに見せるのには適している。
ムックとしてはおもしろい切り口だけど、レイアウトが滅茶苦茶で詰め込んだだけという感じで読みづらい。いくつかの情報を拾い読みするには良いだろう。なんか昔のキネ旬世界の映画監督シリーズの
ようだ。作り手の愛情が感じられない。未映像化プロジェクトの紹介も中途半端だ。書きっ放しで、 書かれている内容を編集者が理解しているとは思えない。読むよりも持ち歩いて、スターバックスの
屋外テーブルに飾ってひとに見せるのには適している。